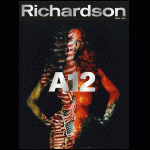坂口健太郎と齋藤飛鳥、近くて遠いふたりの想い
kentaro sakaguchi & asuka saito
model: kentaro sakaguchi & asuka saito
photography: ryutaro izaki
interview & text: rei sakai
edit: manaha hosoda
自然体であること、それは坂口健太郎の魅力のひとつだが、取材の中でみえたのは、彼のしなやかな強さであった。自身の弱さや情けなさ、愚かさを隠すことなく受け入れ、大きく笑い、すべてを包み込むような愛情がある。父性に近い土台をもつ人だ。そうして少しずつ人を巻き込んでいく坂口の横で、自らのペースを崩さず凛と佇むのは齋藤飛鳥。どこか掴みきれない遠さをまといながらも人を惹きつける引力が、本作においても色濃くみてとれる。映画『サイド バイ サイド 隣にいる人』の公開を前に、それぞれの役への向き合い方、作品を通してみえた他者との関係性について話を聞いた。
坂口健太郎と齋藤飛鳥、近くて遠いふたりの想い


本作は “距離感”が鍵を握る作品だったと思います。カメラワークも、主人公の未山一人に没入することなく、すべての人に対して等しく映し出されていたのが印象的です。演者として、距離感を表現するうえで意識されたことはありますか。
坂口:人と話をするときに、なんとなく腕を組んでみたり、足を組んでみたり、鼻を掻いてみたり、自然に出る癖ってあるじゃないですか。それを監督から、全部削ぎ落としてほしいと言われて。立つときも、本当にただ“立つ”ということを大事にしました。ただ座る、とか。これって違和感を感じるんですよね。未山の特異性というか、ちょっと近寄り難い感じは、リアルを削ぎ落としたことで表れた部分もあるなと思います。
齋藤:莉子は、時間が経つにつれて少しずつ心がほぐれていくんです。美々にようやく触れることができるようになったり、詩織さんと目を見て話すことができるようになったり。そういうちょっとした変化が時間の経過とともにあるので、監督と話し合い、このシーンはこのくらい時が経ったから少し砕けた喋り方にしようとか、ちょっと声色を明るく意識してみようとかを決めていきました。
物語の中で、未山が言った「人は結局信じたいものを信じる」という言葉がとても印象的でした。未山と莉子、それぞれが信じたいものって何だったと思いますか。
坂口:最初に台本を一読したとき、未山と莉子はすごく依存の関係だなと思ったのですが、途中から、もしかしたら未山の方が莉子に依存しているのかもしれないと思いました。莉子が未山に求めていることって実はあまりなくて、むしろ未山がやってしまう、そういう動きをしてしまうというか。過去の莉子像も、未山が作ったのかもしれないという感覚があります。



未山は、自分が描いた過去の莉子像や未山像を信じていたし、信じたかったのかもしれないですね。それがたとえ事実とは異なっていたとしても、そこを信じたからこそ生まれた関係性でもあります。莉子が信じていたものについては、どう思いますか?
齋藤:莉子は未山を信じたかったし、信じていたとは思います。ただ、本当は自分を信じたかったんじゃないかな。信じたいけど、自信がないから寄りかかっていた感覚はありますね。
坂口:寄りかかりたいよね。もっと寄りかかるべきですよ、人は。一人じゃ生きていけないんだから。
『サイド バイ サイド 隣にいる人』というタイトルの通り、今回の作品では常に誰かのそばにいたと思いますが、この映画を経て、誰かのそばにいることってどういうことだと思いましたか? 愛や赦しの言い換えにも捉えられるなと思いました。
坂口:必要とすること。よく、愛は自己犠牲だって言ったりするじゃないですか。でも、一緒にいてもその気持ちの方向が交わらなければ、それは一緒にいるだけになってしまいますよね。寄り添う、そばにいるって、多分どこかで求める・求めあわれることがすごく大事な気がしていて。頼らない人たちが多すぎると思うんです。でも、相手を頼る、頼られる、必要とする、必要とされるってとってもいいことだと思うから、そばにいるって、それに少し近いんじゃないかなと思いますね。
齋藤:一人では生きていけないから、必ず隣には誰かがいてくれた方がいいし、いてもらうべきだとは思います。ただ、この作品を観ると必ずしもそこに言葉が必要なわけでも、触れ合う必要があるわけでも、何かアクションをしなきゃいけないわけでもないのかなと思います。未山と詩織と莉子っていう、すごく不思議な三角関係が成立しているのも、そういうことなのかなと思いますね。