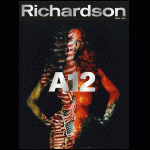ニューヨークで活躍する15人の写真家を捉えた『フォトグラファーズ・イン・ニューヨーク』が公開
©Alldayeveryday
News
ニューヨークで活躍する15人の写真家を捉えた『フォトグラファーズ・イン・ニューヨーク』が公開
Now On Screen; New York Photographer's Documentary Film 'Everybody Street'
最先端のカルチャーが最速で集まる街、ニューヨーク。目紛しく表情が変わるその一瞬を捉えようと多くの写真家たちが街を駆け巡る。
最先端のカルチャーが最速で集まる街、ニューヨーク。目紛しく表情が変わるその一瞬を捉えようと多くの写真家たちが街を駆け巡る。ニューヨークのストリートスナップを撮り続けたファッションフォトグラファー Bill Cunningham (ビル・カニンガム) が亡くなったことも記憶に新しいが、この街には様々な写真家たちが、独自の目線で日々ニューヨークを舞台に活動を続けている。その内の写真家15人にスポットをあてたドキュメンタリー映画『フォトグラファーズ・イン・ニューヨーク』が2016年8月から公開中だ。
監督は、自身もフォトグラファーとして活動し、スケーターたちやグラフィティ・アーティストなど、ストリートのキャラクターを撮り続けてきた Cheryl Dunn (シェリル・ダン)。彼女が選んだ15人の写真家の中には、1930年代からニューヨークを撮り続け、昨年にこの世を去った写真家 Rebecca Lepkoff (レベッカ・レプコフ) や、Magnum Photos (マグナム・フォト) の正会員である Bruce Davidson (ブルース・デビットソン) 、Elliott Erwitt (エリオット・アーウィット)、など錚々たる写真家らが出演している。
様々なアクセントの言語が飛び交い、文化が複雑に混交する舞台で、新旧の写真家たちは何を見つめているのか?これはチャレンジ精神のみを武器に、真実と希望の詰まった一瞬の夢を追い求めて、日夜街をさまよう15人の写真家たちの現在進行形のドキュメンタリー。変わり続ける街で、一瞬の夢を追い求める写真家たちの魂と情熱の記録である。
以下、本作で長編映画初監督を務めた Cheryl Dunn のインタビューを以下ノーカットでお届けする。
— 写真家になった経緯は?
まず、私の家族は全員肉体労働者で、アートをやっている人が一人もいな かったの。私はニュージャージー出身でニューヨークに旅行でいくことがあったんだけど、「いつかここに住んでやる」って思ってたわ。大学で美術史を学びながら、ファッション系の仕事を探すために やっとニューヨークに引っ越したんだけど、理想と全然違ってニューヨークが大嫌いになってしまった。 少し経ってから、当時付き合っていた彼氏がモデルとしてスカウトされ、ミラノに行くことになったの。 「もうこんな街うんざり!クソみたいなオフィスと変な人に囲まれたくないし、私はフォトグラファー になりたい」と思い、お金を貯めてニューヨークを後にしたわ。ミラノではファッション フォトグラファーとして仕事を見つけた。
— ミラノでは彼氏と住んでいたの?
彼氏は一ヶ月ほどでミラノから引っ越したけど、私は2年住んだわ。1週間5ドルぐらいで生活でき たし快適だったし、仕事の関係で様々な場所にも行けた。その後、写真家のアシスタントになるため、 ニューヨークに戻ってきたの。4年半その仕事をした後、商業カメラマンとして自立したわ。その4年半の間、アシスタントをしながらボクシングの写真を撮ってたの。これは仕事としてではなく趣味としてやっていたんだけど、ボクサーを撮り続けることによってスキルが磨かれていったわ。
— ボクシングに興味があったの?
父とボクシングを観て育ったから、幼いころから好きだったわ。ムハメド・アリ世代のボクシングは 特別な輝きがあった。姉と付き合おうとしてた男が、当時アメリカのヘビー級王者レイ・マーサーのマネージャーだったの。その人がニュージャージーのビール醸造所にジムを作って、私はそこに通っていた。当時ボクシング観戦のチケットはとても高くて、テレビで観たい人も、1試合100ドルの放送料を払わないと観れなかった。大衆向けのスポーツとは呼べなかったわ。
ボクシングの世界は人種差別、男尊女卑とバイオレンスが当たり前のように行われる場所なの。男しか許されない世界にポツンっと私がいるわけだけど、ボクシングの知識があった私は、すぐにボクサーたちと交友関係を持てたわ。ボクシング界にいる女なんて、誰かのツレか親戚しかいないから、彼らも最初は私の存在に困惑したはずよ。ボクサーは「男の中の男」っていうイメージを保たないといけないから、あまりボクサー同士で喋ることがないの。私はそこに気づいて、話し相手として近づいていったわ。思った以上にみんな心を開いてくれて、いつのまにか認められていた。
— ストリートフォトグラファーとして成功するには特殊な性格が必要だと思う?取材した写真家に共通するものは何かあった?
共通はしていなかったけど、皆それぞれ何かを持っていて、それを今回の映画で見せたかった。ヴァニティ・フェアが毎年ハリウッド号で「ザ・レネゲード」だったり「ザ・~~~」ってタイトルつける でしょ?それと似ていて、この映画に登場する写真家には何か、その人特有のキャラクター性や特徴があるの。例えば Ricky Powell (リッキー・パウエル) だったら「ニューヨークのクレイジー野郎」ね。Ricky のキャラ性に惹かれて様々な人が彼に近寄っていき、心を開くのよね。その反面、静かなテクニシャン系の写真家もいる。自分の存在感を消すことによって、より自然な写真を撮ることができるの。みんなそれぞれ 持っているものは違うけれど、必ず何かあるわ。
Mary Ellen Mark (マリー・エレン・マーク) は、女性ならではの利点があるって言ってたわ。例えば女性だと、ドアをノックしてすぐ家に入れてもらえることが多いけど、男性だったら信頼してもらうのに苦労する。彼女も私もこれに気づいていて、フルに活用してるわ。ビジネスの面では、女性だからって不公平な扱いを受けることもあるけど、「男尊女卑だ!」って愚痴ってる時間があるなら、頭を使ってやりたいことを成し遂げた方がいいでしょ?
良い写真家に共通するものがあるとすれば「鋭い勘」と「観察力」ね。良い写真家は聞き上手な人と似ていて、自己主張をしないの。ストリートフォトグラフィーは写真家が主人公になったらおしまいよ。
— この映画で一番感心したのは、キャストの多さだよ。
このキャストを集めるのには相当苦労したから、そう言ってもらえると嬉しいわ。何度も「なんで、こんなことしてるんだろう」って思ったわ。知人からは「出演者多すぎない?」って心配されることが多かったけど、どうしても全員入れたかったの。
— 取材したかったけど、できなかった人はいる?
女性の写真家をもっと入れたかった。元々、この映画は美術館から依頼された短い映像作品のはずだったの。制作期間も6月~9月の3ヶ月しかなくて、その間にスケジュールが合う写真家も限られていた。この映画を⻑編として作ろうって決めた後、数人に再度取材のオファーしたらオッケーしてくれたの。Elliott Erwitt (エリオット・アーウィット) がその一人で、クリスマス前日に取材したの。写真家は外にいることが多いけど、クリスマスシーズンになると家族と過ごすために戻ってくるのよね。
一人どうしても出演してくれなかったのが Robert Frank (ロバート・フランク)。実はまだ諦めてないの。小規模なスクリーニングをした時、Michale Stipe (マイケル・スタイプ) が「面白いけど、この映画には Robert Frank が必要だ。 私がなんとかしよう」と言ってくれたの。彼は Patti Smith (パティ・スミス) に連絡してくれて、彼女からRobert Frank に話を振ってもらったの。Robert Frank は過去に Patti Smith が題材の映画を撮っていたから、いけると思ったんだけど断られたわ。一度諦めたんだけど、1ヶ月前に日本のジャーナリストが「友人が Robert Frank の下で働いてるから、聞いてみるよ!」って言ってくれたんだけど、その時には映画はすでに完成していた。すると、その人が「Robert は今ニューヨークにいるよ」と教えてくれて、カメラ片手に彼の家の前で出待ちしようか考えたわ。映画のラストシーンが「失せろ!お前に写真について語るつもりはない!」と怒鳴ってる Robert Frank だったら最高じゃない?正直、もしこのタイミングで取材ができたとしても、 できるかわからないわ。取材一つに私は相当時間を費やすから、疲れ果ててるの。でも、中指立てた Robert Frank を撮るためだったらいつもでいくわ。
— この映画のキャストは写真界の巨匠が多いけど、緊張はした?
キャリアが⻑い写真家を取材したから、インタビューはできる限り準備したわ。Elliott Erwitt は89歳で、Rebecca Lepkoff (レベッカ・レプコフ) なんて96歳。キャリアが⻑いとインタビューは何回も受けてるし、同じ質問も何度も聞かれていると思うの。だから30分という時間を決めて、質問を厳選するのは楽しかったわ。上手くいくと、インタビュー後も話してくれて、交友関係にも繋がったわ。Elliott Erwitt のインタビューは5日間かけて準備した。彼について書かれているものはすべて読み、動画もすべて見たわ。10代の時にキャリアを積み始めて、今年90歳になる人の下調べは大変よ。
— Rebecca Lepkoff は96歳なの?! ( ※取材当時、2014年8月17日にこの世を去った)
そうよ!彼女はフォト・リーグの一員で、ストリートフォトの歴史においてとても重要な人物。何年か前にフォト・リーグについての映画があったんだけど、彼女のパンク精神に驚かせられたわ。私が嫌いなのは映画で年老いた人が登場すると、典型的な老人用の BGM が流れて、いつも同じ空気になるじゃない?この映画ではパンクな Rebecca Lepkoff を見せたかったの。彼女は本当にクールで、今でも「ねぇ、私の展示会くる?」って突然電話かけてきたり、しょっちゅう公園で人の写真を撮っているの。彼女が一員だったフォト・リーグは写真の影響力を世界に知らしめた重要なグループ。元々映画クラブとして始まって、ゆくゆく写真を撮り始めた団体なんだけど、Paul Strand (ポール・ストランド) などが講師をしていた。生徒の大半が貧困に悩まされてたローワーイーストサイドの移⺠の子供たち。生徒たちに自分が住んでいるエリアを撮るよう促していたの。
— 生徒たちのライフスタイルを写真に収めて欲しかったんだね。
そう。あまりにもリアルなスラムが映し出され、アメリカ政府がビビッて「フォト・リーグはコミュニストだ!」と言って、活動停止を命じたの。50年早送りして80年代に入り Clayton Patterson (クレイトン・パターソン) という人物が、1989年のトンプキンズ・スクエア・パークで起こった暴動の一部始終をビデオカメラに収めたの。この暴動はヒドくて、警察が⺠間に暴行を加え、何人もの警察官が辞任させられたの。暴行を加えられた⺠間たちは Patterson の映像を証拠として使い、警察官を訴えて勝ったわ。Patterson は逮捕され、映像が出回らないようにと警察は必死だったの。政府の対応は1930年も1980年もあまり変わらないわね。
— こういう話を聞いていると、何でも記録することが重要だね。
そう、最近起きたボストンマラソン爆弾テロの時もすぐ犯人が捕まったでしょ?あれは写真や動画の証拠があったから、たった2日で捕まったのよ。みんなが常に写真を撮っている社会だと犯罪も起こしにくいはずよ。
— 映画中に出てきた一つのテーマが「被写体との接し方」だったね。Bruce Gilden (ブルース・ギルデン) のように、突然目の前に飛び出て撮るのか、Bruce Davidson (ブルース・デビットソン) や Jamel Shabazz (ジャメル・シャバズ) のように許可を得てから撮るのか。あなたのスタイルは?
その2つの中間かしら。撮っている人に嫌な気持ちはさせたくないけど、撮っていることに気づいて欲しくもないの。私が惹かれるのは自然の中にある一枚で、私がその人と喋ってしまうと、カメラを意識して、自然体ではなくなってしまう。だから、気づいていない時に一枚撮って、もし変な目で見られたら、状況を説明してもう一枚撮ってあげる。この2枚目はもちろん、一枚目とは比べ物にはならないけど、相手を嫌な気持ちにさせないためにやるわ。何度か絶好のシャッターチャンスをワザと撮らな かったこともあるわ。私が撮った写真によって人を傷つけたくないからよ。
— パパラッチとストリートフォトグラファーは似ていると思う?
パパラッチの被写体はいつもセレブ。ストリートフォトグラフィーはそこにいる通行人や普通な人を撮る。両方ともストリートで撮ってるから、勘違いしやすいかもしれないけど、撮る目的が全く違うの。
— Jamel Shabazz を除くと取材した写真家は全員白人で、撮る写真の多くが大都会で暮らす社会的少数派の影がテーマに感じる。リアルな現状を記録するために写真を撮る写真家と、金儲けのためにショッキングな写真を撮る人のラインはどこにあると思う?
良い質問ね。金儲けのために写真を撮るものは雰囲気が違うの。撮られる方もバカじゃない。あなたがどういう意図で写真を撮っているのか、一瞬でバレるわ。本作で登場する Boogie (ブギー) は東ヨーロッパ人なんだけど、彼のバックグラウンドであのコミュニティーに潜入できたのは Boogie だけだと思う。彼は強いセルビア訛りがあるんだけど、それを利用して信頼を得たらしいわ。彼が言っていたのは「俺の英語はアイツらの敵が喋るような英語じゃない」かと言って、いきなりBoogieが入り込んで、無断で撮り始めたわけじゃない。しっかり彼らと信頼関係を築いたのよ。その信頼は写真を使って育めるものでもある。例えば、Bruce Davidson は撮った相手と連絡先を交換し、写真を送ってあげてたの。Jamel Shabazz は毎週金曜日の夜にタイムズ・スクエアかブルックリンに行って、通りすがりの人と話して、写真を撮ってたから「ピクチャー・マン」って呼ばれるようになったの。
— Boogie はセルビアでも写真は撮ってたの?
ええ、過去に撮ってたわ。
— 社会的に無視されているコミュニティーは注目を浴びたいという欲求が強いと思う。だから撮られるのを許可するのかな?
2006年に “It’s All Good, Boogie” という Boogie の本を読んで思ったんだけど、大勢の人から注目を浴びたいってよりは誰でもいいから気にしてほしいんだと思う。私はイーストヴィレッジの Avenue D に住んでるだけど、私のすぐ隣のストリートでは毎日銃声が聞こえるわ。学校を卒業する子なんてほとんどい ない。“It’s All Good, Boogie” に写ってる子が果たして何人生きてるかさえも、わからない。Boogie はあの子たちの写真を撮っていただけではなく、あの子たちに興味を示し、彼らと時間を一緒に過ごしたの。 あの子たちはそれが嬉しかったのよ。Boogie はあの子たちを見下してないし、金のために利用していたわけでもない。後、彼らのことを恐れていなかったのは大きいわね。Boogie は10代を戦時中のベオグラードで過ごしたから、銃は怖くないの。すでに地獄を見てきた人だから、「おい、どんな銃を持って るか見せてくれよ!」って感じで彼はあの子たちに接して行ったわ。社会で声を与えられない彼らに とって銃は彼らの力であり、声でもある。
ストリート・フォトグラファーとして重要なのは真実のみを見せること
Boogie は普段経験することのできない世界をフィルターなしで見せようとしているの。偏見をもって撮っていたら、ああいった写真は撮れないわ。知識と理解は思いやりを産むわ。人種差別主義者や、性差別主義者は単に無知なの。理解した上で真実を映し出すのは悪いことじゃないわ。その真実が見ていて辛いことだとしても。
— 認められるストリート・フォトグラファーになるには未開拓なアンダーグラウンドコミュニティーを探さし出さないとダメだと思う?
そうわ思わないわ。どこに行くんじゃなくて、どれだけそこを深く掘り下げられるかが問題だと思う。 ストリートフォトグラファーって曖昧なポジションで、よく「君たちはジャーナリストじゃない。物語を伝える必要はない。街をパシャパシャ撮ってれば良い」って言われる。しかも、アンダーグラウンドって言葉自体が古臭いと思うの。だって、アンダーグラウンドな場所だとしても、一回ブロガーに書かれれば、そこはもうメインストリームになるでしょ。どれだけ時間を費やし、その場所やコミュニティーを深く掘り下げられるかが勝負よ。写真を5000枚撮り、10枚選び抜くのと、街に出てたった10枚撮るかの違いよ。
— 家を出て、「しまった、カメラを忘れた!」っていう瞬間はある?
あるわ!気づいた瞬間パニックよ。普段は気づいた時点で家に取りに帰るわ。
— フィルム写真は時代の流れと共に無くなっていくと思う?それとも DJ にとってのレコードの様なもの になると思う?
DJ にとってのレコードの様になると思うわ。残念ながら、フィルム写真に興味がある人でも、機材も生産数が少ないから高くなっていて気軽に始められることじゃない。私は幸運なことにフィルムの聖地のような場所に住んでいるからすぐ買えるけど、近くでフィルムを売っているところがなくて困っている友人はたくさんいる。フィルムはこの先、さらに大衆から離れアートの分野に近づいていくと思うわ。倒産していく会社も多いけど、中には Polaroid のように買収されてフィルムを売り続けているケースもあるわ。この世には写真を愛している人が多くいるから、消えはしないと思うわ。 最近、音楽フェスで写真を撮ることが多いんだけど、何千人もの若い子を目にするの。中にはカスタムストラップに可愛いケースに入ったフィルムカメラを首からぶら下げてる子もいるわ。10代はトンがる年頃だから、デジタルではなくアナログに憧れる子も少なくないと思うわ。
— ニューヨークはもう撮り尽くされたと思う?
ニューヨークが撮り尽くされるなんて無理よ。毎日何かが変わる街なの。少し離れただけで戻ってくると、新しいビルが建っていたりする。私の友達が「5年間引っ越してニューヨークに戻ってきたら、見覚えのない街になっていたよ」って言っていて、全く同感だったわ。ニューヨークは昔から常に変わ りゆく街として知られている。様々な国から人々が移⺠してきて、明日新しいレストランが開くかもしれない。ストリートアートもいつ新しいものが出現するか検討もつかないわ。
— この映画のサウンドトラックは素晴らしいと思うよ。
自分が好きな音楽を選んだわ。ニューヨークを彷彿させるような音楽にしたかった。メインで使っているのは私の友達でもある、Endless Boogie (エンドレス・ブギー)。ちゃんとした音楽権利の話はこれからするんだけど、 場合によってはサウンドトラックが大きく変わるかも。あとは、音楽に詳しい友人に「ニューヨークの街を歩いてる時に思い浮かべる音楽は?」って聞いてみたりもしたわ。
— Cat Power の “New York, New York” のカバーも良かった。
あの権利は高くつくわ。Cat Power は友達だけど、Frank Sinatra (フランク・シナトラ) は面識ないから。最初は別の曲をエンディングに使ってたんだけど、しっくりこなくて、「ニューヨーク曲」でググってたらこの曲にたどり着いたの。最初に聴いた時、思わず泣いてしまったわ。その時、色んなことでヘトヘトだっ たってのもあるけど、美しいメッセージがあると思うの。私はヤンキーズの試合前に流れる Jay-Z の曲でもいつも涙しそうになるの。私にとって賛美歌のようなものよ。この2曲は「ニューヨークに憧れて」っていう思いが詰まっていて、私は強く共感できるの。
— ニューヨークでチャンスを掴むってこと?
そう、夢を叶えるチャンスがある街だと思うの。
— 次のプロジェクトは何か動き出してるの?
映像プロジェクトを同時進行で2つ進めてるけど、今は主に I am Other っていうファレル・ウィリア ムズがディレクターのシリーズに取り組んでる。私は Creative Growth っていう、オークランドの障害者 用アートセンターの映像を撮っているわ。かれこれ7年間あそこで撮影しているんだけど、I am Other ではその映像を短いドキュメンタリーシリーズとして配信していくわ。アーティストに取材したり、作品などをメインに紹介していくの。アートを通してコミュニケーションをしている人たちに惹かれて、 そこを追求したわ。
<プロフィール>
Cheryl Dunn (シェリル・ダン)。ニューヨークの写真家・フィルムメイカー。スケーターたちやグラフィティ・アーティスト、バイカー、デモの人々など、ストリートのキャラクターを撮り続けてきた。長編初監督となる今作は、2010年にサウス・ストリート・ミュージアムからの依頼で撮り始めたものだが、映像を納品後に、インタビューキャストを徐々に増やしドキュメンタリー映画として発表された。前衛的なアートから、ストリートカルチャーまでの幅広い題材を、誰しもの心に響かせる映像として昇華させる、才能あふれる女性監督。
| 作品紹介 | |
| 映画タイトル | フォトグラファーズ・イン・ニューヨーク |
| 原題 | Everybody Street |
| 監督 | Cheryl Dunn (シェリル・ダン) |
| 製作 | Cheryl Dunn (シェリル・ダン)、Lucy Cooper (ルーシー・クーパー) |
| 音楽 | Endless Boogie (エンドレス・ブギー) |
| 出演 | Bruce Davidson (ブルース・デビットソン) 、Elliott Erwitt (エリオット・アーウィット)、Jill Freedman (ジル・フリードマン)、Bruce Gilden (ブルース・ギルデン)、 Rebecca Lepkoff (レベッカ・レプコフ)、Mary Ellen Mark (メアリー・エレン・マーク)、 Jeff Mermelstein (ジェフ・マーメルスタイン)、Joel Meyerowitz (ジョエル・マイエロウィッツ)、Martha Cooper (マーサ・クーパー)、 Jamel Shabazz (ジャメル・シャバズ)、Clayton Patterson (クレイトン・パターソン)、Ricky Powell (リッキー・パウエル)、Boogie (ブギー)、 マックス・コズロフ Luc Sante (リュック・サンテ) |
| 製作年 | 2013年 |
| 製作国 | アメリカ |
| 上映時間 | 83分 |
| 配給 | Akari Films |
| 配給協力・宣伝 | プレイタイム |
| HP | akarifilms.co/photographers-in-newyork/ |