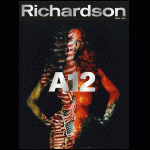『知らない記憶を思い出す』 生湯葉シホ
sponsored
Shiho Namayuba
essay: Shiho Namayuba
photography: So Mitsuya
edit: Miwa Goroku
2021年7月から連載形式でお届けしている CHANEL N°5(シャネル ナンバーファイブ)の100周年アニバーサリー企画。第1章のインタビュー、第2章マイ・フェイバリット、第3章フォトジャーナルに続く第4章は、香水好きでも知られるライターの生湯葉シホさんによる香りのエッセイ。
『知らない記憶を思い出す』 生湯葉シホ
Journal
S先生が入ってくるまで、窓の外はただ白かった。12番教室の教卓に立った先生は、なにかに憑かれたみたいにしばらくぼうっとしていた。先生の視線は座っている学生たちのあいだを通り抜け、窓のほうを向いていた。
雪が降った日の明るさは、晴れた日の明るさと似ているようでまったく違うのですね。きょうの外の白さはまぶしくてちょっと困るくらいですね。純粋経験、というものについてみなさんと考えてみたのが前回でした。額にかざして庇にしていた手を下ろし、先生はそのままひとつながりの台詞のように教科書をめくって読みはじめた。まばらな学生たちも同じように教科書をひらく。一拍遅れ、はっとして窓に目をやると、たしかに外はまぶしいほどに白かった。晴れた日の明るさがすこんと空気を貫くような白ならば、その日の明るさは乱反射するおおきな折り紙を壁という壁に貼りつけたような白だった。
*
趣味でバードウォッチングをする人に、鳥を知ると季節の数が増えますよ、と言われたことがある。鳥の名前を知り、それがどんな気候のもとで活動する鳥かを知ると、晩秋や早春のようなあいまいな季節を見逃さなくなりますよ、と。
その話を聞いているとき、むかし住んでいた家の近所にあったバーのことを考えていた。はじめてそこを訪れた5年ほど前、カウンターに立ち並ぶジンだかウイスキーだかのボトルはどれもZoomの背景のようにぼんやりしていて、それを、とひとつ選んで指し示すことさえためらわれた。
店に通うようになって何度目かのころ、隣の客に勧められて飲んだリキュールから立ち上るばらの香りに驚き、目の前に置かれた瓶の名前をおもわず書き留めたのだった。サンタマリアノヴェッラのリキュールローザ。知ることは忘れないという意志なのだとそのとき思った。いくつかの酒の名前をおぼえ、しだいにカウンターに並ぶボトルの1本1本にピントが合うようになっていくと、まったく知らない酒を頼むのもふしぎと怖くなくなった。
*
忘れられない香りはありますかと私が尋ねると、その女性はさして戸惑う様子もなく、母の、と口にした。それから数秒黙って、なんでしょうあれは、と言った。
なんなんでしょう、あれ。お母さんって、私や父と同じ洗剤を使って同じ空間で暮らしているはずなのに、なぜか家族でひとりだけ違う香りがしませんでしたか? 私がおぼえている限り香水は使っていなかったと思うんだけど、不思議でたまらなかった。母の香りとしか形容できない香りなんですが、そうだな。たとえるなら……
と店内を見渡して彼女が手にしたのはミモザの香水だった。試香紙にワンプッシュすると、華やかでパウダリーな香りの奥に、素肌そのもののようなムスクと薄いバニラの匂いが感じられた。こんな香りでしょうかと言われ、ああ、わかりますなんだか、と答える。私の母はいつもネロリの香水をつけていたから、ほんとうはわかるはずない。ないのだけど、わかります、と思う。
*
20代のはじめに香水を集めるようになってから、常に私の頭にあったのは、母とは違う香りがほしいという思いだった。さらに言えば、母を起点としてこれまで出会ってきたさまざまな大人の女性たち、あらゆる好きな人や嫌いな人とも違う、自分だけの香りがほしい。そう思い、強烈にアニマリックな香りや自分では吸わないタバコの香り、レザーの香りを選んでは悦に入っていた。
ニッチで変わった香りがほしい、という願望の根にあったのは、既視感の軽視と未知のものへの過大評価だったといまは思う。人気の香り、親密な印象の香りから遠ざかれば遠ざかるほど、誰からも連想されない、独自の個性のようなものが手に入ると信じていた。
調香師のジャン・クロード・エレナが、著書『調香師日記』のなかでこんなエピソードを紹介している。ある人がエレナに、「そのつくりものみたいなモノはなんでしょうかね」と尋ねた。それはフルーツサラダのなかに入っていた賽の目状のドラゴンフルーツだったが、西洋人にとっては馴染みのない果物らしい。“こんなふうに対象物をつくりものだと思いこみ、そう言いきってしまうのは、それが未知のものだからである。”“これまで何度も「あなたの香水に入っているのは花などの天然香料だけで、合成香料はいっさい入っていないのですか」と聞かれた。その質問にはいつも、私は天然香料と同じくらい合成香料も使っていて、合成香料がなければ香水はつくれません、と答えている。”“化学のおかげで、私たちは自然のさまざまな制約から解放された。”とエレナは言う。未知と思えるものは実はありふれている、とも、既知のもののなかにも意外な奥行きがある、とも読める話のように感じる。
*
CHANELのN°5を日常的につけている友人をひとりだけ知っている。ファッションもコスメもフリークと呼んでいいほどに好きな人だけれど、香水はそのひとつしか持っていない。
誰もが知っている香りっていうけど、正直、香水じたいつけてる人なんてほんのひと握りじゃん。友だちからもパートナーからも、なんかいつもいい香りだね、としか言われない。たくさんの文脈や記憶を背負っていても、つける人にその重さを感じさせない香りがこれなんだと思う。友人はそう言う。それに、仮に香りがほかの誰かにまつわる記憶を人に連想させたとしても、そのとき、たとえばいま、目の前に立っているのは私だし。
*
つい先日、北国の雪どけのような香りに思えませんか、と紹介された香水を試していたら、あの雪の日の哲学の授業のことを思い出した。
僕はつめたい香りの向こうにどこか求肥のような感触を連想します、と店員さんに言われ、記憶のなかの窓をひらいて12番教室の外に出る。雪を踏みしめてみると、スエードのようなやわらかい起毛を感じる。授業を終えたS先生が、小声で誰かと話しながらタバコを吸っている。3年前にとり壊されてしまった旧校舎の裏で、バスを待つ人たちの手袋の下の指がかじかんでいる。たぶん、ほんとうにそうだったような気がするけれど、そうでなくてもかまわない。思い出すたびに記憶の違ったところが膨らんでいき、空気を孕み、透きとおっていく。不格好な風船のようになった記憶に触れながらいつもの香水を手首に吹きかけるとき、それはまったく新しい、未知の香りに変わっている。