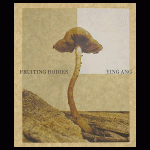孤独を力に変えて。小島秀夫と片岡千之助が語り合う、創造の原点
Hideo Kojima & Sennosuke Kataoka
Model: Hideo Kojima & Sennosuke Kataoka
Photography: Tomoaki Shimoyama
Styling: Shunsuke Okabe
Hair & Make up: Miki Marutani & Rie Aoki
Interview & Text: Daichi Kinoshita
Tailor: Azuna Saito
Edit: Manaha Hosoda & Minori Inoue
ゲームクリエイターとして世界中の人々を魅了し続ける小島秀夫と、歌舞伎の伝統を背負いながら、ルネサンス音楽劇「ハムレット」などの挑戦を通じて現代の表現を切り拓く片岡千之助。一見、異なる二つの世界を生きる両者だが、その創作の根源にあるのは、「孤独」を昇華させた先にある「生き甲斐」への探求だ。
片岡が「映画を観ているような感覚」からハマったと語る小島監督作品。彼の最新作『DEATH STRANDING』(以下デススト)シリーズが掲げる「繋がり」という深いテーマは、孤独な表現者の道に通じるものがある。コジマプロダクションのオフィスで実現した、初めての対談。彼らはなぜ自ら難しい道を選択するのか。そして、なぜその道の先でも多くの人々を魅了し続けられるのか。その力の源を紐解いていく。
孤独を力に変えて。小島秀夫と片岡千之助が語り合う、創造の原点
Journal
—まず、お二人の関係について知りたいのですが、もともとご親交があったのでしょうか?
片岡千之助(以下、S):この対談を機に、ですね。元々僕は一方的に、15年ほど前の小学生の頃から大ファンです。一番最初に遊んだ小島さんのゲームは『オプス(メタルギアソリッド ポータブル・オプス)』。それから逆戻りして、『メタルギア』『メタルギア2』『メタルギア ライジング リベンジェンス』『メタルギアソリッドV ファントムペイン』もプレイして…。もう本当に、それが自分の中での青春でしたし、それがあったことによって育まれた友情もありました。『オプス+』って通信で戦えるじゃないですか。僕、それがすごく強くて周りによく自慢していました…(笑)。
小島秀夫(以下、H):すごく遊んでいただいて…。ありがとうございます。
S:当時から今まで、本当に大ファンです。この対談が決まってから急接近というか、先日は「ハムレット」を観に来ていただきましたし、10周年イベント(「Beyond The Strand」)にもご招待いただきました。
H:僕はもう、千ちゃんのファンですから(笑)。
S:いやいや恐れ多いです。イベントで10周年の軌跡を拝見できて、本当に自分自身もパワーをいただきました。「頑張ろう!」って。
H:この10年を振り返ったら、今も大変ですけど、特に最初は色々大変やったなって思いますね。実はね、今のオフィスのビルも最初は借りられなかったんですよ。それで「どうしよう…」って思っていたら、なぜか突然借りられることになって。よくよく聞いてみると、このビルのオーナーが僕のファンだったんです(笑)。
S:すごい(笑)。結局最後は人とのご縁とタイミングだなとは思いますけど、ここまで持っていらっしゃるとは。
—先日開催された10周年イベント(「Beyond The Strand」)は、IP の強化や現在製作中の『OD』のお話など、非常に濃い内容でしたね。
S:もうね…全てが夢のようです。みんなが考えていることを、小島さんは当然のように超えてくるじゃないですか。夢のような出来事を起こしてくれる。特に印象に残っているのが、この先10年のフェーズについてのお話。10年後のことを具体的に考えてそれに向かって進むって簡単なことじゃないなって思うんです。僕は「10年後どうしたい?」って聞かれても正直分からないですから。
H:達成できる夢って達成してしまうと終わっちゃうんです。例えば、夢が「コジプロに行きたい!」って人は、ここに来た時点で満足してしまう。そこから先どうするか、っていうのが一番重要。だから、叶わないような夢を設定して、それまでの道のりを物差しでマーキングしながら近づいていくというのが、僕は大事だと思っていますね。
—片岡さんはどのようなゲームが特に好きなのですか?
S:僕は結構いろんなジャンルのゲームをやっているんですけど、中でも特にシナリオとかストーリーに惹き込まれるものが好きですね。僕にとっては、映画もアニメもゲームも同じ一つの作品。その物語から人生の教訓を得られるような、深く没頭できる作品を好んでプレイします。それは、小学生の頃は『メタルギア』だったし、今となっては『DEATH STRANDING』シリーズ。ゲームと舞台って全く関係ないって思われるかもしれないですけど、表現の世界としては一番近いところにあるものなんじゃないかなって僕は考えています。小島監督に表現の幅の無限性というか、無限大な感覚を広げていただいていますね。

片岡: ジャケット ¥124,300、パンツ ¥77,000、T シャツ ¥31,900/以上すべて OUR LEGACY (アワー レガシー)、スニーカー/モデル私物
小島: ジャケット ¥423,000、ブーツ ¥129,800/ともに LEMAIRE (ルメール)、パンツ ¥77,000/OUR LEGACY (アワー レガシー)、トップス ¥26,400/SUNSPEL (サンスペル)
—『デススト2』の発売おめでとうございます。シリーズを通して、小島さんが最も大切にされているポイントについて教えてください。
H:シリーズを通して、核となるテーマは「繋がり」なんです。ストーリーもそうですし、ゲームシステムも繋がりを中心に考えています。まず『デススト1』では、繋がることは非常に大変で、繋がった以上は責任を負わないといけない、ということを描きました。例えば、ゲーム内で薬を待っている老人がいて、自分が薬を届けずに、しばらくして行くと死んじゃっているんです。繋がりって、そうじゃないですか。当時のオンラインゲームは、世界中が繋がっているのに、皆が棒(武器)で叩き合うようなゲームばかりだったんですね。せっかく繋がっているんだから、縄(繋がり)のゲームを作りたかったんです。SNS の中傷といったネガティブな繋がりがある中で、もうちょっとこう、緩い繋がりを提案したいという意図がありました。
そして、今作『デススト2』のテーマは、「繋がりすぎるとどうなるか」という諸刃の剣なんです。繋がることによるネガティブな側面も描いています。『デススト1』発売後にコロナがあり、さらに世界を見ていると戦争、紛争が大変な状況になってきました。それを受けて、結局「縄」だけではダメなのか、「棒」もないと世界は一つにならないのか、というような問いかけを『デススト2』でやっているので、その結果として、アクション要素も結構増えることになったんです。
—今作のサムは前作とは違い、仲間が常に近くにいる状況のように感じましたが、その変化の背景は?
H:まず『デススト1』は、サムがルーと二人だけで大陸を横断していく、ものすごい孤独感があるゲームだったんです。だからこそ、見ず知らずの人たちの残したアイコンといった「繋がり」にホッとしたりする。『デススト2』はそうではなく、マゼラン号という船がついてきます。あれはドールマンやレイニーといった、家族ではない人たちが一つ屋根の下で暮らす疑似家族なんですよ。今回は、この疑似家族の中での孤独を描いています。帰る家があるという意味では、『デススト1』の孤独とは違います。ただ、とはいえ、彼らはあくまで他人なんです。サムが血まみれ、泥まみれになって一生懸命に物を運んで帰ってきても、みんなは呑気に遊んでいますし(笑)。そういう、家族がいる中での孤立感といった、前回とは違う新しい孤独を描くために、シナリオを変化させました。前回、「あまりにも寂しすぎる」って言われたのもありますけど。
S:そんな感想が背景にあったんですね(笑)。
—ゲーム監督やシナリオライターは“孤独”が伴うポジションだと思いますが、今作を作る上でドールマンや跳ね橋部隊のような悩みを聞いてくれたり背中を押してくれた仲間はいましたか?
H:全くいないです。この50年間ぐらい。でも、具体的な悩みは言えないんですけど、同じような悩みを持った人とは友達なんです。Guillermo del Toro (ギレルモ・デル・トロ) や Nicolas (ニコラス・ウィンディング・レフン) のようなもの作りしている人たちは、家族にも言えない悩みを抱えて一人で作り続けている。まさに『デススト』と一緒です。1人で歩いていて辛いなと思っていたら、10人ぐらいの同じような足跡を見て安心する。ちなみに、「今、このシナリオのここで悩んでんねん」っていう会話はほとんどしないです。どっちかというと、「こんな面白いこと思いついたで」っていう自慢をしています。
—片岡さんが演じた「ハムレット」も孤独な役だったのでは?
S:そうなんです。その孤独が自分を成長させてくれましたね。一人って寂しいし、苦しいし、悩ましい。監督がおっしゃった通り、誰に聞いても答えは出ない。それこそ、僕にとっての足跡は、自分の祖父だったり尊敬する方々なのかもしれないなって。悩む、苦しむ。だからこそ、それが生き甲斐になっていく。生き甲斐と、悩みや苦しみってものは、絶対的な繋がりというか、その両者がないと、それは生業にならないと思っています。あと、今回の舞台を通じて、初めて自分のルーツに自信が持てたということも大きかったです。役者の家に生まれた人間だから、「役者をやるのは当たり前」という感覚がずっとあったけど、なぜ僕がこの家に生まれたのか、今までの過去を振り返った時に、それがやっと一本の細い線に繋がり始めた感覚があって、何かが始まった感じがしたんです。この苦しめた経験を唯一話せたのは祖父でした。祖父は「よかったよかった、それは大きなプラスやね」と喜んでくれましたね。
H:答えは自分で探すべき。誰も教えてくれないですから。答えを探して悩んでいる人を見たら安心しますね。
S:「いいね〜!」って思っちゃいます(笑)。
—お二人が『デススト2』で特に気に入っている小ネタやギミックを知りたいです。
S:「そこか〜」って言われるかもしれないんですけど、僕はカプセル怪獣のようなシステムです。ウルトラマンが大好きなので。捕まえた BT が召喚できて、あのテーマ曲も流れて…。僕は、監督がウルトラマン好きというのは存じ上げていたので、「ついに、ここで出してきたか!」って感動しました。次は、もしかしたら変身するんじゃないかって思っています(笑)。
H:ちょっと難しくしすぎたかもなって思っています(笑)。僕が気に入っているのは、あるキャラクターがマゼラン号に隠れているところですね。写真撮影モードでたまに後ろにおったり、廊下にちょろっといたり、ムーンウォークしていたりするんです。これはだいぶ気合いを入れて作りました。まだ SNS にはあまり出ていませんね。
S:隅々までやり込む楽しみが増えました。
—片岡さんは大学で西洋演劇のゼミに入ったり、小島さんは新たなゲームジャンルを生み出したり。お二人とも難しい方の道を選択し、切り拓いて活躍されている印象があります。
H:僕は、宇宙飛行士に憧れた世代なんです。冷戦時代の1960年代、前人未到という言葉が好きなんですね。誰もが行ってないところに、勇気と知恵と努力を持って行く、ということにすごく感動する人間なんです。ゲームも同じで、まだ誰もやってない、挑戦していないところへ行きたい、という思いがあります。この年齢でゲームを作っているんですから、人がやってないことをやりたい。そこに自分の旗を立てたいんです。「ここまで来たぞ」という旗を立てて、フォロワーがそこに向かってくる。誰かが到達した道を行くのは、その痕跡を辿っていけばいいので、比較的大変ではないんです。ただ、誰も行ってないルートってなると、失敗すると死んでしまうので、その覚悟でいかないといけない。そこは大変です。ちなみに、ステルスという単語が世に出たのは『メタルギア』が発売されてから10年後なんですよ。最初は賛否両論で叩かれていました。でも、僕はステルスを作りたかったわけじゃなくて、普通とは違う手法でエンタメを作りたかっただけなんです。今もその考えは変わっていません。
S:実は今、歌舞伎役者でありながら2年間歌舞伎の舞台に立っていません。というのも、自分がその家に生まれて歌舞伎の世界にいる中で、「この時代、ただ業界の中にいるだけでは歌舞伎を守れない気がする」と感じたのと、従来の「20代は経験を積む」という歌舞伎役者のテンプレートが、急に自分の中で「違うな」と感じてしまい、一度離れようと思ったんです。本当に歌舞伎命の祖父なのですが、話すと意外と理解してくれました。「今じゃない」という自分の直感を信じています。今回の『ハムレット』を終えて、自分の中でガラッと変わった部分があったので、着実に前へ進んでいると思うんです。たった一回の人生だから、「こうありたい」と自分の中で誓ったことを信じて進む。セーブしてやり直しがきかない人生ですしね。
—最後に、お互いに何か聞きたいことはありますか?
H:僕は今62歳になったんですけど、千ちゃんは37年後の自分のイメージできますか?
S:イメージですか…難しいですね。今と変わらず、ぼーっとしているとは思うんですけど。監督は37年後の99歳の時、何してると思いますか?
H:僕はね、機械の身体をもらって火星で炭鉱を売っている。地球は若者に渡して、そういうのをやりたいですね。