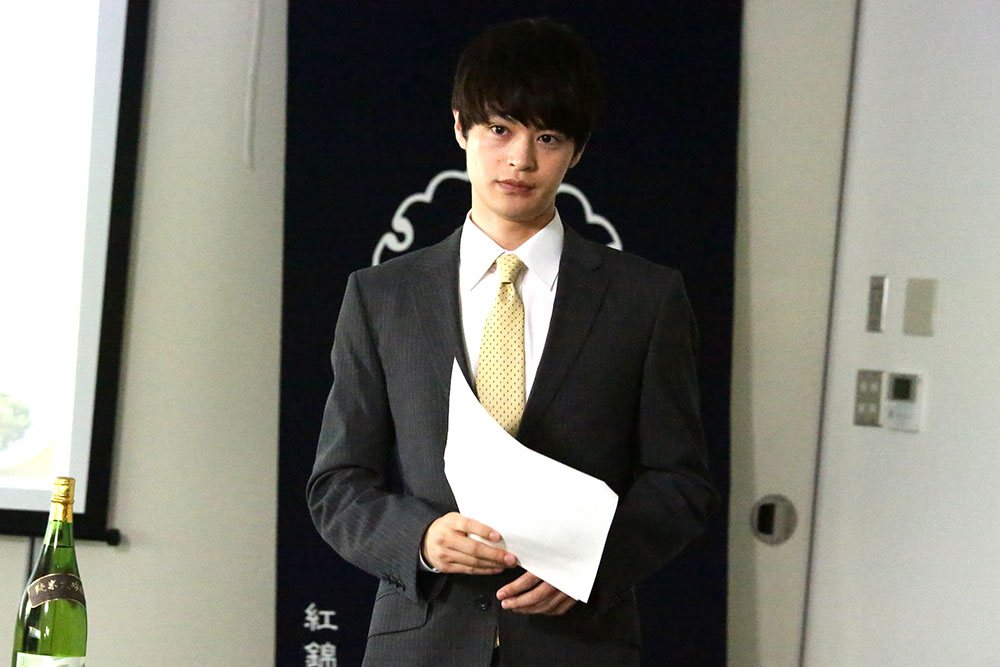映画監督・濱口竜介インタビュー
Ryusuke Hamaguchi
Photographer: Eriko Nemoto
Writer: Tomoko Ogawa
9月1日より公開の映画『寝ても覚めても』で、商業デビュー作となる濱口竜介監督にインタビュー。本作は、第71回仏カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、世界20カ国以上で配給が決定するなど世界中の映画ファンの間で大きな話題となっている。フィクションなのにも関わらず、ドキュメンタリーを観ているような、その物語から離れたくないような映画体験をさせてくれる濱口監督。彼が映画を通して成し遂げたいこととは?
映画監督・濱口竜介インタビュー
Film
ミステリアスな自由人麦と誠実なサラリーマン・亮平。瓜二つの顔を持つ二人の間で揺れ動く主人公・朝子の8年間を描いた作家・柴崎友香の恋愛小説『寝ても覚めても』。本作を映画化を熱望し実現させたのは、メイン女優全員が演技未経験で、総尺5時間17分の大作となった『ハッピーアワー』を監督した濱口竜介だ。監督の商業デビュー作となる『寝ても覚めても』(9月1日公開) は、第71回仏カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、世界20カ国以上で配給が決定している。フィクションなのにも関わらず、ドキュメンタリーを観ているような、その物語から離れたくないような映画体験をさせてくれる濱口監督。彼が映画を通して成し遂げたいこととは?

Photo by Eriko Nemoto
—原作『寝ても覚めても』を読んで、映画にしたいと思わされた一番の魅力はどこにあったのでしょうか?
柴崎さんの他の小説には、本当に綿密な日常の描写が特に視覚的なレベルでずっとあるなという印象で、今作もまあ恋愛は入っていても日常の話なのかな……と思いながら読んでたんです。そうしたら、好きな人にそっくりな男っていうのが結構急に出てきて、意表を突かれて。でも、その瞬間、普段そんな風にはなかなか思わないんですけど、これは映画になるかもなと思いまして。同じ人を本当にそっくりな役として映せば成立してしまうので、自分が今置かれている状況というか、予算レベルでも原作のこの面白さを実現できるなと。それで読み進めると、ラストのほうでまた、「えええ?」と驚く展開があるという。
—確かに驚くエンディングですけど、私は主人公・朝子の正直さが羨ましいなと思ったくらいで、あまり批判的な気持ちにはならなかったんですけど、批判的な意見もあるんだと最近知りました。
結構、あるみたいですね。でも、僕も肯定的に受け止めたんですよね。まぁ、その行動を取られるまでは気がつかなかったけれど、確かに朝子はずっとこんな女性だったと。この人はまさにそのように行動する人だなっていうのが、彼女の選択のその都度あるんですよね。そういう、“深い納得感” と “驚き” があって、めちゃめちゃ面白いじゃないか!っていうことで、これを映画化できたらなという気持ちになったんです。
—柴崎さんが Twitter で、「(略) 顔が同じでも別の人だから関係ない、でいいのに、そうならない。人間の顔ってなんなのか、人間は何を見てるのか」と書いていましたが、監督自身は、本作を通じて「人間の顔ってなんなのか?」と考えたりはしました?
いや、これはね。考えないんですよ (笑)。なぜかって言うと、きっとそれを考えないと小説は書けないと思うんですけれど、物語は既に存在しているし、役者さんに一人二役でやっていただくことも決めているから、映画はシンプルに同じ顔を撮ればいい、ということなんです。だから、その問いはもう観客の皆さんに考えていただければいいかなっていうことで。あくまで自分がその深淵なテーマをですね、僕が考えたかというと、まあぜんぜん考えていないっていう (笑)。答えをこちらが持ってるわけじゃなくて、やっぱり、問いかけそのものを、問いかけのまま映画にしている (笑) っていうことですかね。
—確かに、映画を観たあともその答えについてずっと考えちゃいました (笑)。濱口監督の映画って、フィクションってわかっているのに、そこにいる人たちが本当に生きている感じがすごくしてしまうので。
あくまで、この物語としてリアルっていうことなんだと思います。物語はつくりものなのでリアルじゃないのは当たり前で、でもその物語を進めていくときに、この人にとってはこうする、こう言うことがリアルっていうことが積み上がっていくんじゃないだろうかと思って。この物語の中でリアルを作っていくというか。
—役者さんの感情に嘘がないっていうことですか?
うん、でもそこまで言っていいのかは……。役者さんの中で何が起きてるのかは僕にもわからなくて、ただ人間やっぱり大したもんで、嘘は嘘ってそれなりに見てわかるんだとは思うんですよね。そこで、演技とは嘘であるという事実は動かせないので、その嘘の手がかりを与えないというのが基本戦略になるんじゃないですかね。
—監督が、感情やニュアンスを排したフラットな状態で「本読み」をさせるのも、そのためですか?
「ただセリフを言う」ってことをすると、何か立ち上がるっていうんですかね。演技していることを隠してない状態が現れるんですけど、かえってそのことで演じることの嘘がひとつなくなっていく気がしてます。その一方で不思議なことに、本当にそのやり取りの中で感じた本当の感情が混じってくることも、きっとあるんですよね。今回、唐田えりかさんをオーディションで朝子役に選んだ理由は、声がいいからなんですけど、なんで彼女に決めたのかを最近取材をしていく中で思い出して。マッサージをしながら亮平に「めっちゃ好き」と言うシーンを本読みしてもらったんですけど、最初は参加者の人それぞれが思うように読んでもらって、その後ちょっとニュアンスを抜いてもらう。なんですが、みんな「めっちゃ好き」っていうことはこのくらい気持ちを込めなきゃダメなのかな、と思ってる感じでセリフを言うんですよ。
—ニュアンスが入っちゃうんですね。
そう。「ニュアンスを抜いてください」って言っても、絶対、入ってきちゃう。でも、唐田さんの「めっちゃ好き」は、すごく平坦だったんだけど、そっちのほうがはるかに伝わってきたんですよね。「めっちゃ好き」って言葉の意味のレベルの話だから、それはもう感情を付け加える必要がないんですよね。セリフはセリフで、自分で働くというところがあって。だから、役者がセリフの仕事を邪魔しないことで、かえって観客にとってすごく広がるというか。そして演じる相手にも同じように作用することがあるんだと思います。「めっちゃ好き!」って言われるよりも、すごく平坦に言ってもらったほうが、ああめっちゃ好きなんだな~、っていう気持ちにむしろ前のめりになれるというか。
—確かに、実際なかなか言わない言葉ですしね (笑)。今回、東出昌大さんと唐田えりかさん、演技の経験値の差のあるお二人が主演でしたが、その組み合わせが生み出す魅力というのは感じましたか?
すごく感じましたね。こんなに経験値の差のある人がメインっていうのが初めてだったと思うんですけど、これは本当に面白い。起こるべきことが起こるというか、やっぱり、経験値が少ない人だけだと手詰まりになってしまう瞬間があって。演技経験の少ない人たちは要するに演技というもので自分をコントロールすることに慣れていないので、かえってその人自身が素直に出やすいというのがあるとは思うんですけど、自分ではない人を演じるわけなので、それだけでは発展しないことも多々ある。だから、経験のある人が加わると、そこに道が開けることが結構ある。一方で、経験のある人は、やっぱり、ふりをするとか、そういうことにに慣れすぎてしまうきらいがあると思うんですけど、その経験のない人の真っ直ぐなボールを受けていると、多分きっと何か感じるところがあるんじゃないですかね。お互いに、何か引き出しあっていると感じがしたような気がします。
—原作と異なる映画のオリジナルシーンとして、牛腸茂雄さんの写真がキーとして使われていますが、そこは最初から明確に設定されていたんですか?
だんだん出てきたという感じですかね。牛腸茂雄さんの写真に関しては、原作で、朝子は写真を撮ったり見たりするのが好きだったというのがあって、脚本に「写真展で麦と出会う」ってことを書いてしまうと。「じゃあ、この写真って何の写真なんだ?」という話に映画においてはなるんです。で、「作るのか?」、「いやでも作ったらそのクオリティは大丈夫なのか?」という中で、すごく直接的に、牛腸茂雄さんの写真が思い浮かんでしまった。『SELF AND OTHERS』(2001) という佐藤真監督の牛腸茂雄さんのドキュメンタリーを観ていて、実際写真展にも行っていて、普通に好きだったんですよね。そして、それは多分めちゃめちゃ主題と合っているぞっていう。だから、これは思いついてしまったっていうのがすごくでかいですね。
—そして、震災についても原作には描かれてなかったところですよね。
小説は2008年までの話ですけど、原作にもあるように時代の流れみたいなものを脚本にちゃんと入れ込めるといいということを、共同脚本の田中幸子さんにオーダーした時に、震災をきっかけにして二人の関係が劇的に進展するというその描写があがってきたんです。一応エンターテインメントの映画を作るっていう気持ちでいたので、「大丈夫なのか?」って思ったんですよね。で、自分で脚本を書かせてもらえるペースが来た時に、「いやあ、どうしよう」って思ったけれど、なぜか消せなかった。その理由はたぶん二重にあって、実際にあったこの震災をエンターテインメント映画だからといって消すっていうのはおかしくないか?っていう思いがあったことがまず一つ。もう一つは、自分で脚本を紐解いて構造を考えていくと思うんですけど、単純に主題と合っていた。それは、物事が自分の予想もしていなかった時に急に起こるということ。他からやってくるというか。
—外的な要素によって物事が進んでしまう。
そうです。まったく思いもよらなかったような自分というものを発見してしまう、っていう。まあ全体そういう話だなと。
—麦自体も、震災みたいな人ですしね。
まあ、そうなんですよ (笑)。言ってしまうと、完全にそういうことだなということがあって。ただ、アイテムみたいな使い方に見えないようにしないといけないと思って。でもそれってどういうことなのかなと考えた時に、もう背景というのじゃなくて、震災を真正面から扱うというか、物語の血肉として組み込もうと。なので、結果的に東北に行くという描写になっていったんだと思います。
—本作で商業デビューとのことですが、インディーズとの一番の違いはどこでした?
まあその、本当に端的に規模が違いますよね。人が多いし、場所も多い。それをどう扱っていったらいいのかを、試行錯誤したところはありましたけれど……。ただ、一人一人自分でちゃんと考えられる人が増えていくというのは、作品にとってはものすごい可能性なんだなあと思いました。特に演技に関しては指示をそんなに出すわけではないので、役者さんたちが自分で考えて加えてくれたものっていうのは、ちゃんと映画に映っているなあという気はしていて。多様なキャストが集まってくれて、本当にそこは良かったなあと。それはこの規模の映画じゃないと絶対にできなかったことだと思いますね。
—今回、カンヌ映画祭の公式上映でも喝采されていましたが、監督は賞についてはどういう考えをお持ちですか?
いやあ、僕はなによりまず単純に映画好き、というところがありまして。そうすると、どういうことがわかるかというと、別に映画祭に出ていても、映画祭で賞を獲っても、つまらない映画というのは山とあるってことなんですよ。賞=作品の評価としてあまりダイレクトには受け止めすぎないところはありますよね。ただ、映画祭に選ばれたりっていうことがあると、何よりも、周りの人が喜んでくれる。それは本当にありがたいことだなって思いますね。映画づくりって、結局ゴールが見えづらいことだと思うんですよ。特にスタッフとかキャストにとっては。だから、自分たちの作ったものが良いものだったんだっていうことを世間が表明してくれるっていうのは、ものすごく力になることだと思います。

Photo by Eriko Nemoto
—監督が、映画を通して成し遂げたいこととは何でしょうか?
ドキュメンタリーの経験を通じて思うのは、本当に、カメラってドキュメンタリーと相性がいいんだなってまず思うんですよね。フィクションの時に到達できなかったようなものっていうのが、ドキュメンタリーだと撮れたような気がする。それはやっぱり、ものすごくシンプルな「本当にそうである」ってことの力なんです。それを記録して見せるという単純な構造がドキュメンタリー映画にはあって、それがカメラの正しい使い方という感じがするんですよ。それとは逆に、これは僕の師匠でもある黒沢清さんが言っていることで、カメラを使ってフィクションで物語を語ろうなんていうのは、土台破綻していると。なぜなら、役者がそのキャラクターではないのは明らかであって、あくまで役者がキャラクターを演じている、そのリアルが記録されるということを黒沢さんが言っていて、これもまったくその通りであると。
—ほう。
だとすれば、そのようなリアルを写しとってしまうカメラを使って、人を本当に説得するようなフィクションを作ることができたら、それはすごいことなんだ、ということを思うようになるんですよね。だから、このフィクションを語るにはまったく向かないこのカメラという道具を使って、演技というどうやら最悪の組み合わせらしいものを記録しながら、一体どうやったら人が納得するような映画を作れるのか、フィクションとして語ることができるのかっていうのは、自分のすごく大きな興味というか……。本当でないと明らかにわかっているにも関わらず、これは本当なのだとしか思えないと信じられるものを、一体どうやったら作れるのか?っていう。
—ものすごく不可能なことに挑戦している、ということですね。
そうです、不可能な遊び (笑)。決して解決しないこの問題を使って、ずっと遊んでいられるっていう。
—それはいい仕事ですね (笑)。
いやあ、いい仕事ですよ (笑)。ずっと作り続けたいなと思いますよね。カンヌに行った後、「次が大事ですよ」って言ってくる人がすごくたくさんいて。なんか、「うるせえなあ」と思うわけですよ (笑)。大事に作らなかった作品はないですが、一方で常にいい加減な気持ちで作っている部分もあるので、その感じも大事に恐れず作っていきたいと。できればいろいろ失敗しながら作り続けていきたいなと。だって不可能なことをやっているんですから、失敗ぐらいしますよっていう (笑)。その失敗できる環境をどう整備するかだなと思っています。
—最後の質問なんですけど、監督はどんな距離感で流行というものとお付き合いされているのかなと。
いやいや、流行って、やっぱり昔から憧れますよね。“この流行に決して乗れない俺” みたいなものがずっとあるので…… (笑)。どっちかと言うと、乗れるものなら乗ってみたいっていう気持ちは常に持っています。ただ、流行と私の間の絶対的な距離、みたいな、そういうものがありまして。その距離がですね、やっぱり自分が監督をすると、エライものでそのまま記録されてしまうっていう感じがあるなと思ってはいるんです。とはいえ、流行っていうものを、否定的に捉えたくないっていう思いは常に持っているので、「乗れてはいないが、その端っこだけでも掴みたい」みたいな、そういう気持ちでやっていて。
—流行の端っこだけを掴みたいという気持ちはなんだかわかります。
流行が映っているものは絶対古びていくんですけれども、それがいいなと。昔の映画を見ていると、どんだけ超然としたような映画を撮ってる人でも、なんがしかの流行というかその時のモードはやっぱ映ってるんですよ。で、それって絶対古びてしまって、「ああやっぱりこういうことやってたんだね」みたいな気持ちで見るんですけど、それがとても貴重な資料でもあるし、それでも変わらないものがあるということもわかるので、流行が映画に映ってるっていうのは、とても大事なことだと思います。

Photo by Eriko Nemoto
<プロフィール>
濱口竜介 (はまぐち りゅうすけ)
1978年12月16日、神奈川県生まれ。2008年、東京藝術大学大学院映像研究科の修了制作『PASSION』がサン・セバスチャン国際映画祭や東京フィルメックスに出品され高い評価を得る。その後も日韓共同制作『THE DEPTHS』が東京フィルメックスに出品、東日本大震災の被害者へのインタヴューから成る『なみのおと』『なみのこえ』、東北地方の民話の記録『うたうひと』(共同監督:酒井耕)、4時間を超える長編『親密さ』、染谷将太を主演に迎えた『不気味なものの肌に触れる』を監督。2015年、映像ワークショップに参加した演技経験のない女性4人を主演に起用した5時間17分の長編『ハッピーアワー』を発表し、ロカルノ、ナント、シンガポールほか国際映画祭で主要賞を受賞。一躍その名を世に知らしめた。自らが熱望した小説「寝ても覚めても」の映画化である本作で、満を持して商業デビュー。第71回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に選ばれるという快挙を果たし、世界中から熱い注目を集めている。
| 作品情報 | |
| タイトル | 寝ても覚めても |
| 監督 | 濱口竜介 |
| 出演 | 東出昌大、唐田えりか、瀬戸康史、山下リオ、伊藤沙莉、渡辺大知 |
| 配給 | ビターズ・エンド、エレファントハウス |
| 制作年 | 2018年 |
| 制作国 | 日本・フランス |
| 上映時間 | 119分 |
| HP | www.netemosametemo.jp |
| ©2018 映画「寝ても覚めても」製作委員会/ COMME DES CINÉMAS | |
| テアトル新宿、ヒューマントラストシネマ有楽町、 渋谷シネクイントほか全国公開中 | |