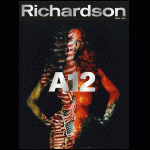ゾンビ映画を通してジム・ジャームッシュが伝える処世術
Jim Jarmusch
interview & text: mikiko ichitani
translation: akemi nakamura
長編デビュー作『パーマネント・バケーション』(1980) 以降、様々なテイストの作風を打ち出し、そのたびに熱狂的な映画ファンの心を掴んできたインディペンデント映画界の巨匠 Jim Jarmusch (ジム・ジャームッシュ)。彼の最新作となる『デッド・ドント・ダイ』が、世界的なパンデミックによる公開延期の困難を乗り越え、日本でもついに6月5日(金)より公開した。
ゾンビ映画を通してジム・ジャームッシュが伝える処世術
Film
『ミステリートレイン』(1989) や『コーヒー&シガレット』(2005) など、オフビートな作風で日本でもカルト的人気を誇る Jim Jarmusch。前作『パターソン』(2017) では、“何も起こらない” 普遍的な日常を映画の中で丁寧に描き、彼のブレない世界観を見事に表現しきったのも記憶に新しいだろう。そんなアメリカ映画界の巨匠が最新作に選んだのは、なんとゾンビ映画。これまでも、西部劇『デッドマン』(1995)、吸血鬼映画『オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ』(2013) など数々のジャンル映画に挑戦してきたが、そのどれもが従来の型にはまらない作品ばかり。本作でもそんな “ジャームッシュ節” が見事に炸裂している。
アメリカの警察官が3人しかいない平和な街に突如大量のゾンビたちが現れるという王道のストーリーでありながら、近年の人気ゾンビ作品とは何かが違う。「ウォーキング・デッド」のようなシリアスさはなく、『新感染 ファイナル・エクスプレス』(2016) のように過激でもない。George A. Romero (ジョージ・A・ロメロ) によるゾンビ映画の金字塔『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』(1968) にオマージュを捧げた本作は、恐怖や疾走感というゾンビ作品に期待される要素を潔く切り捨て、牧歌的な緩さやユーモアを盛り込んだ Jim Jarmusch ならではのゾンビ映画に仕上がっている。コロナウイルス感染症の世界的流行により、図らずも現実とリンクする場面も多く、ところどころ消費社会への風刺も効いているのもポイント。コーヒーやwi-fi、ファッションといった生前の欲求に従ってさまよう屍たちは可笑しくもあり、どこか親近感を覚えてしまう人も多いはず。常に独自のまなざしで世の中を捉えてきた Jim Jarmusch に、映画作りにおける考え方や、これからの世界を生き抜く秘訣などを語ってもらった。
—本作では、メインキャスト以外にも多くの個性豊かな俳優陣が登場しています。このようなキャスティングについて、最初の段階からイメージされていましたか?
これまでにも、『デッドマン』や『コーヒー&シガレッツ』(2003) のような作品で大人数のキャストというのはやってきているのですが、そもそも僕自身が好きな監督の作品に大人数キャストのものが多いような気がします。例えば Wes Anderson (ウェス・アンダーソン)。彼の場合は、素晴らしい俳優ばかりを集めて、小さな役にまで割り振っている。俳優たちもそういうアイディアを気に入ってやっているように見えますよね。そんな彼のようなやり方をすごく尊敬しています。それから Paul Thomas Anderson (ポール・トーマス・アンダーソン) も、それぞれすごく才能がある幅広いキャストを起用したりしていますね。映画の歴史を振り返ってみても、多くの俳優を起用した素晴らしい作品がたくさんある。例えば『おかしなおかしなおかしな世界』(1963) とか、60年代初期の『予期せぬ出来事』(1963)、Blake Edwards (ブレイク・エドワーズ) 監督の『グレートレース』(1965) とか。つまり、優れた俳優達を多くキャストするという前例が映画の歴史にはこれまでもあったわけです。
僕の場合は、今回の脚本を書いている時から、僕が一番好きな俳優ばかりに出てもらおうと思っていました。それで彼らがやりたいと言ってくれるかどうか見てみよう、という感じでね。また、これまで仕事をしたことがなかったような俳優とも仕事がしたいと思いました。例えば Caleb Landry Jones (ケイレブ・ランドリー・ジョーンズ)とか、Danny Glover (ダニー・グローバー) は長年好きだったんだけど、これまで一度も一緒に仕事をしたことがなかったし、Austin Butler (オースティン・バトラー) も才能のある若い俳優で注目していました。それから Selena Gomez (セリーナ・ゴメス) も昔から尊敬していて仕事をしてみたかった女優の1人ですね。結果的に、今回多くの素晴らしい俳優と一緒に仕事できて、本当にラッキーだったし、すごく撮影が楽しみでした。
—なかでも、Bill Murray (ビル・マーレイ) や Iggy Pop (イギー・ポップ)、Tom Waits (トム・ウェイツ) などはあなたの作品を語る上で欠かせないキャストだと思います。改めて振り返ったときに、あなたが何度も仕事をしたくなるキャストたちに共通する部分はなんでしょうか。
僕はいつも俳優をすごく本能的に選んでいるので答えるのが難しいですね。実際に会った時のバイブスとか。会うことで自分が好きかどうか分かるから、自分の本能を信頼してきての結果ということになる。それを分析して答えるのはちょっと難しいんです。ただ彼らに共通して言えるのは、人間的にも素晴らしくて、お互いが尊敬できて、コラボレーションができる俳優だということ。それは間違いない。つまり、一緒に何かを作ろうとしてくれる人だと思います。そして僕のアイディアを僕が考えている以上のものにしてくれる人達であるということは間違いないですね。

© 2019 Image Eleven Productions Inc. All Rights Reserved.
—ご自身の世界観を保つために衣装のこだわりなどはありますか。
衣装や、小道具、アートディレクションなどは僕にとってはすごく重要な要素です。ディテールには相当こだわって作ってきました。そういう部分はひとつひとつの積み重ねでできるわけで、その過程が僕は映画作りの中でもすごく好きな部分です。衣装デザイナーは、前作の『パターソン』から引き続き Catherine George (キャサリン・ジョージ) が担当しています。彼女はニューヨークに住んでいて、『スノーピアサー』(2013)、『オクジャ』(2017) といった Bong Joon Ho (ポン・ジュノ) 監督の作品も多く手がけています。衣装を決める一番最初の段階では、プロダクション・デザイナーなどのアート部門、カメラマンと一緒に各自がもちよったアイデアを出し合って、そこから、みんなのアイデアをまとめて僕から彼女に渡すという流れになっているんですが、彼女は本当に最高で、僕たちが求めているすべてを見つけてきてくれるんですよ。彼女みたいな素晴らしい人達と一緒に仕事ができて本当にラッキーだと思います。
—具体的にはどのようなこだわりだったのでしょうか?
ゾンビの衣装に関しては、色々なものが混じった感じにしたいと伝えました。というのも、この作品にでてくるのは様々な時代からやってきたゾンビだから。ゾンビの中には、現代的な服を着たゾンビもいるし、1950年代からやってきたように見える服を着ているゾンビもいるべきだと思ったんです。実際に彼女はゾンビが色々な時代からやってきたように見える服を揃えてくれました。例えば、僕が一番好きな Iggy Pop と Sara Driver (サラ・ドライバー) 扮するコーヒーゾンビカップルに関しては、「彼らは1971年にブルーオイスターカルトのロック・コンサートを観に行ってその帰りにバイク事故で死んだんだ」と伝えました (笑)。それを元にして彼女はぴったりの服を見つけてきてくれた。Iggy Pop には、革のプラットフォームブーツを。Sara Driver が着ている服は、1968年か1969年に撮影された写真の中で Anita Pallenberg (アニタ・パレンバーグ) が着ていたものをほぼそのまま再現して、本当にその時代に見えるようにしてくれた。Catherine George ってそういう意味で本当に素晴らしいんですよね。
—劇中には、コーヒーゾンビや wi-fi ゾンビなどユーモアたっぷりのゾンビたちがたくさん登場しますが、もしあなたがこの世界でゾンビになったら何ゾンビになったと思いますか?
きっと僕は本屋さんの外で待っているようなゾンビになるんじゃないかと思います。またはレコード屋さんとか映画館とかね。きっとその3つのうちのどれかですね。
—全体を通じて、Sturgill Simpson (スタージル・シンプソン) による主題歌が効果的に使われています。かねてより大ファンだったとのことですが、彼との仕事はいかがでしたか。
そうそう、僕は Sturgill Simpson の大ファンで脚本の段階から彼がテーマ曲を書いてくれたらいいなあと思いながら書いたんです。僕が考えていたイメージは、60年代初期のカントリー・ソングで、なぜか忘れられていて、それが発掘されるというもの。彼に脚本を送って、僕のアイディアと昔の Patsy Cline (パッツィー・クライ) や George Jones (ジョージ・ジョーンズ) のような曲を例に出して曲のリズムについて少し話しました。その結果、彼はこの映画のために本当に美しい曲をクラシックなカントリーのスタイルで書いてくれたんです。彼には心から敬意を表したいのと、あんなに素晴らしいテーマ・ソングを書いてくれて感謝しきれない。彼は本当に最高のアーティストですね。
—『パターソン』の撮影前から、本作の構想を練られていたとのことですが、すでに次のプロジェクトも始まっていたりするのでしょうか。
今書いているものは2つあるんだけど、それについてはあまり話したくないんですよね。1本は、20年間も書きたいと思っていたもので、若者を主人公にしたロードムービー。もう1本は、オムニバスみたいな感じで、それぞれの物語に違うキャラクターが登場する。最近は書く時間がなかったんだけど、今こうしてみんなと同じように家にいるからとうとう完成させられるかもしれませんね (笑)。
—本作で描かれる得体の知れない恐怖というのは、昨今の世界とリンクしています。中でも、恐怖や混乱からくる欲求のあまり他人を顧みない人々の様子が世界中でみられますが、監督はどのようにご覧になっていますか?
今はこのウイルスが世界中で広まっていることで、僕らは全員一緒なんだということに気付いてくれたらいいなと思います。それから、僕らが今直面している本当の恐怖。例えば、地球温暖化という地球上の本当の脅威にも。ただ、今若い人達が始めた “Sunrise Movement” や “Extinction Rebellion” などもあるし、彼らはそういう危機をしっかりと認識しているように思います。なかでも、Greta Thunberg (グレタ・トゥーンベリ) は僕にとってのヒーローなんです。彼女は恐れていないし、彼女は何が起きているのかを認識している。もちろんそれは彼女が未来に起きることを恐れているからだけれど、でも彼女は科学がここでは一番重要であることを知っている。だから僕は、未来に対して希望を持っているんです。でも、そういう恐怖感のせいで、人々が利己的になっているというのは否めない。実際にいまだって、ネガティブなことがたくさん見えています。例えばアメリカではみんながトイレットペーパーを買いだめするというようなことが起きている。人と分かち合おうとはしていない。でも今回のことを通してそういう態度が変わればいいと思います。僕らはここで、全員がお互いを助け合わなくてはいけない、ということに気付かなくてはいけないのです。

© 2019 Image Eleven Productions Inc. All Rights Reserved.
—このような試練のなかでもユーモアや人間らしさを失わないために必要なことはなんだと思いますか?
とても難しい質問ですね。ただ僕なりに答えるとすると、こうやってみんながすごく落ち込んでいる状況の中にいると、地球上の命というのは、ユニバースという時間軸の中で見たらそれは指でパチっと鳴らしたくらいしかないすごく短い時間でしかない。そんな中で、今僕らはこの惑星で多くの美しいできごととまた多くの悲しいできごととともに、意識を持って一緒に生きている。だからこそ、お互いの存在やユーモアがあることに感謝し、芸術や、科学や、そして自然の真価を認められるというのは、いかに素晴らしいことなのかと気付かなくちゃいけないと思います。僕らがここにいるってだけでもどれだけ凄いことなのかというね。物事を客観的に見つめ、深呼吸して、この映画の中で、RZA (米ヒップホップグループ ウータンクランのリーダー、本作では配達員のディーン役で出演) が言うように「細かいことひとつひとつに真価を認めなくちゃいけない」と思う。それが僕からのアドバイスですね。
僕らそれぞれが授かった才能というのは、本当に短い間しかここに存在しない。だからそれを可能な限りみんなで守らなくちゃいけないと思うんです。その中でもジョークというのはすごく大切。もちろん、アーティストとか科学者とか、僕らのイマジネーションもそう。だけど、アートとか科学とか哲学などと同じくらい大事なのは、ジョークやユーモアだと思っています。人間として笑うってことはすごく大事だし、健康的なこと。だからこそ、ユーモアは僕にとってすごく大事なんです。