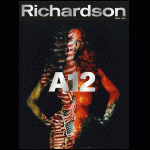「ニューヨークが魅力を失うことは絶対にない」ウディ・アレンが捉え続ける永遠のミューズ
Photo/Getty Images
Woody Allen
interview & text: mikiko ichitani
translation: akemi nakamura
『マンハッタン』(1979)『ブルージャスミン』(2013) など数々の名作を世に送り出してきた名匠 Woody Allen (ウディ・アレン) 監督の通算50作目となる最新作『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』が7月3日(金)より公開となる。
「ニューヨークが魅力を失うことは絶対にない」ウディ・アレンが捉え続ける永遠のミューズ
Film
ニューヨークのマンハッタンを舞台とした『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』は、Diane Keaton (ダイアン・キートン) とのタッグでセンセーションを巻き起こした『アニー・ホール』(1977) や『マンハッタン』といった1970年代の Woody Allen 作品を彷彿とさせるクラシックなラブストーリー。メインキャストには、Timothée Chalamet (ティモシー・シャラメ)、Elle Fanning (エル・ファニング)、Selena Gomez (セレーナ・ゴメス) を起用し、公開前から注目を集めていた本作。新世代のアメリカ映画の顔として今をときめく3名の競演というだけでも話題性は十分なわけだが、実際に観てみると真の主役はロケーションとなったニューヨークそのものなのではないかという思いがよぎる。
劇中では、メトロポリタン美術館やセントラル・パーク、カーライルホテルなどニューヨークの数々の名所が美しく切り取られ、重要なシーンではニューヨークを代表するアーティスト Frank Sinatra (フランク・シナトラ) が生んだ名曲「Everything Happens To Me」が主人公たちの想いを代弁する。近年は多彩なジャンルに挑んできた Woody Allen が、映画人生の終盤で描いたのは、男女の恋模様や運命のいたずら、切なくも過ぎていく人生など古き良きニューヨークで起こる “あの頃” の物語だったのだ。そんな往年の名作へのノスタルジーを刺激する本作について、 Woody Allen 自身はどのような感情を抱いているのか。また、これまでにも幾度となく彼の作品の舞台として描かれてきたニューヨークという街の魅力について監督自身に語ってもらった。
—本作ではメインキャストにジェネレーションYやZと称される新世代を代表する役者たちが起用されていますが、いま活躍する多くの若い俳優たちの中で彼らをキャスティングした経緯を教えてください。
まず Timothée Chalamet に関しては、キャスティング・ディレクターの Patricia DiCerto (パトリシア・ディセルト) の紹介でした。彼女がある時、「(舞台を観て) Timothée Chalamet という若い俳優が出ていたんだけど、素晴らしかった。ぜひ彼に会ったほうがいい。」と言ってきたんです。それで実際に会ってみたら本当に素晴らしかった。だから彼を今回起用することにしました。実際、一緒に仕事してみて彼のことを好きになりましたし、とても素晴らしい演技を見せてくれたと思っています。
Selena Gomez については、彼女がシンガーだということはもともと知っていましたが、演技もできるとは知りませんでした。あるとき、彼女の女優としての活動を知り、興味が湧いたのでニューヨークで実際に会ってみました。第一印象は、すごくチャーミングな女性だと思いましたね。台本を読んでもらう時に、「台詞には、素晴らしいものもあるし、笑えるものあるから、演じるのがすごく難しいよ」と伝えたんです。そしたら、彼女は「自分で出来る限り頑張ります」と言って、すごく説得力のある演技を見せてくれました。それで彼女を起用することに決めたんです。彼女はシンガーってだけじゃない、本当に優れた俳優だと思います。
それから Elle Fanning は、本当に優れた俳優で、僕にとっては若き Diane Keaton (ダイアン・キートン) を彷彿とさせるんです。彼女を見た時、僕が初めて Diane Keaton を見た時を思い出したくらい。それって最高ですよね。彼女は、これから先も素晴らしいキャリアを築いていくと思うし、映画界にとってすごく重要な存在であり続けると思います。もちろん、この映画のなかでもとても輝いています。
—現代の若者たちを主役に据えながら、舞台に選ばれる施設や引用される作品名や人物、ファッションや音楽にいたるまで70年代の古き良きニューヨークを彷彿とさせます。このような演出は最初から意識されたのですか。
とくに意識はしていません。僕自身、ニューヨークで生まれ育ったので、街のことは知り尽くしているというのもあるし、この仕事も随分と長いことやってきたので、ある程度の技術的な面での熟練は備わっていると思います。良い映画をつくるのに必要なのは、運ですね。良い運がなくちゃいけない。天気に恵まれないといけないし、俳優達が自分の願っているような演技をしてくれないといけないし…。僕にできるのは、まず良い脚本を書くこと。そこから実際に外に出て行って撮影を開始したら、良いものになるように最大限の努力をする。基本的には映画作りというのは、10%経験と、90%の運なんです。
—本作はあなたの歴代の作品のなかでも、批評家やファンたちの間で『アニー・ホール』と比較されることが多いようですが、そのことについてどのように感じますか?
自分が両方の作品の近くにいすぎてよく分からないですね。僕はいつも、ひとつの作品をつくっては次の作品にいくというやり方をしてきました。過去の作品を振り返ったりはあまりしないんです。実際にこの作品ももう何年も前につくり終えていて、その後に、『Rifkin’s Festival』(原題・2020) をつくり終えて、次の新しい脚本も書き終えています。だから、この作品も実はもう僕の中では随分昔の作品のような感覚なんです。細かいディテールとか忘れてしまったところもあるし。『アニー・ホール』にいたってはもう何も覚えてないくらいです。『アニー・ホール』は、少なくとも30年は見ていないですしね。いや、70年代に作られたから、もう50年は見ていないかもしれません。

Photography by Jessica Miglio ©︎2019 Gravier Productions, Inc.
—あなたがこれまで制作した映画は、いつ見ても新鮮さを損なわないものばかりです。映画を作る際、人物像の作り方や映像表現を含め、未来を見据えた工夫などはありますか。
それはきっと、僕がその時々に意味のある社会的な問題を映画のテーマにしてこなかったからだと思います。人によっては、目の前にある問題やニュースのヘッドラインになっているようなこととかを映画の題材にすることで、大成功することもあるでしょう。例えば、今ならコロナウイルスに関する映画を作るとか、中近東の問題や中絶に関する問題など世界中の人達がいま問題としていることをテーマにしたりとか。けれど、僕はこれまでにそういう映画を作ったことがないんです。
時代遅れになるかならないかというのは、結局のところそれが良い映画か酷い映画かということだと思います。僕の場合は描いてきた題材のおかげというのもあるかな。『アニー・ホール』や『マンハッタン』で描かれているような問題は、きっとこれから10年先も同じだと思うんです。だから、出来の良い作品だったら永遠に見てもらえると思う。そこで描かれている問題が普遍的だから。逆に、悪い映画だったら、なるようにしかならないです。それは良い映画を作らなかった場合の現実だということで受け入れるしかないと思います。

Photography by Jessica Miglio ©︎2019 Gravier Productions, Inc.
—監督を語る上で欠かすことのできない街、ニューヨーク。これまで多くの困難に直面しながらもニューヨークが魅力的な都市であり続ける理由はどこにあるのでしょうか。今回のパンデミックや収束後の未来について考えることはありますか。
正直、パンデミックの後にニューヨークがどうなるのかは検討もつかないですね。もちろん、僕が願っているのは、ワクチンを見つけて、このパンデミックが何かしらの形で収束してくれること。このパンデミックが完全に消滅することになってくれればいいと本気で願っています。ニューヨーカーは、アメリカのなかでもとくに最悪な状況下で、みんな頑張ってきました。ピークだった数ヶ月前と比べても良い結果を出しているし、それだけでも素晴らしいことだと思います。今年か、来年か分からないけれど、絶対にワクチンも見つかるはず。そうなれば、レストランやお店も開くだろうし、劇場も再開して、これまでと同じニューヨークを取り戻してくれると期待しています。これまでも数々の困難に直面しながら、ここぞというときに立ち直れるとこのがニューヨークの偉大なところですから。でも、今回の経験で学んだことから、生き方が変わるようなこともあるかもしれないですね。例えば、会社に行かなくても、家で働くことが可能だと分かった人達がいるかもしれない。だからといって、突然全員が家で仕事して、会社や店に誰も行かなくなるってことはないと思いますけどね。ラジカルに変わらないものもあると思うし、それは不可能だと思う。

Photography by Jessica Miglio ©︎2019 Gravier Productions, Inc.
ニューヨークは、こういった困難に直面しながらも、常に発展してきた場所です。例えば、僕が子供の頃は誰も自転車で通勤なんてしていなかった。でも今は地球環境のためにも、また地下鉄での感染を避けるためにも、より多くの人達が自転車を使うようになり、街もそれに対応するために道路などの環境を迅速に変化しました。そうやって街というのは変わっていくものですから。今回のパンデミックという大変な経験を通じて、街をどのようにより良くできるのか、学んだり考えたりするきっかけになればいいと思います。
でも、5年後にニューヨークを見てみたら、見た目的にはパンデミック前と大きくは変わっていないかもしれません。もちろん、年月の経過による自然の変化というのはあるだろうけど、ラジカルに変わることはないと思う。劇場やスポーツアリーナもこれまで通りの活気を取り戻すだろうし、レストランも活気を取り戻して、みんなディナーに外食に行くようになると思いますしね。中には、もうニューヨークには住みたくない。田舎に引っ越したいっていう人たちも出て来るでしょう。でもニューヨークというのは必ずまた新たな人達が、「ニューヨークに住みたい!」と思って集まってくる場所なんです。だからどんな状況であっても、未来のニューヨークが、ニューヨークらしくなくなってしまい、魅力を失うなんてことは絶対にないと思います。
—監督ご自身、生活の変化やクリエイティブについて考えることはなにかありましたか。
基本的にはこれまで通りの生活をするように心がけています。でも、仕事して疲れた1日の終わりに友達と会ったり、レストランでディナーを食べたりとか、緊迫から開放されるような瞬間がないのがすごく恋しいですよね。僕にとってこのコロナ禍というのは、クリエイティブな面において、まったくインスピレーションが湧くものではなかったです。もともと僕はそのとき世界で起きていることに影響されたような映画を作るのは好きじゃないので。もちろん人間としてはそういうことに興味や関心があるけれど、それを題材にして作品を書きたいとはまったく思わないです。だからこの状況というのは、まったくインスピレーションが湧くものではなくて、単にニュースってだけ。それに、新たな発見というほどのものも特にないですし。とはいえ、僕はニューヨークの自宅で過ごせているので、本当に最悪の状況の中で生きているというわけでもないのかな。でも、さっきもいったように日中にふと仕事を休憩して、気軽に散歩に出かけるみたいなことができなくなったことはすごく悲しいです。舞台を観に行ったりもできないですし。それから一番大きいのは、スポーツが見れないことですね。バスケットボールはないし、野球もない。そういう意味でいったら、やっぱり僕にとっていまの生活は大悲劇です。