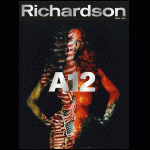綺麗な写真の手前にある綺麗な眼差し。フォトグラファー Piczo
piczo
photography: Asuka Ito
interview & text: Takuhito Kawashima
「Piczoさんは美しいものを美しく撮る」 と Mame Kurogouchi のデザイナー黒河内真衣子は言う。そんな当たり前のこと? と思うかもしれない。しかし実はそれが難しい。しかし彼はそれを撮ってしまう。もちろんコンポジション、光の取り入れ方、被写体との距離感などの技術的な部分もあるだろうが、“美しい写真” の大部分が依るのは、Piczoという人物の人柄である。“かっこいい” とは違う。どこか暖かさがあり、ユーモアやどこか遊び心も感じる写真。ロンドンを拠点に活動し、『i-D』『New York Times』 をはじめとするワールドワイドな雑誌から 『Beauty Paper』 などの新進気鋭の雑誌やアートディレクターからのラブコールが絶えない Piczo。彼の眼差しに迫る。
綺麗な写真の手前にある綺麗な眼差し。フォトグラファー Piczo
Photography
── “ピクさん” や “ピッくん” といった愛称で呼ばれていますが、そもそも “Piczo”(ピクゾー)の由来を教えてください。
あんまり大きな声で言えることじゃないんだけど、中学の時に気絶させる遊びのようなものが流行ったことがあってね。それで自分も気絶してしまって…… その時に頭から地面に落ちて、痙攣してピクピクしながら口から泡吹いていたらしい。それで、次の日から “ピクゾー” っていうあだ名になっていた(笑)。
── それを自分の活動名にしてしまうのがなんとも Piczo さんらしいですね。もともと美大ではグラフィックを専攻していたのにも関わらず、カメラを手にしたのはなぜですか?
当時付き合っていた油絵専攻の子が、趣味で写真をやっていたから。その子に影響されて自分も……。「パソコンよりもカメラがしっくりきた」 と、かっこよく言い切りたいところなんだけど、当時の日本デザイン業界って、寝ないのが当たり前みたいな世界で。つらそうだなぁ〜と思ったし、それにすごい才能溢れる人が周りにいっぱいいた。長嶋りかこも同世代だったり……。なんかもっと自分にしかできないことないかなと探していたところにカメラが現れて。そんな感じなんです。カメラを持って、バンド活動している大学の友達のライブに行って写真を撮ったりしていたね。

『nikki』 より
── 今年 aptp books から刊行された 『nikki』、その名の通り日記のように撮影した写真を集められています。Piczo さんがカメラを持ったばかりの頃に撮影していたものと同じコンセプトなわけですね。
そうかもしれない。同じものを撮り続けるのもそんなに苦ではないし、それどころか楽しんでいる自分もいる。モデルや役者として活動する miu ちゃんも、20歳ぐらいの時からもう 5〜6年、帰国するたびに撮り続けているし。彼女の成長過程を記録できるのもカメラを持っているからこそできるある種の特権なのかなと思う。
── 藤代冥砂さんの言葉で 「時間を止めたくて写真を撮るわけではない。むしろその逆だ」 とあります。まさにその感覚でしょうか。今はアートとしての写真も増えている中で、『nikki』 に載っているような写真は、写真を撮る行為の本質的な部分な気がします。
自分の中では、写真はアートと記録の間にあるものだと思っていて。アートは、特にコンテンポラリーアートの場合は、観るのに知識が必要。こういう文脈があるからこそ、この作品が面白い、とかね。当然写真にもそういった文脈はあるんだけど、自分はアーティストでもないから、知識がなくても 「なんかいいな」 と思える写真を撮る。自分にとってその感情を引き起こすことができるのは、鑑賞者の琴線に触れるようなリアリティがあることなのかなって思う。被写体とかの距離感だったり、インティメイトな写真であったり。特別な瞬間の写真だったり。

『nikki』 より
── 『nikki』 とファッションブランドのコマーシャルワークとで Piczo さん的に違うところってどんなところですか?
仕事だとどうしても “はめる” という行為になってしまう。水平は取れているか、構図は整っているか、洋服はちゃんと見えているか、とか考えれば考えるほど、はめにかかってしまっている気がする。パッと見た感じは綺麗に見えるんだけど、どこか綺麗すぎてしまうと平凡な写真になって……。本来、歳をとれば視点が広がるはずなのに、仕事をすればするほど、どんどん視点が狭くなっていく感覚が怖かった。『nikki』 に載せているほとんどが、何にも考えずにただある意味、自分ではコントロールできないモーメント(瞬間)を本能的にシャッターを押してできた写真ばかりで。当然クライアントがいるわけでもないし、誰かに見せようと思って撮影しているわけでもないから。
── 普段 『nikki』 のような写真を撮ることで、ある種バランスをとっているのかもしれませんね。
この写真たちはアート作品でも当然ないし、ポートフォリオに入れるような写真でもなくて。見方によっては、“無意味” なものと言えるかもしれない。だけどもそれが自分にとってものすごく大切なことだった。「何のために写真撮ってんだっけ?」 ってことを忘れないようにするための行為に近いんだと思う。
── 一体 Piczo さん何のために写真を?
写真でコミュニケーション取れるのが楽しいからだと思う。撮ってる時もそうだし、撮った後も。撮る時はその時のアクションとリアクション。撮った後も、現像した写真を見てもらった時の反応だったりがやっぱり写真を撮っていていいなと思うことかな。
── そんな Piczo さんの眼差しというか人間性が、コマーシャルの写真や、特に 『nikki』 には顕著に現れているように感じます。写真集の制作にあたって注力したポイントはどこにありますか?
さっき話したような感じで撮影しているので、写真一枚一枚にこれのここを見て欲しいというようなものは正直ない。でも今回写真集という一冊にまとめる時には男の子も女の子も、高い服を着ていても、母親のおさがりの服を着ていても、または裸でもみんな同じだよというような、みんながみんなをフラットに見て欲しいとは思いながら制作した。

Mame Kurogouchi Fall Winter 2020
── その写真の楽しさを、Piczo さんの場合はコマーシャルの作品からも感じとれるのは、やはりモデルさんとのコミュニケーションがあるからでしょうか。以前現場でご一緒したとき、モデルさんたちが準備OKでも、なかなかシャッターを切らずに、モデルさんたちと一緒に座りながら話しをしているのが印象的でした。
撮影のコンセプトにもよるけど、その時は作り込んだ写真ではなく、できるだけ自然体に近い彼女たちの様子を撮影したかった。ただのフォトグラファーとモデルという関係性を少しでも曖昧にしたいと思っていたのかもしれない。
── それにものすごく粘っていましたしね。「Piczoさん撮れてると思います!」 と言われてからも10分ほどカメラを離さなかった。
そうだった? でも確かに 『nikki』 の話ではないけど、やっぱり自分ではコントロールできないハプニング的なものをコマーシャルの撮影でも求めてしまっているのかもしれない。リアリティ探しの旅に。ファッション撮影で楽しいのは、こういうイメージを作りたいと思うビジョンと、それをリアリティがあるように見せるモーメントがクリエイションとして存在しているところなのかもしれないね。

UNPOLISHED MAGAZINE
── Piczoさんがロンドンで語学学校に通っていた頃、モデル事務所に頼まれて新人モデルたちのコンポジットを撮影していた、まさにあのシリーズの雰囲気ですね。ご自身のベッドルームを撮影場所に使っていたという。
「テストする?」 みたいな感じで事務所から声かけられて、バジェットもないので、とりあえず自宅に来てもらって部屋で撮るぐらいしかできなくて。あとは家の周辺で撮影するっていうのをほぼ毎日繰り返していました。
── そこから「これ誰が撮ったんだ?」 みたいな注目が集まって、Piczo さんのキャリアは本格スタートするわけですね。
なのかな? そのあたりがどのような仕組みなのかは自分には分からないんだけど。

Gap Fall 2020
── ロンドンというクリエイティブにおける世界トップクラスの競争社会で、Piczo さんならではの表現方法を見つけ、周りに流されずにスタイルとしていることがすごいと、同じロンドンで活躍されているスタイルストの Ai Kamoshita さんもおしゃっていました。それに現在では We Folk という世界のアートディレクターが注視するアーティストエージェンシーに所属していますよね。作家としてではなくコマーシャルフォトグラファーとして、日本人で所属している人はごくわずかです。フォトグラファーとしての自信はつきましたか?
どうだろう。劣等感の方が勝ってるというのが正直なところ。みんなそれぞれカルチャー的な背景がしっかりあって、それが色彩感覚として影響されていたり。さらにその感覚に今住んでいるヨーロッパのクリーンさがミックスされて、ものすごく新鮮な写真になっていたり……。変人たちにいつも圧倒されています。なんせ、こっちは大阪生まれ。教師の倅ですからね。

Piczo。大阪の自宅にて
── その家庭環境こそに Piczo さんのコミュケーションの高さの理由があるのかもしれません。
確かに。自分がロンドンに行きたいと言った時もサポートしてくれたし。学ぶことに対してはサブジェクト問わずサポートしてくれる家庭だった。あとはとにかく明るい親だったこともあってか、自分も卑屈に考えることなく、素直でい続けられている気がする。英語が喋れないからとか、アジア人だから…… みたいなことに対してネガティブに考えすぎない。友達が 「会ってみなよ」 と言うなら、とりあえず会ってみるとかは、自分の生まれ育った環境が少なからず影響しているのかもしれない。
── 人に対しても素直ですが、カメラに対しても素直ですよね。いつもカメラを持ち歩いているイメージがあります。一度誰かが 「ロンドンのカメラ小僧」 と Piczo さんのことを話していたことを思い出しました。
カメラは持ってると発見があるからね。カメラを持っていないと見逃してしまうことって本当にいっぱいある。人に会う時も、カメラを持っていると持っていないとでは自分の中に残る記憶や印象も全然違う。カメラを持ちながら、「何かあるかもしれない」 って気持ちでいるのはなかなか刺激的ですよ。