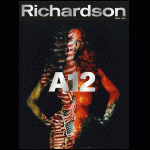石それぞれが持つ魅力を引き出し輝かせる。マリーエレーヌ・ドゥ・タイヤックの手腕
Marie-Hélène de Taillac
photography: ryutaro izaki
interview & text: aika kawada
保守的なジュエリー業界で、あえてキャンディーのような色石を使う。Marie-Hélène de Taillac (マリーエレーヌ ドゥ タイヤック) のユニークさは、カラーバリエーションの豊富さにある。また、長きにわたるジュエリーは男性が女性に贈るものという固定概念を超えて、“女性が本当に楽しんで身につけられるジュエリー”を世に提案して来た。他のジュエラーと一線を画す遊び心たっぷりの名品たちは、世の女性たちの心を射抜き、憧れとなって社会進出を鼓舞して来たと言えるだろう。
もうひとつ、Marie-Hélène de Taillac ならではのこだわりがある。それは、ゴールドの美しさ。一般的に純金は柔らかく傷ついたり変形したりしやすいことから、多くのジュエリーは、銀や銅を含めた合金に加工した18K以下が使われている。しかし Marie-Hélène de Taillac は、より金の含有量が高い22Kに美しさを見出し、一貫して提案し続けている。
そんな確かな審美眼と美しいものへの飽くなき探究心、エレガンスとユーモア、自立した女性像は、幼い時期を過ごした北アフリカや中東、ファッションについて学んだロンドン、そして生活拠点であるパリで培われたものに違いない。デザイナー本人に、これまでの歩みとクリエーションに対する想いを訊いた。
石それぞれが持つ魅力を引き出し輝かせる。マリーエレーヌ・ドゥ・タイヤックの手腕
Portraits
—現在のご自身を形づくった、子供のときの思い出を教えてください。
政府関係者で石油業界で働く父の仕事の都合で、様々な国に住んで育ちました。リビア生まれで、ベイルートで11歳まで育ちましたが、12歳からパリに住み、17歳でロンドンに引っ越しました。北アフリカでは、とても古いジュエリーを見る機会もあり、知らず知らずにユニークな経験をしていたのだと思います。ベイルートには、母がルビーやサファイヤをオーダーしている宝石屋さんがあって、隣で見ているうちに石に興味を持つようになりました。両親がイランに住んでいた時期には、まさに宝と言えるような宝石を持ち帰ってきたことも。当時はジュエリーデザイナーになるとは思っていませんでしたが、天然石や宝石について学んだ時期もあり、幼いころから常にジュエリーに魅せられていました。いまはパリに家がり、休日はフランス南西部のガスコーニュにある家族で所有する城で過ごしています。
—ジュエリーデザイナーになったきっかけは?
ロンドンではジュエリーやファッションの仕事をし、そのひとつが帽子で知られる PHILIP TREACY (フィリップトレイシー) の元でした。当時のファッション業界はとても忙しく働きづくめで、もっと楽しく仕事ができたらと思っていました。仕事を辞めてアジアを旅する中で訪れたインドのジャイプールで、「ジェムパレス」という宝石の加工などをできる老舗ジュエラーで見た色石、カッティングなどの技術に非常に感銘を受けたのです。そこで元パートナーだった男性に出会い、小さなコレクションを作ったのがブランドの始まりです。1996年に作った初期のデザインは、今も存在していますし、翌年の2つ目のコレクションで登場した「”カボション”リング」はブランドのシグネチャーアイテムでもあります。現在は、パリの装飾美術館のパーマネントコレクションとして所蔵してあるんですよ。
—ダイヤモンドやサファイアではなく、色石を使ったクリエーションはジュエリー界の常識を覆しました。色石にこだわった理由は何だったのでしょうか。
当時は Jil Sander (ジルサンダー) の人気もあり、パリでもミニマルなファッションが人気でした。対してジュエリーはまだクラシックなデザインが多くて、日常的に身につけられるものがありませんでした。以前から色石や天然石を好んでいましたが、当時ジュエリーで使われることは稀でした。強いて言えば、Marina Bulgari (マリナ・ブルガリ) や Andrew Grima (アンドリュー・グリマ) くらいでしょうか。ほとんどが、色のない冠婚葬祭に使うようなジュエリーが売られていました。
—石のカッティングは、伝統に則ったスタイルで行なわれていると伺っていますが、具体的にどのような方法ですか。
石は一つ一つ異なるので、カッティングを個々に変えることで一番ふさわしい形にしています。それから、ブリオレットというダイヤモンドに施すカッティングがあるのですが、初めて他のプレシャスストーンやセミプレシャスストーンに取り入れました。インドでないとできない大変高度な技術です。石は山の中に眠っているものを採掘しますが、もともとは全く光っていません。なので、いかに石を磨きカッティングして活かしてあげるかで価値が決まります。人工的なものではなく、天然の産物である石に命を吹き込む作業に情熱を注いでいます。

—22Kへのこだわりと、あなたが考えるゴールドの美について教えてください。
ゴールドが本来持っている色と風合いが好きなので、本当は純金である24Kを使いたいのは山々なんです。しかし、あまりにも柔らかく繊細な素材なのでジュエリーには適しません。最も近しい美しさを保ってるのが22Kなんです。世の中にはリペアのしやすさや機械で大量生産しやすいことから18K以下のジュエリーが数多く販売されています。22Kは手作りでないと加工できないので、効率的ではありませんが、そこに変えがたい美しさがあると思っています。また、22Kはほどよい柔らかさがあるので、糸状にして編み込むことができ、細やかな手作業に適しています。シルバーゴールドなどは化合物を加えて色を調整する必要がありますが、ありのままのイエローゴールドの色味と天然石とのピュアな組み合わせに、美の可能性と価値を置いています。
—豊富な色とモチーフ使い、さらに、HPや店頭のトロンプユイルを使ったプレゼンテーションまで。わくわくするようなブランドイメージには、何かメッセージが込められているのでしょうか。
幼い頃から色に敏感で、楽しいものが大好きでした。ジュエリーだからといって、感性のスイッチを切り替えてクリエーションするわけではありません。私が生まれた60年代は美しい色とパッションに溢れた時代だったと思います。Jacques Demy (ジャック・ドゥミ) 監督作品など、当時の映画からも見て取れますよね。強いシルエットが流行した80年代や黒が好まれた90年代とも異なります。生まれた時代のムードは色濃く、クリエーションに反映されていると思います。それに温暖な国で育ったからか、パリジェンヌらしいとは言えないかもしれないですね(笑)。歴史的にも色は常に貴重なもので豊かさの象徴であり、位が高い身分の人が楽しむ風習でもありました。CHANEL (シャネル) の黒が取り上げられがちですが、フランスも服飾史を遡ると、実はあまり黒を着ない国。高田賢三さんはとても色を好む方でしたが、その後80年代に一世を風靡した川久保玲さん、山本耀司さんによって黒が好まれるようになったのです。私の姉の Sophie (ソフィー) が COMME des GARÇONS (コムデギャルソン) に勤めていたときは、影響されて黒を着るようになったのですが、祖母に「私たちのメンタリティーの色ではない、黒をなぜ着るの?」と言われたことがありました。黒は元々は喪に服す色ですからね。
—雲、猫、魚、花、ミツバチ……。かわいらしいモチーフを取り入れるのはなぜですか。
1900年代の歴史を見みると、宝石は購入する人の価値観によって大きく左右されるものでした。80年代は石油業界のアラブの方々が数多く手に入れ、彼らはいかに石に価値をもたらせるかを重視していました。なので、ジュエラーたちも、権威がある高級品としてシリアスなデザインのものを作っていました。1920年代に入ると戦争があったからか、遊び心のあるモチーフが増えるんです。ジュエリーは必需品ではないからこそ、人生に喜びを与え楽しむもの。そういった楽しいジュエリーを作りたいという気持ちから、可愛らしいモチーフを取り入れています。それも、皆さんのお守り代わりになるような。北アフリカや中東で育ちヨーロッパで暮らす身からすると、現在各地で起こっている戦争に心が塞がってしまうんです。ニューヨークを拠点にスナップ写真を撮り続けた写真家、Bill Cunningham (ビル・カニンガム) の「ファッションというのは、現実をサバイバルするための鎧である」という言葉はまさにそうで、夢を見させるジュエリーがこの世には必要だと常々思っています。顧客の皆さんも、何か楽しいもの、毎日身につける喜びがあるものを求めてお店に来てくださっています。その昔、ジュエリーは男性が女性に購入するもので、高価なものは財力と権力の象徴でした。隣にいる女性はデコレーションの一部。社会構造を押し付けられていたのです。60年生まれの私は、女性が自分の楽しみのために自分でジュエリーを買い始めた最初の世代だと自負しているんですよ。
—ジュエリー界からの反発はあったのでは?唯一無二でありながら、国際的に成功できた理由を教えてください。
いいえ。パリでオープンしたばかりの Colette (コレット) で展開でき、女性たちが早々にポジティブなリアクションをしてくれました。その後、アメリカや日本の女性たちも、面白がっていい反応をしてくれたのです。いわゆるジュエリーの販売方法をとらなかったことが功を奏したのだと思います。嬉しかったのは、女性たちから「これまでジュエリーや宝石に興味がなかったけど、あなたのジュエリーは身に着けたい」という声が非常に多く聞けたこと。既存のジュエリーファンよりも、新しいファンとの出会いがあり想像よりも早くブランドの認知が広がっていきました。
—パリにショールームとオフィス、インドのジャイプールとボンベイにデザインから加工まで行う工房を設立されています。インドは大きな変化を迎えているのでは?
インドを初めて訪れたのは89年のこと。信じられないような大きな大きな変化が起きています。IT分野など、インド人の新しい世代の価値観にも驚かされています。そんな経済的な発展の中でも、まだ街には風情のある古い作りの家屋などが見られますが。
—伝統的な宝飾品の作り手の技術は守られているのでしょうか。
心配事のひとつです。インドは家内制手工業が強く、家業は代々男性が継ぐものでした。現在は情報社会の発達と経済状況が良くなったことで、たくさんの職業の選択肢が増え、父親が技術師であっても息子が継ぐとは限らないのです。職人技術の貴重さや継承の大切さについて、まだ議論されていないのが現状だと思います。もし引き継がれたとしても、同等のクオリティを保てるのかを懸念しています。現実的に伝統技術や職人を守るには、賃金と働く環境の改善が必要です。どこの国も抱えている問題は同じですね。
—末っ子の Victoire (ヴィクトワール) さんは、Officine Universelle Buly (オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー) で成功されています。4姉妹でいらっしゃいますが、いつもどのようなことを話しするのでしょうか。
Victoire は以前から美容について興味を持っていましたね。彼女が Colette でPR業務をする前は、私のブランドのPRをしてくれていました。以前は4姉妹、全員が私の仕事に関わりを持ってくれていたんですよ。家族で集まると、ビジネスの話ばかりするわけではありません。でも、お互い違うテイストを持ち、分野が異なっていても相談に乗ることはあります。姉妹なのでたくさん話し合わなくとも、各々の美的感覚を理解しているのがいいところ。結婚式みたいな家族イベントがあっても、不思議と適材適所で動ける強みもありますね(笑)。阿吽の呼吸というか、何を目指していて、どれくらいの基準をパーフェクトとするのか。そういった感覚までよくわかっているんです。最近は、姪っ子たちも仕事を手伝ってくれているので、次の世代とのやりとりも刺激的で楽しいです。
—ジュエリーをつける心得を教えてください。
こう付けるべきというルールに縛られて、臆病にならないこと。ジュエリーはつけないといけないものではありません。もっと純粋に心の声に従って直感的に楽しんだがうまくいくはずです。もちろん、現実的に購入できるできない価格的なハードルはあると思います。また、ジュエリーは、自分の大切な人や次世代に譲れる、長期にわたって愛され存在するという面白さもありますよね。商品的な価値だけではなく、自分らしいもの、想いを寄せられるものを選んでいただきたいです。
—今後やってみたいことがあれば教えてください。
若い世代をサポートしていきたいです。これまでも、若い人たちがビジネスに関わってくれ、彼らが何年か後に独立し、自らのビジネスを成功させていく姿を幾度も目にしてきました。若い方々にお伝えしたいのは、希望を持ち、夢を見ることを忘れないで欲しいということ。自分の気持ちに従って行動することで、夢で終わらず現実で形になることがあります。難しい時代ですが、恐れずに、好きという気持ちや、やってみたいという意欲を大切にしてください。
—最後に、一番好きな石は何ですか?
一番難しい質問ですね。強いて言えば、スピネルとトルマリン。サファイアも好きです。色のニュアンスが好きなんです。スピネルは、ルビーと同じくらい希少な石で、赤に近いピンクがとても魅力的。色で遊ぶのが楽しい石なんです。