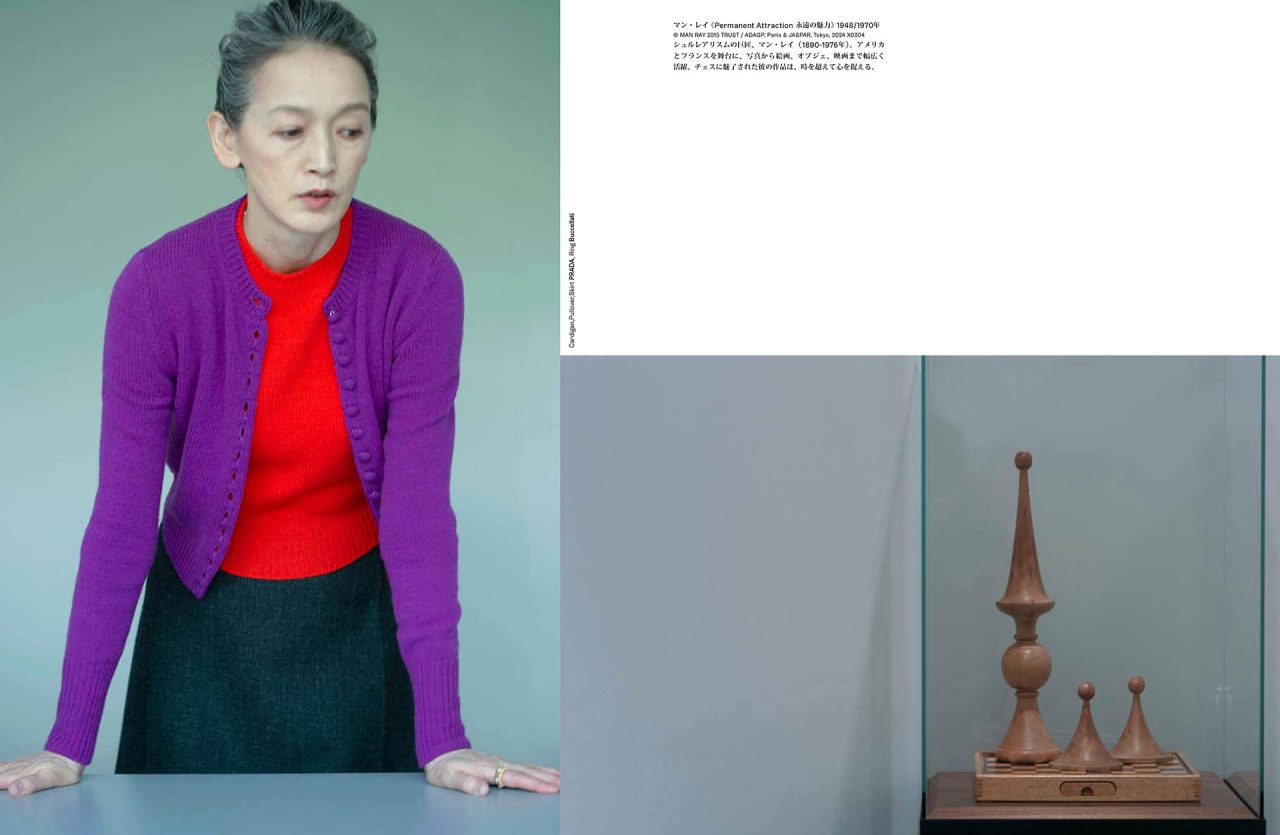クラリス・ドゥモリが生み出す、洗練された、シンプルでエコロジカルな美学
clarisse demory
photography: riku ikeya
interview & text: tomoko ogawa
パリを拠点に世界のファッションやカルチャーシーンで活動する、Clarisse Demory (クラリス・ドゥモリ)。過度でなく、シンプルだけれど、洗練された、静謐な美しさを放つ確固たるスタイルで、The Row (ザ・ロウ)、LEMAIRE (ルメール)、Sophie Buhai (ソフィー ブハイ)、RIER (リア) などのクリエイティブ・コンサルティングを行う彼女。今回、完全日英バイリンガル版として、「アートブック」スタイルの新誌面へと生まれ変わった、資生堂の企業文化誌『花椿』(No.832/2024年11月28日発行号)で、クリエイティブ・ディレクションを手がけた Clarisse Demory が、これまでのキャリアや彼女の仕事のスタイル、そして、『花椿』のクリエイティブ・ディレクターとしての経験について語ってくれた。
クラリス・ドゥモリが生み出す、洗練された、シンプルでエコロジカルな美学
Design
—あなたの Instagram のプロフィールには、「テイラーメイドのクリエイティブ・ディレクションと戦略」「キュレーションとスタイリング」と書かれていますが、あなたのキャリアパスは謎に包まれています。どんなふうに現在に至ったのかをお伺いしてもいいですか?
私は専門的な勉強はしていず、独学でここまで辿り着きました。ロンドンに1年間留学をしましたが、親の援助がなかったので半年後には働かなければならなくて。応用芸術を学ぶには、材料費もかさむし、海外で生活すること自体がハードなことでしたから、仕事を始めた方が好都合だったんです。その後、パリに戻って別の2年間の学校に申し込み、1年間通いましたが、同時に働きもしました。そこから10年間、30歳まではどんな仕事でも引き受けてきました。ちょっとおもしろい話なんですが、私はもともとカフェ&レストランを経営していたんです。
—そうだったんですね。それは初耳です。
あるとき、パリ東部のベルヴィル地区を歩いていたときに、通りすがりに廃墟と化したレストランを見つけて、大きな可能性を感じたんです。私は、ポテンシャルを感じるものが好きなんですね。その場所に正当な何かを施したくなって、中にいる人に写真を撮っていいかを聞こうと思ったんです。そうしたら、その女性が元オーナーで、もう運営はしていないと知りました。そこはゲットーのど真ん中というあまり治安がよくない地域で、彼女もそれが原因で店を閉めたようでした。でも世間知らずだった私は、いいところだと思ったんです。ベルヴィルにはアジア系の小さなレストランがたくさん並んでいるけれど、この界隈でおいしいレフレンチスタイルの料理を食べたい人はたくさんいるはずだと感じ、彼女にそう伝えました。そうしたら、彼女が私を説得し始めたんです。「あなたなら、レストランができる」ってね。実際、仕事もなかったので、やるべきだと思って。すでに頭の中でアイディアがたくさん芽生え始めていましたし。ただレストランを経営したことがなかったので、どうしたらいいかわからず、全部を自分で用意しました。カフェにはオーツミルクもライスミルクもあって、アルコールは全て自然派、でもコカ・コーラもあるような、とても変わった組み合わせのメニューだったと思います。
—ちなみにレストランの名前は?
以前存在していた2つの名前をそのまま合体させて、「L’Oiseau Blanc – La Capucine」としました。ベルヴィルは今となってはヒップスターの場所みたいになってしまいましたが、Maison Martin Margiela (メゾン マルタン マルジェラ) のアトリエにも近く、そのエリアを拠点とするジャーナリスト、ギャラリスト、建築家、アート・ディレクターたちがレストランに集まっていました。彼らが私にポジティブなフィードバックをくれて、クリエイティブな分野で働くことを勧めてくれたんです。そうして彼らの多くはよき友人となりました! メニューはグラフィックデザイン的でもあるし、内装やプレイリストを手がけることが、アート・ディレクションだったんですよね。でも、当時は人々のコミュニティやスタイルを作り、コミュニケーションを図ることをディレクションと呼ぶなんて知らなかったし、私の進む方向だとは思ってもいませんでした。そうして2年後、ファッションブランドだけでなく、レストランやホテルなどでも横断的に仕事をするようになりました。レストランを閉店したのは、32歳のときで、ホスピタリティ産業からファッションとコスメティックに方向転換しました。レストランはたくさんの規制があり、隅々まで堅実で安全でなくてはいけないので、そのときの私はファッションやコスメティックの方が刺激的に感じたんですよね。

—クリエイティブ・ディレクターとしての仕事はすぐ軌道に乗りましたか?
もちろん、すぐにうまくいったわけではありませんでした。クライアントのためにプレイリストを用意したり、ソーシャルメディア用のブランドコンテンツやショップウィンドウを作ったり、どんなチャンスも逃しませんでした。でも、まだ私はクリエイティブ・ディレクターではなかったですし、肩書きとして名乗る勇気はありませんでした。そして、ちょうど38歳になったとき、正式に自分をクリエイティブ・ディレクターと呼ぶようになりました。
—準備が整ったということでしょうか?
そうですね。プロジェクトの指揮者として、各企業とコミュニケーションを取れるようにもなりましたし。また、プロのカメラマンになったことはありませんが、自分で写真も撮っていたので、ある時期から、ジャーナリストが私の撮った写真を気に入って、出版もされたんです。写真、グラフィック、スタイリングでプロフェッショナルな一定のレベルに達することができたと感じました。と同時に、私はレストランを経営するビジネスマンでもあったので、芸術的な面だけでなく、商業的な目標を持つクライアントのニーズも理解することができたんです。それゆえ、私のミッションは、コンサルティング戦略からブランドイメージの開発、コミュニケーションまで、かなり広範囲に及ぶこともあります。例えば、仕事の内容のメニューがあったとしたら、全メニューを提供することもできるし、アラカルトで提供することもできるというか。
—The Row や LEMAIRE、Sophie Buhai のような著名なブランドから、RIER のように新進気鋭のブランドのクリエイティブ・コンサルティングを担当されていたり、広告撮影のスタイリングを手がけていたり、一つのスタイルはありながらも、世界のクリエイティブなフィールドで活動をされていますが、なぜそのような仕事の仕方になったのでしょうか。
私のキャリアが、デジタルカメラ、ブログ、ソーシャルメディアに囲まれたデジタル時代にスタートしたことが大きいと思います。当時は知識もなかったですし、周りにクリエイティブな人たちのコミュニティもなければ、知り合いもいませんでしたが、インターネットが突然、世界に触れるきっかけを与えてくれました。そして、写真やビジュアルを通してオンラインで仲間と知り合うことができた。SNSは人脈を広げるのにかなり役立ちました。たまに打ちのめされることもありますが、ポジティブな側面もたくさんあると考えています。
—あなたがコラボレーションするブランドや仕事を選ぶときの基準、決め手はあるのでしょうか?
これまで私が決めたことは一度もありません(笑)。積極的なタイプではないですし、非常に運がいいだけ。あまりクライアントを獲得することに対しては努力もしませんし、がんばって何かをすることもほとんどありません。その理由は、エージェントがいないこと、コミュニケーションをあまり取らないこと、ウェブサイトを持っていないことにあると思います。それらが自然なフィルターの役割を果たしていて、私に連絡をしてくる人たちは、なぜ私に連絡したいのかをよくわかっているのです。つまり、私には簡単にはアクセスできないので、ある程度のモチベーションが必要だと言えるかもしれません。ご存知のとおり、私には一つのスタイルがあるので、あらゆるタイプのクライアント、あらゆるターゲットのためにプレーすることはできないんです。だからこそ、クライアントが自然と私のスタイルを求めて辿り着いてくれていることは、とてもラッキーだと思っています。
—あなたが仕事を通して何を表現したいかを言葉にするとしたら?
長い間、自分が何をしているのか全くわからなかったんです。でも、いろんな人がフィードバックをくれるようになってから、自分の仕事を分析できるようになりました。でも、フィードバックによってスタイルを変えることはありませんでした。レストランの始まりと同じく、私は物事を可能な限り良くすることが好きだし、より良いものを作ることが好き。そして、自分のスタイルを言葉にするとしたら、リラックスしていながら、同時に洗練されたシンプルなものかな。だから、エフォートレスに見えるというか。エコロジカルな側面でも、できる限り努力はしていますが、仕事において自然を尊重することはなかなか難しいんです。だからこそ、私の作品はあまりカラフルではないのかもしれません。より自然な色調なものからの方が、よりエコロジカルな製品を見つけることができますから。リサイクルも心がけていますし、中古品を使うのも好きです。ブランドのラベルで物をランク付けしたりはしません。バランスを取ることが重要だと思います。それがエコロジカルな部分であり、私の仕事に対する、ある種の洗練と言えると思います。
—資生堂の企業文化誌『花椿』のクリエイティブ・ディレクターとしての依頼が来たときは、どんな気持ちでした?
正直、最初はスパムだと思いました(笑)。先ほどもお伝えした通り、私はウェブサイトを持っていないので、クライアントはすべて Instagram を通じて連絡してきます。たくさんのDMを受け取りますし、ときにはメッセージに圧倒されて、チェックするのが嫌になることもあるんです。だから、広告か何かかなと思ったのですが、よくよく読んでみると、とてもよく書けていて、そこには編集長の塚田優子さんからの素敵な手紙もありました。『花椿』のアーカイブのリンクが貼ってあり、一瞬で虜になりました。少し見ただけで、私の脳みそがすぐに燃え上がり、アイディアがとめどなく溢れてきたので、消えてしまわないように書き留め始めました。きちんと返信するために少し時間がかかったのですが、その間、他の仕事やプロジェクトで忙しく過ごしながらも、頭の中は、いつも『花椿』のことを考えていました。そして、たくさんのアイデアを書き留めた長いメールを送り、スッキリしました。その時点では、自分のアイディアを持って、編集室のチームを説得せねばと思っていましたが、実際コミュニケーションを始めてみると、私たちはとてもスムーズに足並みを揃えることができました。
—『花椿』の前身である『資生堂月報』からの100年分のバックナンバーをご覧になって、どんなふうに感じました?
まず、50年代のレイアウトが素晴らしいなと思いましたし、60年代から80年代は、とりわけ知的な要素を感じることができました。自動翻訳のおかげで、カルチャー的な部分も理解することができましたし、社会的なトピックを扱いながら、文学レベルの高さも感じられました。表面的でなく、トピックに深みがあったので。そして、90年代から2000年にかけてのファッションストーリーはとてもエッジが効いていましたし、年代ごとに本当にさまざまなタイプのものが詰め込まれていると感じました。
—2024年号は“CARE”に焦点を当てているそうですが、テーマはどのように定まっていったのでしょうか。
内容や可能性を考え始めて、編集長の塚田さんと共有したとき、何か赤い糸というか、共通点みたいなものが見えてきたんです。それは長い間、私の中にあったものだと思います。特にウクライナでの戦争以降、世界ではとても悲しいことが起きています。というのも、世界中を飛び回るようになってから、ウクライナにも友人やフォロワーがいますし、レバノンにも友人がいますし、パレスチナに家族がいる友人もいるので、戦争が身近に感じられるようになったんです。友人がキエフの地下鉄で寝ていて、食べ物が見つからないというときに、私が Instagram で朝食の写真をポストするのはどうなのかなと思うようになりました。コンテンツを共有するなら、まともなものでなければと。今、この世界には良識が必要であり、それはとても重要なことだと思います。だから、良識というものを、ケアそして地球というテーマを通して伝えることができたらと考えました。
—今回、グラフィックデザインは日本在住のフランス出身のアート・ディレクター Eric Pillault (エリック・ピヨ) に依頼したそうですね。
日本語はまるでピクセルのようで、細部まで完璧に表現することは私の手には負えなかったので、さまざまな雑誌で経験があり、コミュニケーションも円滑にとれるEric Pillaultに任せました。グラフィックデザインや印刷物専門のクリエイティブ・ディレクターもいますが、私の場合はそうではなく、もっと横断的なので。
—そもそも一つのことに専門的でありたいという考えはあるのでしょうか?
もし、あなたが何か一つのことにすごく秀でていたければ、何かを犠牲にしなければいけないとは思うんです。でも私は、さまざまな分野で働く喜びを犠牲にしたくはなくて。だから、自分の専門が何かを聞かれたとしたら、たぶん、スタイリング・オブジェクト、もしくはコーディネートと答えると思います。
—振り返ってみて、日本語と英語の2カ国語で発行される新たな『花椿』をクリエイティブ・ディレクションするという経験はいかがでしたか? また、“CARE”の特集を通じて、どのような気づきがありました?
日本に来るのは以前からの夢でしたが、私は観光客として旅をするタイプではなく、来る目的が必要な人なんですね。だから、日本でこのような機会に恵まれ、仕事として、日本の習慣や文化を発見できたことは素晴らしい体験となりました。また、雑誌の全体を通したクリエイティブ・ディレクションという仕事は初めてだったので、多すぎて答えられないほど、さまざまなことを学びました。それぞれの企画がたくさんの知識をもたらしてくれましたし、プロジェクトに参加するたびに、周りの人たちとの仕事の進め方についてより深く学ぶことができました。その分、自分自身と向き合う機会も増えたと思います。
—通訳はあっても、日本語環境でのものづくりは初めてだったかと思いますが、いかがでしたか?
私は、フランス人で、英語では完璧には表現できないこともありますし、常に翻訳や通訳が必要な状況は確かに難しくはありました。でも、私はコントロールフリークな人間なので(笑)、今回の経験が、人に任せることを学ぶいいきっかけになったと思います。ときには通訳をしてくれた『花椿』の編集者が、緩衝材のような役割を果たしてくれましたし。私はフランス人なので、かなり率直に話す方なんですね。一方で、日本人はすごく礼儀正しいのに対し、フランス人はそうではないので。そういうマナーの違いをうまく伝えるフィルターとなってくれる通訳者がいたことに、とても助けられました(笑)。