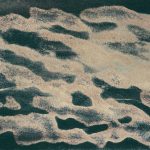取り巻く世界と関係しながら、高木正勝が記録する、音が生まれる瞬間。
masakatsu takagi
photography: asuka ito
interview & text: tomoko ogawa
人口約20人の小さな村にある自宅で、周囲の環境と一体となり、自然とのセッションを記録するという、きわめてパーソナルなピアノ曲集『Marginalia(マージナリア)』シリーズを作り続ける音楽家・高木正勝。一方で、細田守監督によるアニメーション映画『おおかみこどもの雨と雪』(12)、『バケモノの子』(15)、『未来のミライ』(18)などの映画音楽も手がけている彼が、このたびソングブック『うたの時間』をリリースした。本作には5人のアーティストがゲスト・ヴォーカルおよび作詞で参加。高木のピアノ演奏とともに、うたを携え新たなかたちで生まれ変わった楽曲たちが収録されている。リリースを記念し、ビルボードライブ大阪・横浜では、ライブも開催されたばかり。
映画やドラマ、CM、舞台といったスケールの大きなクライアントワークと、音と対話し遊んでいるようなパーソナルワーク。一見、対極にあるように思えるふたつの創作を行き来する彼が、その根底に共通して流れる“生まれる瞬間”への思いを語った。
取り巻く世界と関係しながら、高木正勝が記録する、音が生まれる瞬間。
Music
—京都に拠点を移され、その後、里山に移住されたのが2013年頃だったと思いますが、そこから12年を経て、自分の変化をどんなふうに感じていますか?
普段はあまり気にしませんが、新幹線や車で移動しながらその場所の風景を見ていると、例えば、家の隣にすぐ家があるんですよね。当たり前なんですけど。マンションも部屋同士の距離が近い。それが一番気になる。家に帰ると、200メートルぐらいの距離、人がいないので。それが当たり前で、都心に出れば人がいるのが当たり前。変な話ですが、最初の頃は、うちの村に住んでいるおじいさんやおばあさんを、当たり前じゃないそちら側として見ていたけれど、今は自分もそちら側にいる。こちら側には、自分にとっての当たり前が全部ないんです。電車の中にある暗黙のルール自体もない生活だから、周りを見て、自分も昔こういうことを気にしてたなということをたくさん見つけますね。僕もそこにいたら、そうなってただろうなと思うので、その差が面白いですね。
—『Marginalia』シリーズは、里山での生活が音楽になっていくという日記のような作品ですが、以前の作品からもその片鱗は感じるものの、完全にそれができるようになったのはやはり環境があるからなんでしょうか?
そうですね。以前から、人の音楽を聞く場合も、スタジオできちんと録られたものよりも、道端で歌っている人がいてほかの人も参加したり、いろんな音が入っている録音が好きでした。そういうものばかり聞いていると、スタジオで録音したものがクリアすぎると感じてしまって、それならライブの録音の方が好きだなとライブものをよく聞いてました。だから、一般的に、スタジオで収録したオリジナルアルバムが先行してあって、そこから派生したものとしてライブアルバムがあるといった格付けがされていることにも、疑問があったんです。僕は生まれた瞬間が面白いと思っていて。最初に出てきたくて出てきたときが一番いい。そこを僕は音楽だと思っています。そこの記録がしたいなと。
—『Marginalia』シリーズはまさに、その記録ですもんね。
はい。家で、弾きたい!と本当に思ったときしかやらないです。そのタイミングで、外でたまたま鳴っているいい音は全部味方につけます。引っ越す前もやっていたことではありますが、多くの人と同じように、以前は録ったものが自分しか聞かないデモテープになってしまっていたんです。表に出すときは、ちゃんと綺麗にしなくては、とつくり込んでいくと、イメージではここに鳥が鳴くのにとか足りないものを入れたくなってしまう。それをやっていたときに、これ、何の意味があるんだろう?とふと思ったんです。そうしたいという憧れだけを入れるのではなく、実際に起こったことを記録すべきだなと気づいて。例えば、アフリカのジャングルの民族の歌があって、そこに住んでいる人たちが本当に歌ってると思って聞いていたのに、実は別々にスタジオで録音していて、調整されていたと知ったら興醒めじゃないですか?
—確かに、悲しい気持ちにはなりますね。つまり、整える前提で音を捕まえにいくようなフィールドレコーディングのスタイルではないということなんですね。
一般的にフィールドレコーディングと呼ばれるものは基本的にしないですね。できたら自分もそこで音を鳴らして、参加したいので、この音がほしいからとどこかに行って、それを録って帰って、ピアノと混ぜるみたいなことはしないです。家でやっているときは、環境が音を鳴らしているわけですが、自分も環境の一部なんですよね。例えば、自分がいることで、鳥が来たり去ったり、自分が音を鳴らすと、鳥が歌ったり、歌わなかったりもする。本当に環境がバンドメンバーみたいな感じです。
—『Marginalia』はソロモン諸島の海から始まったとのことですが、それもつくることを目的に旅に出たわけではなく、その環境が奏でる音との出会いがあったから、という順番ですもんね。
そうです。ここにもしピアノがあったら楽曲ができるのにと思うけどないから、どうやったら自分でこの環境をつくれるだろうと考えたのが始まりだったので。旅に行くときは、大きな楽器であるピアノがないことがほぼ前提なので、自分が気に入ったいい音を見つけたら、どうやってその環境が生まれるのかをリサーチするんです。例えば、手付かずの森を残していて、その前に薮があって、でも一番手前は虫が発生するといった問題があるから、綺麗に草刈りをしているなとか。そこで手入れをしている人に話しかけて理由を聞いたり、仲良くできるのも面白いです。

—パーソナルワークを手がける一方で、細田守監督アニメーション作品の映画音楽や、NHK連続テレビ小説「おかえりモネ」のサウンド・トラックといったクライアントワークも多数手がけていらっしゃいますが、後者はどのようなプロセスで生み出されていますか?
『Marginalia』は、自分の家の音で、自分が好きな音しか入っていませんが、依頼された仕事の場合、他の人のアイディアがベースにあるので、伝えたい物語なり画面がありますよね。洋服に例えるなら、今日着る服をぱっと渡されたとする。そのときに、ちょっとどうやって着ればいいかわからないことがあるじゃないですか。なんとか着てみたけど似合ってないな、というところからスタートすることが大半です。そこから、「なんでこれをうちに渡したんだろう?」、「やりたいことはなんなんだろう?」と読み解いていく。すごく丁寧に「これは赤」ですと説明してもらったとしても、自分にはピンクに見えるときがやっぱりあって。それをどう赤に見えるようにしたらいいのか、もしくは、ピンクのよさを気づかせるのがいいのかなどを考えます。人と関わる以上、それぞれに感覚は違いますから。音楽でも、それは起こりますよね。
—とりわけ、細田監督の劇伴をつくる際は、ほかの作品とは違うアプローチをされたとのことですが、その理由とは?
観る人の数が違うというのが大きくあります。普段は本当に1人2人が聞いてくれて、褒めてくれたら幸せですが、聞いてくれる人の数が何百万人と膨らんだときに、わからない!と立ち止まるんですけど、一周ぐるっと回って、自分が子どもの頃は純粋な耳で音楽を聞いていたなと思ったんです。子ども時代の自分が納得する音と考えると、それはそれでまたハードルがすごく高くなってしまうんですけどね。
—純粋な子どもの頃の自分の感覚を大事にしながら、同時に多くの人に届けることを考えなくてはいけないんですね。
そうですね。でも楽しいです。みんなも遊べるし、自分も行って遊べる公園をつくるみたいな感じで。
—それで、歌をイメージしながら楽曲をつくっていったということなのでしょうか。
子どもだった頃、例えば『となりのトトロ』を見たとして、覚えているのは、劇中鳴っている音楽ではなくて、主題歌かエンディングで流れているフレーズだと思うんです。それをずっと口ずさむから。でも、映画音楽は、そうではない劇伴部分を指しますよね。そうであっても、小さい子どもが見て伝わるものをつくらなきゃいけないと思ったときに、一曲一曲を主題歌としてつくるような気持ちでやるという方法に、たまたま行き着いたんです。つくり方がわからなかったので。そうすると、口ずさみながら進めるので、全部歌になっていくんですね。それを後からオーケストラに戻していきました。
—オーケストラにした劇伴を、歌い手の方がそれぞれ歌詞をつけたのがアルバム『うたの時間』なんですね。
オーケストラにして終わりでよかったんですが、終わってみると「これ、歌だったのにな」という思いがずっと残っていて。三作の映画音楽をやらせてもらったので、曲も溜まって、いつか成仏させてあげないと、とは思っていました。
—人選の過程で、母親かどうかではなく、母に対する想いがある人に歌ってほしいという考えから、クレモンティーヌ、アン・サリー、寺尾紗穂、角銅真実、Hana Hopeといった女性アーティストたちに辿り着いたそうですね。
最初の話に結局つながりますが、何かが生まれる瞬間が好きということが基本にあるので、何をつくっても、僕は結局そこに行ってしまうなと。『うたの時間』では、みなさんに具体的にこういうことを書いてほしいとリクエストはしなかったけれど、生まれる前の記憶についてだったり、お母さんになる喜びだったり、いろんな段階の生まれる瞬間のうたを書いて歌ってくれました。『Marginalia』も、周りの環境と一緒に季節を生み出している、自分も春だったら春、夏になったら夏の一部になるという感覚でやっていて。「お母さん」というキーワードがしっくりくるのかはわかりませんが、イメージとして、何か見出す場所、力、時間、なぜ、それが生まれるのかへの興味が一番強いんですよね。だからどうしてもこういうテーマになってしまう。1回は生み出せたけれど、もう生み出せないかもしれないという考えとも毎日闘っています。だから、生み出せるように日々整えて、生み出せるという自分でいたいですね。
—コンサートやライブはまさに生ものだから、生まれる瞬間のものですね。
今ここでしている話も、もう1度同じことを数分後にしたら、すごいしらけるじゃないですか。そう考えてはいるけれど、1日に2公演がある場合、どうしてもMCの流れで同じ話をするしかないというときがあるんです。そうなったとき、一気に脳が止まるというか (笑)。色々気にしてしまって、間違えるし、すらすらと言葉が出てこなくなる。だから、ライブでの演奏も、一番よかったものに向かってその再現にならないように、今生み出したかのようなものをみんなで目指してはいます。でも何がきっかけになるかはわからなくて、誰かが失敗しそうになることがきっかけになることもあるとは思います。
—日々整えてはいても、もう生み出せない!みたいに打ちのめされることもありますか? そういうときはどう乗り越えていますか?
もちろん、あります。一人の場合は、足掻いて、それでも無理なら頭が痛くなって止まるときもありますけど、舞台上でそれが起こったらもう最悪です (笑)。ただ、こちらが足掻いていることが逆にお客さんにとって何かのきっかけになったり、足掻いてるからこそ、お客さんが自分も同じだと感じてくれて、ずっといいコンサートではなかったかもしれないけれど、最後の最後に一瞬だけ光が見えたということがもし起これば、それはいいコンサートと言えるとは思うんです。とにかく、一生懸命やる、それしかないですね。