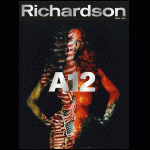エクスペリメンタルロック・バンド Battles (バトルス) インタビュー
Battles
昨年、インストの新作『La Di Da Di』をリリースし、フジロック’16への出演も決定した Battles(バトルス)。ギターとキーボードを自在に操る Ian Williams(イアン・ウィリアムス)、バンドのグルーヴについて正直に語り尽くす。
エクスペリメンタルロック・バンド Battles (バトルス) インタビュー
Music
「今年のフジロックはすごい」。最近、まわりでそのような声を耳にすることが本当に多い。確かに、1月末に発表された第一弾のラインナップは、20周年というメモリアルイヤーを迎えたフジロックへの期待値を限界まで引き上げた。世界でもっともビッグなバンドであり続ける Red Hot Chili Papers(レッド・ホット・チリ・ペッパーズ)と、2013年には武道館での単独公演をソールドアウトさせた Sigur Rós(シガー・ロス)という2組のヘッドライナーを筆頭に、自らの作品で「実験=ポップ」を証明し続けてきた Squarepusher(スクエアプッシャー)、イギリスの労働者階級にとって唯一の希望 Jake Bugg(ジェイク・バグ)、アンファンテリブルという呼び名が相応しいDisclosure(ディスクロージャー)、シェリル・クロウが出てきたころを思い出す Courtney Barnett(コートニー・バーネット)まで、実に抜かりない。Kamasi Washington(カマシ・ワシントン)、Leon Bridges(レオン・ブリッジズ)、Robert Glasper(ロバート・グラスパー)という、ロックやポップス“以外”の分野への目配せも完璧だ。そして先日、最後のヘッドライナーとして、最新作『Morning Phase』がグラミー賞に輝いたベックがアナウンスされた。音楽的には、間違いなくここ数年で1番の充実度。
さて、そんなラインナップの中に、Battles(バトルス)も“鉄板の存在”として名を連ねている。ジョンのドラミングで苗場の地面が振動する瞬間を想像するだけで鳥肌が立つが、インダストリアルなループを中心に据えた最新作『La Di Da Di』を聞けば、そのイメージはさらに祝祭性を帯びるはず。つまり、これはバトルス史上もっともフィジカルな快作。ハードコアというメンバーのルーツを考えるとこういう言い方が相応しくないかもしれないけれど、このサウンドはかなり気持ち良い。この作品に、文字通り“言葉”はいらない。グルーヴの真相を確かめるべく、昨年来日した Ian Williams(イアン・ウィリアムス)に話を聞いた。
―今日実際に会ってみて、バトルスのみんながこんなにフレンドリーだとは想像していませんでした。音楽とは違った印象ですね……
みんなごくごく普通の連中だよ。優しさにはレベルの違いがあるけどね。おそらく、僕が一番不親切。
―今作でも、普段住んでいるNYから離れたロード・アイランドのスタジオにこもってレコーディングを行ったそうですが、スタジオ入りして最初にすることは何ですか。
あらかじめダイレクトボックス(DI)で録った音をスタジオで再生して拡張することから始めることが多い。
―ちなみに、DIで録ったサウンドをスタジオで再生するというのは……?
レコーディングで最も重要なのは再拡張の工程だ。たとえば、DIで録った電子音は人工的だけど、それを実空間に放ってもう一度録音することで、立体的な音に変化する。この工程を経ることで、僕らのサウンドから冷たさが抜けて、有機的なものになるんだ。
―なるほど。では、スタジオでは何を重視しますか?
とにかく話し合うこと。曲のアレンジについての議論には、いつも相当な時間を注ぎ込む。「いくつかアイデアがあるけど、どうやって組み合わせるのがベストかな」とか、「このサウンドの雰囲気で合ってる?」とか、あまり進展のない話ばかり。ソファに座り込んでダラダラと……まあ、そんな感じ(笑)。今回は、予定より3週間作業を延長して、それ以上はスタジオが埋まっていて予約が取れなかったから、一度ニューヨークに戻って、スケジュールが空いたタイミングで再度スタジオ入りする羽目になった。そんなこんなで、結局4ヶ月ほどかかってしまったんだ。
―今作は相当な難産だったと言えますね。
まあね。レコードの制作が容易でないことは理解しているよ。
―そもそもロード・アイランドでレコーディングするようになったきっかけは?
『Mirrored』を制作している時に、ミシガンのスタジオでレコーディングするはずだったのが、急遽スケジュールが変更になって、そこが使えなくなってしまった。すると、デイヴの友人がロング・アイランドのスタジオを運営していることがわかって、かわりにそこで録音することになったんだ。まわりに何もない場所だったけど、その分スタジオとの関係が深まって、上手い具合に事が運んだわけ。だから、意識的に始めたわけじゃない。ただ、東京と同じで、ニューヨークは物価が高すぎる。1時間しかレコーディングの時間がとれないような高いスタジオじゃ、いろんなことを試すこともできない。時間をかけておかしなことを試しながら、“ハマる音”を探すことはとても大切だと思う。
―『La Di Da Di』のメイキングを記録したドキュメンタリー『The Art of Repetition』では、ループ作りもフィジカルな作業に見えましたが、あれは即興なのですか。それとも、あらかじめ他のメンバーと準備しておくのでしょうか。
あらかじめ用意していることが多いね。即興はなかなか上手くいかない。なぜなら、バトルスはとにかく音量が大きいバンドだから。最初からジョンが大音量でドラムを叩くもんから、デイヴと僕も自分の音が聴こえるまでアンプのボリュームを引き上げて、するとジョンが更に大きな音でドラムを叩いて……みんなが自分の“アート”を探るのに必死になって、他のメンバーの音が耳に入らなくなるんだ。別々に録音したほうがお互いの音に耳を傾けられる。だから、数ヶ月間1人で部屋にこもってアイデアを練って、良さそうな音が出たら「これ聴いてみて」なんて具合にメンバーと共有する。すると、「こうアレンジしてみたら」なんてコメントが返ってきたり。この方法で進めたほうが楽だし、効率的だね。とはいえ、即興でやることもないわけではないから、その場合はまず“挨拶”から始めることになる。いわゆるウォーミングアップ。設備の揃ったリハーサル・スタジオで、24時間分厚い壁に囲まれて録音するんだけど、ご近所のミュージシャンは僕らに嫌悪感を抱いてるよ(笑)。だって、「ガシャンガシャンガシャン」なんて大音量でループをセットして、その上から更に4時間くらい「ガシャンガシャンガシャン」と楽器を重ねるんだから。
―ドキュメンタリーの中で、バトルスのメンバーがスタジオで真剣に演奏している最中、一瞬だけお互いに微笑みあう瞬間がありますよね。あれはどういうことなんでしょうか。
笑顔くらいあるよ。そんなにシリアスなバンドじゃない(笑)。でも、僕が若い頃、バンドの練習中にベースの奴がニヤけた顔をこっちに向けてきたから、僕が「ニヤついてる奴は失せろ」と言って手を止めたことがあったらしい。というのは、人から聞いた話で、僕はあまり覚えてないんだ。それにしても、笑顔を拒否するなんてね。今のバトルスがそこまで大真面目かどうかと聞かれると、答えは「ノー」だ。
―以前に比べると、今回のアルバムはサウンドがシンプルで、バトルスが持つ音楽性のコアな部分がより際立ったように感じました。
それはよかった。実は、ぼんやりそういう風にしたいとは考えていたんだ。前作までは、各々が出す音の化学反応が余すところなくリスナーの耳に入るように、「こちらの道への侵入はご遠慮下さい。あちらへどうぞ」みたいな感じで、交通整備をすることに重点を置いていたかもしれない。それに比べると、今回はよりリラックスしてたかな。何か良い音が聴こえると、手を加えるのではなく、そっとしておいた。
―ループで音を重ねていく作業は一見終わりのないように見えますが、曲が完成するタイミングはどうやってわかるのでしょうか。
何だろうね。「オーケー、もう十分」っていう感覚が訪れるんだ。さっきも話したとおり、このアルバムでは元のアイデアに音をたくさん追加して複雑なサウンドを作ろうとする衝動を意識的に抑えてみた。もちろん、今の僕らにも乗り越えるべき課題はたくさんあるけど、曲の終わりを決める部分に関しては、あまり苦労してないと思う。

La Di Da Di
―今回のアルバムをインストにするのは、レコーディング前から決めていたことなんですか。それとも、スタジオに入ってから決めたことなんですか。というのは、インストだということを終始意識させない作品になっていると思ったので。
いいね。僕らもあまり意識せずに作ったんだ。バンドを結成した当初は、女性ボーカルを何人か入れるアイデアもあったけど、複雑になりすぎる気がしてね。「よし、当分はインストゥルメンタルに集中しよう」ってことになった。もちろん、過去にゲストボーカルに参加してもらったことはあるし、今のサウンドにも歌声が入る隙はある。ただ、僕らが作った音楽に歌声が入ったとしても、それは楽器やエフェクトのひとつでしかない。キーボードを入れるのと同じ感覚なんだ。「ボーカルがメインで、インストは背景でしかない」というようなポップ・ミュージック的な考え方をする人もいるけど、僕たちの場合は逆だね。ボーカルは音楽の一部であって、前に出るものじゃない。
―それぞれ好きな音楽について他のメンバーと話すことはありますか。今回のレコーディング期間にスタジオで聴いていた音楽があれば教えてください。
レコーディング中、たまに「それ、Gary Glitter(ゲイリー・グリッター)みたいだね」なんて口走ることもあるけど、必ずしも特定のアルバムや曲を頭に描いているわけではない。夢の中で聴いた音とか、子供の頃に聴いた音楽のように、あくまで漠然としたイメージに過ぎないから。
―スタジオの雰囲気を良くするには、なにが大切だと思いますか。メンバーと話し合いを進めるときには、誰が進行役に徹するのでしょうか。
ほとんどの場合、取り組むべき課題についてはお互いに理解しているかな。今作のアイデアは、デイヴと僕が何となく鳴らし始めたループがきっかけになって生まれた。それぞれ最低でも15くらいのアイデアを出し合って、お互いにコメントを言い合う。そうやって方向性を定めて行くんだ。ちなみに、どんな音がエキサイティングなのかに関しては、メンバーで共通の感覚を持っているよ。
―エフェクターや音楽制作ソフトの情報はどこで得ているんですか。
ベルリン在住のアメリカ人男性が編集している「Create Digital Music」というウェブマガジンから。ソフトウェアとハードウェアがバランス良くカバーされているんだ。

Dave Konopka (デイヴ・コノプカ), John Stanier (ジョン・ステニアー), Ian Williams (イアン・ウィリアムス) | Photography: Hidemasa Miyake
―自分はエフェクター・オタクだと思いますか。
徐々にオタク色が強まってる。ただ、次にどんなソフトを買うかとか、そんな話ばかりする機材オタクの友達に限って人気のないバンドにいるから、複雑な気持ちだよ。成功している奴らはとにかく演奏の練習に余念がないから。僕としては、機材に熱中しすぎても、機材に無頓着になりすぎても良くないと思う。それでも、ソフトに関してはどうしても熱狂してしまうんだ。何だか、脳に訴えかけるものがあって。
―バトルスにとって、バンドの進化とはどういうことを意味しますか。
自分たちの芸が完成したとは思っていない。だけど、器用に音楽を作る方法は分かってきた。バンドって、駆け出しの頃はユニークで新しいアイデアに満ち溢れているけど、レコードを数枚作ると普通のことをやり始めて退屈になる。「初期は良かったけど、つまらなくなったね」なんて言う奴がよくいるだろう。だけど、別の側面を見ると、練習すればするほど演奏は上手くなるはずなんだ。いや、自分たちがそう思っているだけで、まわりから見れば「退化している」ということもあり得るのか……。
―上手くなるってどういうことだと思いますか。
さあね。ただ確かなのは、原始的で自らの行動を自覚していないときのほうが、変なマジックを発揮するものだ。でも、きちんとしたやり方が分かった途端にそのマジックが消えてしまう。奇妙で間違いだらけなのがクールだったのに、って思われるわけ。誰かが言ってたけど、ロックン・ロールっていうのは、自分が何をしているか分からない状態のこと。だから、誰かの耳に届くまで音を鳴らし続ける。上手くでてきているかどうかなんてわからない。ただ、キャリアを重ねても、インプットを怠らず自分の限界を越えようと心がけていれば、少なくとも自分への誠意は残るし、それは音楽にも表れてくるはずだよ。
―理想的なキャリアを歩んでると思えるバンドやアーティストはいますか。
実は、そのことについてずっと考えていたんだ。小説家は、歳を重ねるほど腕を上げるよね。60代になって代表作を書く小説家もたくさんいる。でも、ボブ・ディランが60歳の時に作ったアルバムがベストだと思う人はいないだろう。どうしてだろう。ペインターや映像作家も、熟成し続ける。まだクラシック音楽家であれば腕を磨き続けることもあり得るけれど、ロックバンドとなると、一生期待に応え続けるのはかなり難しい。40代になったらもう……(飛行機の墜落音を真似ておどける)。変なもんだよね。指の動きが遅くなるのかな。
―デジタルに何を期待しますか?
例えば、1.65っていう数字を正確につまみ出すことができる。そういう緻密なプログラミングの中に、「そこだ!」っていう魔法みたいな瞬間が訪れることがあるんだ。ループをコピーし続ければ、曲に永久性を与えることもできるから、デジタルはポップ・ミュージックの枠を大幅に拡張するかもしれない。
―意図して世の中の動きを音楽に反映することはありますか。
僕たちは政治問題を音楽に取り込むのは避けてきた。それよりは、音楽性を重視したほうが解釈の幅が広がって、もっと深いものになると思うんだ。右翼のファシストが音楽を通して想像を膨らませるのは困ったもんだけど。いや、そうとも言い切れないかもしれない……じっくりと考えてみないと、わからないな。
―バトルスの音楽を通してオーディエンスに伝えたいことはありますか。
人間が言語を作り出す前から存在していた“音楽”というものの素晴らしさ。
Special Thanks : Marie Sasago