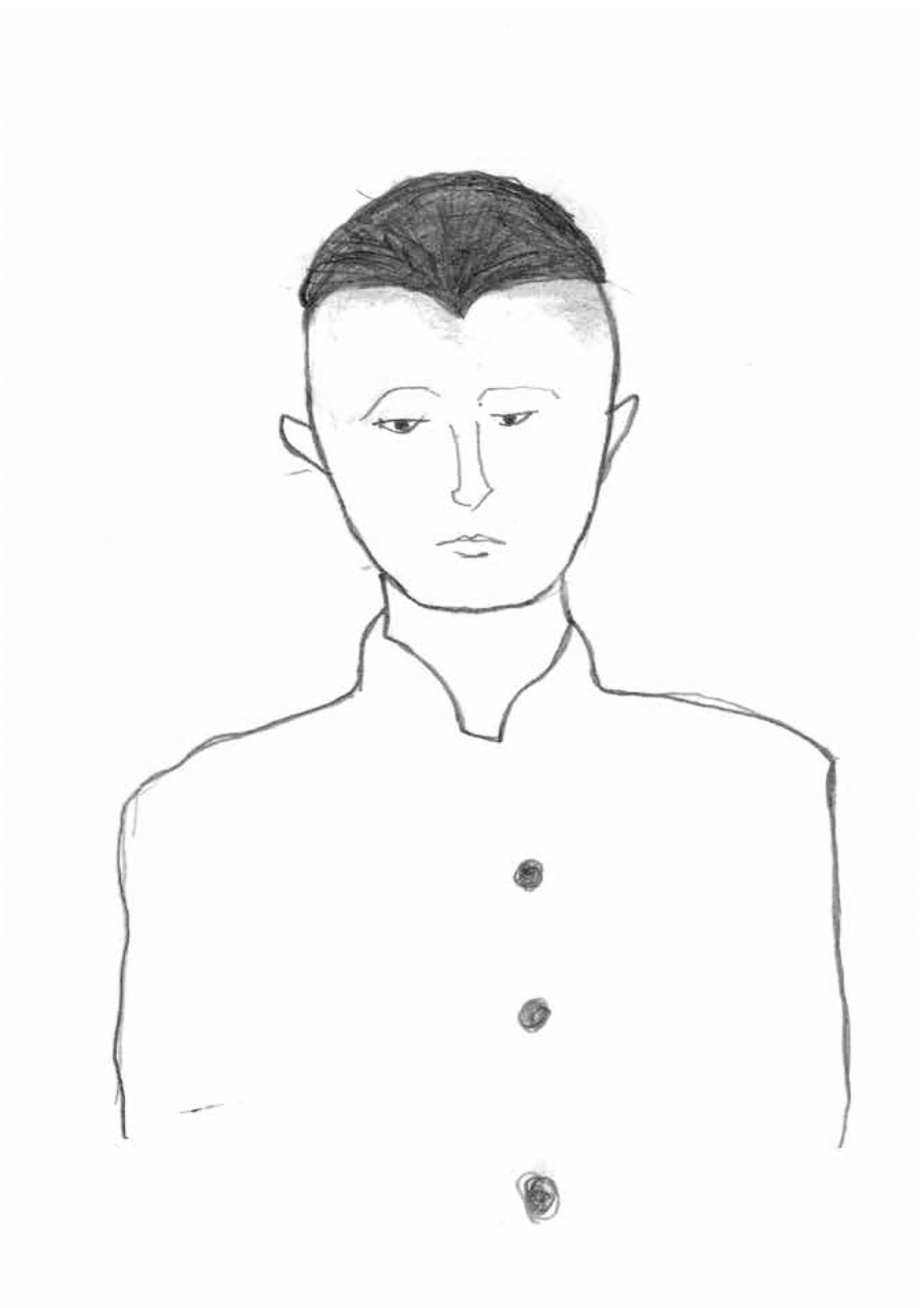『半分、生きた』映画監督 豊田利晃 インタビュー
Toshiaki toyoda
photography: Hiroki Watanabe
text & interview: hiroaki nagahata
新作短編映画「狼煙が呼ぶ」にあわせて制作された豊田利晃の自伝『半分、生きた』では、彼が大阪で将棋棋士を目指していた時代から、阪本順治監督の『王手』の脚本を手がけたことをきっかけに映画の世界へ足を踏み入れ、千原ジュニアや松田龍平などの若き才能と出会い、2度逮捕され、多くの人を失い、その中で映画を作り続けていったという「事実」が、丁重な筆致で描かれている。
『半分、生きた』映画監督 豊田利晃 インタビュー
Film
この本に収められている文章は元々、小笠原諸島を舞台としたドキュメンタリー作品『PLANETIST』の製作時に、写真家の菊池修によって撮影された風景をまとめた写真集につくはずのものだったが、わけあって文章だけが残った。これはもはや、一つの脚本である。今改めて、豊田監督の作品を振り返るのに、この本ほど良いきっかけはないと思う。

『半分、生きた』(HeHe)
-この本の中で、豊田さんはむかしナイフをよく持ち歩いていた、という話が強く印象に残ったのですが。映画の中にもよくナイフが登場しますよね。
僕が学生時代を過ごした80〜90年代の大阪って、電車の中で他人と目が合うだけで喧嘩が始まるような感じだったんです。要は「メンチを切る」っていう。だから、ナイフは単に護身用ですよ。絡まられるし、巻き込まれるから。特に、僕の出身の布施という地域は、「日本でカツアゲと自殺が一番多い街だ」って中島らもさんも書いていました。この地域の荒れ具合は、『実録外伝 大阪電撃作戦』っていう映画でも描かれていますよ。
-その空気は個人的にどう受け止めていましたか?
僕はすごく嫌いでした。ずっと避けたかった。
-でも、映画の中ではそういう環境の真ん中にいる人たちのことを描くことが多いですよね。
逆に僕はいつもその「周辺」にいたから、彼らのことが描けるわけですよ。僕自身、高校はすごく柄の悪い私立に通っていたんですが、そういうやつとは仲良くなったし。
-最初の作品『ポルノスター』では、渋谷を舞台にしていましたよね。
21歳の時に東京へ来て、スクランブル交差点を歩いた時に、大阪と違ってみんなが他人に無関心なことに驚いて。で、主役は千原(ジュニア)くんでいくと。彼が自分とダブって見えたんです。
-千原さんとは、どこでそんなに意気投合したんですか?
それはわかんない。男同士だから、気が合ったというだけ。彼と初めて会ったのは、『エスクァイア』で僕がライターとしていった取材の現場で。彼とは飲みながら話して、そのままジュニアの家に泊まりにいきました。
-今改めて、ヤクザの世界を描いた『ポルノスター』を観ると、この国でこんな暴力が存在していることに実感がわかず、少しファンタジーにも見えました。
90年代の東京って、まさにあんな感じだったんですよ。道端でマジックマッシュルームが売られていたような時ですからね。じっさい映画には、関東で幅を利かせていたチーマーのボスに出てもらいました。僕は真面目な普通の子なんで、だからこそ色々と話をしてくれた。オウムの残党とかも、取材かねてつるんでいましたよ。だから、若い人たちにはファンタジーに見えるかもしれないけれど、あれはリアルなんです。劇中、ジュニアが言う「ヤクザはいらん」も実際に僕が耳にした言葉だし。

千原ジュニアによる『半分、生きた』挿画
-豊田さんはご自身の作品を通して、ある「サイド」の人たちにスポットを当てるという意識はありますか?
そういう気持ちでは映画を撮っていない。ただその時に撮りたいストーリーを撮っているんです。少なくとも、「弱者に寄り添う」なんてことは考えたことがない。いるとすれば、自分の側、自分の身の回りにいる側、というだけ。大きな全体におけるポジションを意識することはないですよ。誰だって仲間はいるじゃないですか。僕も半径5メートルくらいで考えています。
-「自分の身の回りにいる側」という話でいうと、本の中に、「松田龍平、新井浩文、大柴裕介、高岡蒼佑、瑛太、又吉直樹。新しい若者との出逢いで、何か救われたような気がした」という一説がありました。彼らのどこに魅力を感じましたか?
映画って、脚本とキャストが優れていれば、仮に監督がアホでも良い映画になるんですよ。だから、現場に良い人たちが集まってきた時点で、「良い映画になるな」と感じられる、という話ですね。映画は時代のものだから、何となく自分が好きなタイプの役者を並べた、と。又吉もあの頃から面白かったし。
-豊田さんは映画俳優に一番何を求めますか?
背中に背景がある人。プロダクションから「映画に出たいです」と推薦されたような人じゃなくて、本人にそれまでの人生がちゃんと“在って”、その延長上に現実なのか虚構なのかわからない物語が現れるような人。それは、雰囲気というか顔というか、存在に出てくるものです。僕は俳優と個人的に付き合うタイプではないんですが、現場を一回やればたいてい仲良くなりますよ。
-ご自身の作家生活を通して、言い切りたいものはあるんですか?
それはね、一本一本です。映画ごとに何かを言っている。僕は自分のキャリアを俯瞰して批評することはないんで。自分の映画を観ることもほとんどないし。「あの時ああすればよかった」って思ってしまうから。
-豊田さんは脚本から撮影、編集まですべて手がけられることが多いですよね。それは、当初のコンセプトをできるだけクリアに伝えるためかなと勝手に思っていたのですが。
いや、それはぜんぶの作業が面白いし、脚本に関しては自分で書く方が早いからで。僕は3日くらいで書き終えて、そこから何度も直すのに時間をかけるんです。映画はチームワークなので、『がんばれ!ベアーズ』みたいなものですよ(笑)。僕が一番偉いわけじゃない。
-豊田さん自身の声をきちんと反映させたいから、そういう作り方をしているわけではないですか?
僕の声を形にするために、3億も4億も出してくれる人なんていないんですよ。映画づくりは仕事なので。小説家だったら私小説でもいんだけど、映画は集団作業だし、ちょっと違いますよね。(自分の声に関しては)作家なんだからおのずと出てしまうものなだけで。僕自身としては、ただ僕自身なので、そういう意図では作っていない。「自分が思っていることは、実は多数派なんじゃないか」と思いながら映画を作っています。
-そこは僕が勘違いしていました。
『七人の侍』とか『大脱走』のようなエンタメを作ろうと思っているので。「おれの人生=映画」じゃないんですよ。自分が体験した要素はもちろん多少組み込まれているけれど、基本的には物語を想像しながら作っています。
-では、豊田さんにとって理想的な映画とは?
世界中の人たちが観て面白いと思う作品ですよね。『ゴジラ』とか『七人の侍』のような世界映画。そういう地点まで到達したいと思います。
-ただ、作品ごとにその裏側で何があったのかを淡々と描いている『半分、生きた』は、「自伝」という触れ込みで発表されましたよね。そうすると、作品が個人の感情と紐づいて解釈されるリスクはありませんか?
これは、『狼煙が呼ぶ』が公開されるから、あくまでプロモーションの一貫ですよ。僕は映画のためにしか動かないから(笑)。僕は、そんなに自分のことを好きじゃないんだけど、僕の映画を好きでいてくれている人はいると思うから、「映画作りの裏にこんな現実があったんですよ」というのを書くのはいいかなと。あと、『ポルノスター』の時は僕が一番歳下だったんだけど、今は現場で自分が一番歳上になったので、下の世代に向けて書き残したい、という理由もあったかな。
-本の内容がもう一本の映画になっていますよね。
それはね、職業柄。ただ、この内容には嘘がない。まだ書けないこともたくさんあるんだけど。まあ、それは色々ありますよね。
-改めてご自身の半生を振り返られて、何か思うところはありましたか?
本当に色々あったなと。周りで人、死にすぎやろ、って。だけど、人は自分の人生しか生きられないから、それが特別かどうかはわからない。自分の人生に対しては批評的になれないんじゃないですか。
-自伝を読んで勇気を得たことはありますか?
昔から伝記ものはよく読んでいましたよ。黒澤さんが『羅生門』を発表するまでが描かれた『蝦蟇の油』は、文体がすごく誠実で好きでしたね。

-豊田さんが映画の中で一番重んじられているものは何ですか?
カット割りの美しさ。最初は映画の助監督として現場に入って、そこから自分が監督として映画を作ることになって、どこから始めるかというと、断片的に思いついたカットを積み重ねていくわけですね。
-カット割りの美しさは言葉で説明できるものですか?
言葉じゃ説明できないけれど、観た人はわかるんじゃないかな。
-カット割りが美しいと思う監督を教えてください。
もちろん、黒澤(明)さん、小津(安二郎)さん、成瀬(巳喜男)さん、深作(欣二)さん。海外にもたくさんいらっしゃるし、挙げきれないですけど。
-最近、個人的に良かった映画は何ですか?
『鬼龍院花子の生涯』。だから今も浴衣を着ているんです(笑)。
-最後の質問です。今の時代に対して思うことはありますか?
言葉にするとすごく軽いし、言った瞬間に逃げてしまうものなので。それを一本の映画にするのが僕の仕事。自分で温めて、バーンって吐き出した方が、お客さんが喜んでくれるじゃないですか。