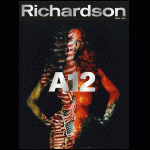「愛されるために映画をつくる」巨匠クロード・ルルーシュの人生観
Claude Lelouch
photography: utsumi
interview & text: waka konohana
フランス恋愛映画の金字塔『男と女』の公開から53年。キャストはそのままに、美しき男女の愛の終末を描いた最新作『男と女 人生最良の日々』が1月31日(金)より公開する。TFP では、昨年来日を果たした巨匠 Claude Lelouch (クロード・ルルーシュ) にインタビュー。82歳となった今でも自らメガホンを取り、作品を生み出し続ける彼に、これまでの映画人生を振り返ってもらった。
「愛されるために映画をつくる」巨匠クロード・ルルーシュの人生観
Film
フランス恋愛映画の金字塔とも称される1966年制作の『男と女』。映画を観たことがない人でも、故・Francis Lai (フランシス・レイ) が作曲した「ダバダバダ……」という美しい旋律は耳にしたことがあるだろう。1966年に Claude Lelouch (クロード・ルルーシュ) が監督した本作は、製作資金が集まらぬ困難のなかから生まれたが、同年の第19回カンヌ映画祭で最高賞のパルムドール、1967年アカデミー賞外国語映画賞とオリジナル脚本賞を受賞するという快挙を成し遂げた。以降、Francis Lai とタッグを組み、『パリのめぐり逢い』(1967)、『白い恋人たち/グルノーブルの13日』(1968)、『男と女の詩』(1973)、『愛と哀しみのボレロ』(1981)、『男と女II』(1986) など男女の機敏を描いた作品を生み出してきた。
『男と女』から53年。1月31日に公開される『男と女 人生最良の日々』は2作目『男と女II』から33年経って制作されたシリーズ第3作目となる。1作目と2作目と同様に主役に Anouk Aimée (アヌーク・エーメ) と Jean-Louis Trintignant (ジャン=ルイ・トランティニャン)、彼らの子供役にも同じ俳優を起用した Claude Lelouch が53年後に見つけた愛の形とは。少年時代からカメラをいじるのが好きで13歳の頃から映画づくりを始め、フランス映画界を牽引してきた監督に、男と女、人生、映画の未来について語ってもらった。

© 2019 Les Films 13 – Davis Films – France 2 Cinéma
―「過去でも未来でもなく現在が一番大切だ」とインタビューで監督はよく語っていらっしゃいますが、恋愛においても同じ考えをおもちですか?
”現在” にこそ幸せが潜んでいると思います。美味しいワインを飲んでいる瞬間、女性とベッドに横たわっている瞬間、”今ある”喜びを十分味わえない人は幸福に近づくことができません。恋愛において現在はキャッシュのようなものです。現実の幸せとは、将来の約束でも、過去の想いでもありません。過去の幸せを思い出すのは、死人を胸に抱いているようなもの。もちろん、愛をどのように考えているかには個人差があると思いますが、個人的には男と女がベッドに行くためになぜあれほど苦労し、その後、一緒のベッドに寝ないためになぜあれほど悩むのか不思議でなりません(笑)。映画についても同じで、私が確かに感じられるのは”現在”しかないので、カメラは”現在”を映し出すことしかできないと思っています。
―『男と女』の第1作目は資金面で非常に苦労され、その苦労がかえって斬新な映像と音楽処理を生み出したといわれていますが、第3作目である本作のチャレンジは何だったのでしょう?
今では Anouk Aimée も Jean-Louis Trintignant も85才をこえていますし、Jean-Louis Trintignant は目もほとんど見えず歩くのにも不自由している状態なので、本作ではスピーディーな恋愛物語を展開しなければいけませんでした。7~8週間もかけて撮影していると2人が疲れて本領を発揮できないので13日間で撮ったんですね。とはいえ、急いで撮影をしてしまうと物語もキャラクターも脆弱になってしまう……。短い期間で彼らのベストを切り取ること、それが今回の挑戦でした。
―そもそも、「自分の傷を自発的に活かせるような俳優を起用したい」ということで Jean-Louis Trintignant と Anouk Aimée を選んだと聞きました。今回、彼らについて改めて発見したことはありますか?
すべての人は変わっていきます。同じ1日のなかでも、時間によって違う自分がいますよね。私の映画で最も美しいと思うシーンは、俳優が最も機嫌がよいときと最も機嫌が悪いときのどちらかで、こういった精神状態の俳優は思いもよらぬ力を発揮してくれます。俳優の機嫌がよくも悪くもないというときは、そのシーンはまぁまぁの中間的な範囲にとどまってしまう。つまり、「多分」「よく分からない」という状態よりも、「YesかNoか」の決定を下すときの人間は、より美しい。なぜなら、決定を自分で下すときの人間の自発性は真実に一番近い状態だと思うからです。結局、真実や真理といったものは誰にも分からない。人間がどこから生まれてどこへ辿りつくのか誰も知りません。ビッグバンが宇宙の始まりだと言われていますが、映画のようなフィクションの概念だと私は思っていて、女性が「I Love You」と私に語るときにこそ、ビッグバンが私の心に起こる……この瞬間のほうが私にとっては真実です。人々にビッグバンを起こす小さな出来事を撮るのが私は好きなのです。
―俳優の自発性が心にビッグバンを起こす、つまり感動を与えるということですか?
俳優の自発性が感じられないシーンはすべて編集でカットしているので、本編のすべてのシーンにおいて俳優は自発的に表現しています。どんなバカなことも際どいことも俳優はいえますが、それが自発的である限り、なぜか下品にならないのですよね。それは子供がいっていることをすべて許してしまうようなもので、俳優の自発的な表現はとても純粋で悪知恵が働いていません。一方、俳優が演技をしている場合はすぐに分かります。とはいえ、自発的に表現している瞬間も演技をしている瞬間も、リハーサルから本番まですべてカメラに収めるようにしています。どうしてかというと、人間の目を撮影したいから。人間は言葉でいくらでも嘘をつけますが、目は唯一嘘のつけない肉体の部分です。きっと私は、映画は人間の目を映すことができるから、舞台監督よりも映像作家になったのでしょうね。私は人の目を読み取る術を若いうちに覚えてしまったので、目を見ればすぐにその人がどんな人かわかるのですよ。
―最初の『男と女』では Alberto Giacometti (アルベルト・ジャコメッティ) の「芸術よりも人生だ」という言葉を Jean-Louis Trintignant がセリフで引用していますが、このときの監督はまだ興行的には成功していらっしゃいませんでした。もし『男と女』の興行的成功がなかったら監督は何をしていらっしゃったと思いますか?
きっとならず者になっていたでしょうね。女性にモテそうですから。音楽家、カーレーサー、闘牛士とか女性にモテる職業に就いていたかもしれませんが、『男と女』がカンヌでグランプリを受賞し、アカデミー賞を受賞して以降、映像作家も女性にモテることがわかったので続けてきました (笑)。いずれにせよ、人間は人に愛されるために、色々な苦労や困難に立ち向かうと思うのです。François Truffaut (フランソワ・トリュフォー) は女の子をナンパするために映画を作っているといっていましたし。だから、自分は愛されるために映画を作っているということを恐れずにいいたいですね。なんて言っても、私が映像作家になったのは自分が女性よりも映画を愛するようになったからなのですが。
―『男と女』を撮影したとき、Jean-Louis Trintignant にも Anouk Aimée にもそれぞれに配偶者がいましたが、監督ご自身はまだ26歳の未婚の青年でした。そんな若いときに、大人の恋愛模様をあれだけ繊細に描けたことに驚いています。
1作目では、自分にとって理想の恋愛の形を描きました。当時は自分が若かったので、傷ついた経験のある女性を幸せにするほうが簡単だと信じていたのですね。何の経験も積んでいない女性にとって愛は気まぐれでしかありません。そんな甘やかされた子供みたいな女性を幸せにするのは不可能ですから。あの映画を撮ったときは、夫を亡くして不幸を知っている子供のいる女性を恋人にしたいと夢見ていて、そんな女性を幸せにしたいと思っていました。でも、女性と出会うたびに私の恋愛観は変わりますがね。
―監督の映画『愛と哀しみのボレロ』には「人生には3つか4つしかパターンがない」というようなセリフがありますが、それは監督の人生観なのでしょうか?
人生のパターンは3つか4つぐらいしか質的に存在しないと思っています。映画づくりだって、物語やキャスト含む、プロセスが違うだけでやっていることは毎回同じです。例えば、宗教にしろ、脚本とセリフはほぼ同じですが、監督が違うので、こちらの宗教のほうがあちらよりも好きといった個人的な好みが出てきます。もし Roman Polanski (ロマン・ポランスキー)、Jean-Luc Godard (ジャン=リュック・ゴダール)、私に同じ脚本の恋愛映画を撮らせたら全く違う作品が出来上がるでしょう。でも、愛の物語は同じ。始まりと中間があって愛の終わりが必ず来る。人生は同じストーリーを語っているけれど、監督と出演者が違う。『男と女』にしろ、これまで何度も語られてきたラブストーリーですが、予算の制限、Jean-Louis Trintignant と Anouk Aimée の美しさ、ドーヴィルの街並み、カメラの違い、そんな要素が集まり、初めて語られたような印象の映画が出来上がったのです。すべての人は違う道を通りながらも最後は同じ死に行き着く……なのに、私は映画を50本も撮ったのですから、自分を褒めてあげてもよいかもしれませんね。
―13歳のときにドキュメンタリーを自作し、もう70年近くも映画をつくり続けてきた監督ですが、映画界の未来をどのように見ていますか?
私にとってカメラが映画の主演俳優……つまり、すべてのシーンに出演しているのはカメラですよね。ですから、監督は俳優に演出をする前にカメラを熟知する必要があります。幼い頃、私はカメラに恋をしましたが、今はスマホが発達して世界中の人々がカメラを手にしている状態です。スマホこそが未来のカメラ。だからこそ、スマホのカメラでどこまでできるかを証明したくて50本目の最新作はスマホだけで撮影しました。今、大事件が起きたときに撮影するのはテレビ局のレポーターではなく街の人々です。しかし、街の人々の撮影技術は高くありません。ですから、私は一般の人々のためのカメラのワークショップを開催して、誰もがレポーターになれるように、誰もが人生の大事件を撮影できるようにしたいと思っているのです。きっと映画史はどんどん変わっていくでしょう。