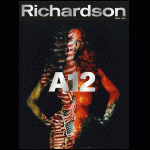「そこに漂うニオイとか “心のうごめき” を伝えたい」若葉竜也
Ryuya Wakaba
photography: yu inohara
interview & text: waka konohana
松居大悟監督作品『くれなずめ』が近日公開する。本作は、監督が主宰する劇団ゴジゲンによって2017年に上演された「くれなずめ」を劇場版としてセルフリブートした作品。成田凌や高良健吾、浜野謙太ら個性豊かな実力派俳優たちとともに存在感を発揮しているのが、ここ数年で話題の作品への出演が続く若葉竜也だ。幼少期から演技の仕事を始め紆余曲折な人生を送ってきた彼が、今思うこと、大切にしたいことについて素直な言葉で語ってくれた。
「そこに漂うニオイとか “心のうごめき” を伝えたい」若葉竜也
Portraits
1歳3ヶ月から大衆演劇の舞台に立ち、子供の頃はチビ玉三兄弟としてその名を馳せた役者・若葉竜也。その後もテレビや映画で多様な役を演じ続け、映画監督はもちろん、業界関係者にもファンが多い。とりわけ、2020年は山田篤宏監督の『AWAKE』、土井裕泰監督の『罪の声』、河瀨直美監督の『朝が来る』、石井裕也監督の『生きちゃった』といった芸術性の高い個性的な作品の出演が続き、今年に入ってからは今泉力哉監督の『あの頃。』と『街の上で』が続々と公開している。殺人犯から棋士、チンピラからオタクまでカメレオンぶりを発揮する彼の新作として、松居大悟監督による『くれなずめ』の公開が控えている。
着実にキャリアを築いてきたように見える彼だが、その裏では仕事が劇的に減った時期もあったという。また、これまで若葉自身がカメラを回し映像作品を創ってきたこと、映画祭で受賞歴のある映画監督だと知る人は意外に少ない。それはなぜなのか——。新作ともに自身のキャリアについて語ってもらった。

©2020「くれなずめ」製作委員会
―「くれなずめ」という言葉を初めて聞きました。
僕も初めて聞きました。日が暮れそうでなかなかくれないでいる状態をさす、「暮れなずむ」の造語だと思うんですけど、言い得て妙な内容の映画だと思います。生と死の曖昧な境界線、人生の曖昧さを、この空の色で松居監督は表現したかったんじゃないかな、と。どの作品もですが、今回は特に芝居の技術力とは違うところで言語化できないザラザラした心を体現化していかなきゃいけなかった。デビュー作品のような気持ちで挑みました。
―この映画はセリフで物語を説明していませんよね。
そもそも僕は、映画には多くの説明は必要ないと思っていたりします。例えば、写真や絵画は台詞や音楽すらない。その説明のない、たった一枚の写真や絵画をみた人達が自らの想像力を喚起しながら作品と向き合う。特に映画は1秒につき24コマという画で構成されているから、写真や絵画よりも情報量がずっと多い。そこに、保険という形で説明的なセリフを入れると、作り手にメッセージを押し付けられる気がしませんか?
―確かに。そうは言っても、説明的なナレーションやセリフが入っている映画が最近多い気がします。
松居監督は言葉で演出するというよりは、現場の温度を大切にしていて、役者を思い通りに動かそうとする人じゃないんですよね。もちろん、「こうしてほしい」という最低限の期待はあるとは思いますが、それだけじゃ満足しない人。とにかく、僕は “心にうごめく何か” を実直に体現化したいと思っていました。
―成田凌さん、高良健吾さん、浜野謙太さん、藤原季節さん、目次立樹さんと若葉さんが演じる高校の同級生6人が友人の結婚式で5年ぶりに再会する物語ということで、今をときめく役者さん達が集結した作品ですが、現場での雰囲気はどんな感じでしたか?
すごくアンバランスで面白かったですよ (笑)。皆さん、「上手にキャラクターを演じて器用に撮影を進めよう」、などという浅はかな役者は一人もいません。本当に個性の強い面子で。非常に面白いキャスティングでしたね。
―若葉さんはいつも脚本を読み込んだ後に、一旦、セリフを忘れて頭を空っぽにして撮影に臨むとか。
セリフを全部覚えて、記憶を曖昧にして、現場でまた構築していくというやり方をしています。というのも、お客さんは1800円を払って、映画館で明瞭なセリフやキレイに整った芝居を見て面白いと思うのか、と疑問を抱いています。それよりも、僕はそこに漂うニオイとか “心のうごめき” をお客さんに提示したいです。セリフを一旦忘れて芝居をするのは、僕が感じる “鮮度” をお客さんに伝えたいから。
―なるほど。若葉さんが演じた役、明石は一見チャラいオラオラ系のようですが、多面的でとても人間的でした。
登場人物をわかりやすくキャラクター化することに対してのアンチテーゼみたいなところはありますね (笑)。複雑で多面的なところに人間の面白さを僕は感じています。だから、そういう人間のリアリティを映画にも持ち込んで、お客さんの想像力を掻き立てたいと思っています。
―ところで若葉さんは、 yonigeのミュージックビデオ「往生際」のほかにも映画監督として活躍されていますね。2018年の『蝉時雨』は門真国際映画祭でグランプリと2019年の山形国際ムービーフェスティバル監督賞を受賞、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2020では『来夢来人』を発表されましたが、若葉さんが映画監督だということがあまり知られていないのは、どうしてでしょう?
役者として見られるよりも、自分の映画を見られるほうが緊張します。隠しているわけではないのですが、映画界には才能の豊かな若い監督がたくさんいて、バイトをしながら自分のお金と時間、心血のすべて注いで作っている。僕は俳優の名前だけで金を集めて、映画を監督したくないんです。やるなら、本気で監督を目指してる人達と、同じ土壌で同じだけ満身創痍になってフェアに戦いたい。新人監督はみんなやってますが、資金繰りも自分達ですし、自分達の足で撮影機材も借りに行きます、ロケの交渉も全部自分達。資金がなければ、レールや特機を自分達でトンカチもって木材買ってきて作った事もあります。そういう事を繰り返す事で、映画作りにおいて見えてなかった可能性を見つけられるんです。出会いもたくさんあります。新人監督がそうやって必死に作った作品をひっさげて、インディペンデントの映画祭に自ら参加費を払って参加するという、当たり前の事を僕もやっているだけです。今は、それをやらずに映画を監督する芸能人が多すぎるだけじゃないですかね。別に正解不正解ではないですが。
―若葉さんは、1歳で舞台をふみ、それ以降もテレビや映画に出演されてきましたが、役者としての転機は2016年の赤堀雅秋監督作『葛城事件』だったように思います。それ以来、作家性の高い監督作品への出演が続いていますね。このキャリアの転機はどのように訪れたのでしょうか?
オーディションでした。ある日突然、まったく仕事のない無名の俳優に来た大チャンスでした。ついに来た。と思いましたね。昔から、仕事もないのに、自分が面白いと思えない作品には参加してこなかったので…。側から見れば生意気だったかもしれませんが。
―事務所には反対されなかったのですか?
会社には迷惑をかけたかもしれませんが、きちんと自分の話を伝えて周りに納得してもらうことは、僕にとってはやるべきことでした。「まだ仕事を選べる立場にない」と思っている若い役者さんたちもいると思うけれど、僕は違うと思う。自分自身を自分でプロデュースしていかないと。誰かにおんぶに抱っこでは、この世界を生き残れない気がします。とはいえ、若気の至りもあり、極端すぎて (笑)。その拘りすぎた自己プロデュースのせいで当時は仕事が全くありませんでしたが (笑)。バイトの毎日でした。
―なるほど、自己プロデュースというのはマーケティング的なセルフブランディングというよりは、自己発見をして自己実現をしていく、ということですね。
そんな難しいことではなくて (笑)。青臭い言い方ですが、頭で考えるのではなく、自分が本当に心が動くものに素直に反応したいんです。本来、僕は月に20万円もあれば大丈夫なタイプなんです。大金を貰っても使い道に困って、くだらないことに使いそう (笑)。毎日粛々と仕事をして、映画を見て、友達とご飯を食べて、たまには旅行に行く生活で満足なんです。『くれなずめ』で、登場人物の一人がサラッと「生きるだけだろ」と呟くシーンがあって。僕は大好きな台詞なんです。凄く共感する。生きていると嫌なことなんてたくさんあるし、好きな仕事でもイライラすることもある。嫌いな人に愛想笑いをしなきゃいけない事だってある。辛くて辛くて、もう遠くに逃げてしまいたい日もある。それでも明日を生きるために、今日も頑張るしかないかなって思います。