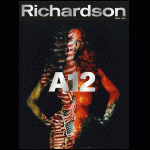孤独のその先をどう生きるかを見つめる、 監督・深田晃司の最新作『LOVE LIFE』
koji fukada
photography: utsumi
interview & text: tomoko ogawa
矢野顕子の同名楽曲をモチーフにした、『淵に立つ』、『本気のしるし』などを手がける深田晃司による監督最新作『LOVE LIFE』。新しい家族として、愛する夫、次郎(永山絢斗)と、元夫、パク(砂田アトム)の連れ子である息子と共に暮らす妙子(木村文乃)が、突然降りかかる悲しい出来事を通じて、自身の愛と人生に向き合う物語だ。人間の弱さ、狡さをまざまざ見せつけられ、それが観ている者を映す鏡になりながら、それでも誰かといる生活、そこにある豊かさを味わえる、力強い作品だ。楽曲に惚れ込んだ20代前半から、約18年の構想期間を経て完成させた本作への思いを、深田晃司監督が語ってくれた。
孤独のその先をどう生きるかを見つめる、 監督・深田晃司の最新作『LOVE LIFE』
Film

(C)2022 映画「LOVE LIFE」製作委員会&COMME DES CINEMAS
―深田さんがこの映画のインスピレーション源となった矢野顕子さんの楽曲「LOVE LIFE」を初めて聴いたのは、いつ頃だったのでしょうか?
約20年前の、20歳頃ですね。聴いて、すごく好きになりました。
―そのときに、どんな解釈をされたんでしょうか?
矢野顕子さんの歌って、繰り返し何度か聴いているうちに、あれ、もしかしたらこういうことなんじゃないか?って思うことが多くて。例えば、「ラーメン食べたい」という曲がありますが、 タイトル通り、ラーメンの話をしているんだけれど、中盤、「友達になれたらいいのに」という気持ちが出てくる。最初は、片思いの相手とせめて友達になれたら、という内容として聴いていたら、これってもしかしたら別れた男女がせめて友達に戻れたらいいのに、もう友達になることもできないという歌なんじゃないかと思ったときに、鳥肌が立ったんです。これも自分の勝手な解釈ですが、「LOVE LIFE」にも「どんなに離れていても愛することはできる」という歌詞がありまして、初めは男女の距離感を想像していたけれど、何度か聴いているうちに、 例えば、子どもと親の歌かもしれないとか、死別した大切な人への歌かもしれないとか、色んな解釈ができるなと思って、そこから連想ゲームみたいに物語が膨らんでいったんです。
―約20年の間に、物語はどのようにかたちになっていったのでしょうか?
夫婦のもとに悲しい出来事が起きた後に、 元夫が帰ってきて、三角関係に陥る、というプロットとラストカットだけは決まっていましたが、その間が全く思い浮かばなかった。脚本を書き始めた2015年ぐらいから、ようやくなんとか考え出して埋めていった感じでした。元々は、ある意味もっとシンプルで、明快に主人公が一人で自立していく話だったのですが、脚本を書いていく途中で、だんだん変わっていったんです。自立って、わかりやすいテーマであり、アクションなんですが、私たちの生の抱える問題の本質というのは、自立できるかできないかではなく、結局、自分自身はどうしたって一人である、孤独であるということを理解した上で、それでも誰かと生きていかなくちゃいけないことだと思って。それが、まあ、生きることの難しさと面白さみたいなものかなと。
―その月日を経て、自立や孤独に対する価値観が変わっていったことが影響しているんですかね?
そんなに意識はしていないですし、結果的にそうなったんですけど、変わっていったのかもしれないですね。毎回毎回、孤独を描くことを自分なりに試みてきたと思っていて、妙子の自立を描いたとしても、それは結局は孤独と隣り合わせのものとして描くことになるんですが、製作中にコロナの時代になったことも影響はしているかもしれません。「離れていても愛することはできる」という歌の歌詞が、ソーシャルディスタンスに始まり、人と人の距離が具体的に意識されるようになった今、また新たな意味を持ってきたと感じました。だからこそ隣にいる誰かとどう向き合うのかというところの入り口まで描けないかなと考えながら、ラストシーンができていきました。

(C)2022 映画「LOVE LIFE」製作委員会&COMME DES CINEMAS
―元夫のパクがろう者であるという設定は、深田さんが東京国際ろう映画祭のワークショップに参加された経験から生まれたそうですね。そこで手話という言語表現について、改めて思うところがあったのでしょうか?
今から思えば当たり前のことですが、手話は補助器のようなものではなく、日本語、フランス語、英語と同じようにひとつの言語なんだと理解できたんです。言語によって色んな特性はあると思いますけど、特に手話というのは、非常に映像的な三次元の言語である。空間の言語であると感じました。
―表情も豊かですよね。
そうですよね。手話にとって表情も重要な文法の一つであるということを自分もようやく知ることができました。パクがろう者という設定は元々なかったんですが、妙子と元夫が共通の言語を話して、今の夫である二郎にはわからないということにすると、その三角関係に緊張感を加えることができて、いろんなパワーバランスが生まれてくるんじゃないかなと思ったんです。じゃあ、その言語は何かと考えたときに、東京国際ろう映画祭のワークショップの講師を引き受け初めてろう者の方々ときちんと接することになり、手話にしようと。むしろ、なぜ、今までの映画にはろう者が登場しなかったんだろうという問い、それを逃げずに考えなくちゃいけないと思いました。例えば、聴者の登場人物が出ていることに関して、「なぜこの役は聴者なんですか?」という質問は出ませんが、ろう者が出ると、「なぜこの役はろう者なんだろう?」と疑問を持たれてしまう。そこに理由を求めてしまう。
―マイノリティとして特別視されてしまう。
今回の作品は当たり前のように、ろう者がラブロマンス、メロドラマの三角関係の一画を背負っていること、それこそが大事なことだと思っています。もちろん、社会問題を正面から描いた作品もあるべきで、ろう者の方が今も抱えている社会的な問題や差別の問題は間違いなくあるんだけれど、ろう者の役が出てくる度にそれらのテーマを背負わされるべきではないと思います。そういった社会的な問題をマイノリティの役が常に背負わされてしまうと、役の幅も広がっていかなくなってしまうので。
―妙子とパクとの言語、妙子と二郎の言語があるという見え方で、そういうことは現実でもあるので、疑問は持たなかったですけどね。
そう観てもらえたら嬉しいです。この三角関係においては、普段はマジョリティである二郎が、手話がわからないことでマイノリティの立場になるというところが演出のポイントにはなっています。あとは、自分自身が初めて映画で扱う言語だったので、新鮮で色々とアイディアが膨らみました。鏡越しに手話で話しかけたり、窓ガラス越しに会話できるとか。
ーそういったシーンは、パクを演じた、ろう者の砂田アトムさんと話し合いながらつくっていったんですか?
シーンによりますが、聴者の視点での勝手な思い込みになっていないか、砂田さんにはその都度その都度、確認させてもらいました。鏡越しに手話で会話をしたいというアイディアも、普段することがあると砂田さんが仰ってくれたので、取り入れました。ありえないことを演出でやらされてるようなことにはならないよう、確認を取りながら進めていきました。そういった意味でも、砂田さんにパクを演じてもらえて本当によかったなと思っています。

(C)2022 映画「LOVE LIFE」製作委員会&COMME DES CINEMAS
ーこの映画でパクはマイノリティとしての社会問題を一人で背負ってはいませんが、作品の中では現実に起こっているさまざまな社会問題が、目を逸らすことなく映し出されているなと感じました。意図的なものではないと思いますが、どういう意識で社会問題について扱っているのかなと。
結果的にですね。ただ逆に言うと、そういった要素が作品の中に入ってくることを厭わないという考えではあります。普通に生きていれば、誰だって何かしら問題抱えていると思いますし、誰かに対してカメラを向ければ、生きる上での問題が自然と入ってくるものであり、それらをわざわざ排除することはしないという姿勢ではあります。むしろそれは特別なことじゃなくて、海外の映画を観ていても、普通の若者の青春ドラマであったとしても、人種問題や貧困の問題が当たり前のように日常として描かれていますし、いわゆる「社会問題」は、普段、私たちが生きている道の上にも常にあるものなので、そういった問題を抱えている世界に自然と登場人物が立っているという意識は、忘れないようにしたいと思っています。
ー今回、木村文乃さん、永山絢斗さんのキャスティングは、どうやって進めていったんですか?
木村さん、永山さんはキャスティングの方から候補を出してもらって、まずは宣材写真から直感的に「この人だ」と。それで実際にお会いして、決めていきました。木村さんはその芯の強さが脚本の妙子を更新してくれそうに思えました。二郎役の永山さんは、普段からボソボソ小さい声で喋る方なので、その感じがすごい二郎だなと(笑)。
ー三角関係の3人以外の俳優さんも本当に説得力があるというか、実際に、この世界で生きている人物だと思える方ばかりでしたが、オーディションで配役を決められたそうですね。
これほどの数の役をオーディションで決めることができた機会は、自分の作品でもなかなかありませんでした。そもそも日本には、オーディション文化があまり根付いていないという前提があり、特にキャリアを積まれた俳優さんは、オーディションから縁遠くなってしまう傾向があると思っています。でも、オーディションをやった方が、より役と合う俳優を探すことができるし、新たな出会いがある。過去作は過去作でしかないので、過去作だけ観ていたら絶対お願いしなかったかもしれない人でも、オーディションでこんなにいい俳優さんなんだと気づけることもあります。若い役者さんにとっても、オーディション文化が根付いてないことからくる弊害がたくさんあるんじゃないかと。やっぱり、機会ができるだけ平等に開かれていることはすごく重要で、開かれてない状況が、実は最近のハラスメントの問題ともつながっていくんですよね。
ー昨今、ハラスメント騒動でワークショップが問題視されていますね。
本来であれば、もちろん例外はあったとしても、俳優さんと監督やプロデューサー、あるいは役と俳優の出会いの場は、オーディションであるべきだと思っています。選ばれる立場と選ぶ立場があって、選ぶ側はどうしたって強い権力を持っていることを自覚しなくてはいけない。だからオーディションの場で演技を見て、そこで選ぶ。純粋にオーディションが出会いの場であるといいけれど、そういったシステムが機能していないと、結局、若い俳優にとって役を掴んだり、 キャスティングにつながる場というのが、例えば、ワークショップや飲み会になってしまう。そのことが、監督やプロデューサーに不当な権力を与えてしまっていたと思います。もう一つ、キャリアを積んだ俳優さんにとっても、オーディション文化がないと、主体的に役を選ぶということが難しくなる。やっぱり、待ちの姿勢になってしまう。日本映画界は Robert Downey Jr. (ロバート・ダウニー・ジュニア) でさえオーディションで『アイアンマン』(08)の主役を得たということを、本当に重く受け止めなきゃいけなくて。
ー確かに、海外はオーディションシステムが整っている印象があります。
オーディションがあると、キャリアを積んだ俳優さんも、この監督の作品に出てみたいと主体的に選択することができるようになっていくんじゃないかなと。オーディションがないと、キャスティングはよりギャンブル性が強くなります。俳優さんがたまたま役に合えばいいけれど、合わなかったときに結局、作品だけではなく、俳優さんも損をすることになってしまうんです 。合わない役を演じさせられると、やっぱり下手に見えてしまう。そもそも役に合っていないものを合わせていくことは、大変なわりに実りが少なく、俳優さんにとってリスクでしかないので。自分は、俳優さんを最前線で闘う兵士みたいな存在だと思っていて、最初の銃弾を浴びるのも、傷つくのも俳優さんなんですよね。本当にいろんな意味で、オーディション文化は、もうちょっと普及すべきだと考えています。
ー本作はフランスからの助成金を得て制作され、Sylvie Lager (シルビー・ラジェール) さんと一緒に編集もされています。フランスの助成金システムというメリットももちろん大きいと思いますが、他国のスタッフと仕事をすることは深田さんにどんな影響をもたらしていますか?
まずお金の問題はすごく大きくて、やっぱりこれは外せないんですよね。なぜフランスなのかというと、CNC(国立映画映像センター)が外国の作品にも助成金を出してくれているからです。日本で考えると、文化庁が外国映画に助成金を出してるようなものなので、それがどれだけすごいことかがわかりますよね。フランスのスタッフと仕事をするようになって、単純に自分の文化圏とは違うところで育ってきたスタッフそれぞれの感性が入ってくることが面白いなと。それこそ、映画に他者性が生まれていく。どっちがいい悪いということではないんですが、印象として、日本の技術スタッフの皆さんは、「監督はどうしたいんですか?」と聞いてくれて、それをものすごく高い技術力で実現してくれる方が多い。フランスで何本か仕上げをした印象として、もちろん監督に配慮はあるんですが、彼らはそれぞれが独立したアーティストであるという考え方なので、作品をよくにするために、「こうした方がいいですよ」という意見をどんどん出してくれる。その面白さはすごくありますね。
ー演劇から映画に来るというルートの方はまあまあいると思うのですが、深田さんは映画を撮っているところから、2005年に劇団「青年団」の演出部に入団されています。平田オリザさんのもとで学ぶきっかけとなった出来事があったのでしょうか?
元々、10代の頃は演劇嫌いだったんです。本当に映画オタク、シネフィルだったので、頭でっかちなんですけど、映画以外のジャンルを見下すというよくない傾向がありまして……。実際、20歳の頃に学生演劇を観てみたりもしましたが、俳優が濃い芝居で叫び始めるにつれて、俳優を直視するのが辛くなってきて、もう舞台の隅の小道具を見つめながら終わるのを待つみたいな感じで(笑)。その頃、たまたま『椅子』(02)という映画に出てくれた井上三奈子さんという俳優さんが、青年団に入ったというので観に行ったら、そのスタイルに衝撃を受けたんです。
ーどういったところが衝撃だったんですか?
それまで観てきた演劇とは全然違って、誰も叫ばないし、日常で交わされているような会話が続き、特に感動的な盛り上がりもなく淡々と終わるという内容だったんですね。まず、特にすごいなと思ったのは、日常会話を続けているだけで、誰として本音らしいことを言わないのに、微妙な関係性の中からその人たちが今何を考えていて、どういった気持ちなのかを観ている人が想像できるようにつくられていることでした。でも考えてみたら、自分が好きだった Éric Rohmer (エリック・ロメール) だったり、成瀬巳喜男監督だったりも、それをやっていると思った。それで、ハマってしまって、とにかく青年団を上辺だけ真似した映画を自主で撮ってみたりもしましたが、上手くいかなくて。これはもう中に入ってみないとわからないなと。なので、演劇をつくりたくて入ったというよりも、映画をつくる上での留学のような気持ちで、現代口語演劇と Éric Rohmer を足して二で割れば新しいことができるんじゃないか、という妄想から入ったんですよね。
ーよりいい映画にするために演劇という国に留学したみたいなことだったんですね。ちなみに、『LOVE LIFE』は第79回ヴェネツィア映画祭のコンペティション部門や、第47回トロント国際映画祭のコンテンポラリー・ワールド・シネマ部門に選出されていますが、深田さんは映画祭でノミネートされることについてどんなふうに考えていますか?
まず、賞というのは運とタイミングであって、受賞したか、していないかで映画の面白さが決まるとは全く思わないです。ただ、作品をつくり続けるための力、後押しにはなりますね。そして、決して否定されるべきものではないかなと。そもそも世界三大映画祭(ヴェネツィア国際映画祭、カンヌ国際映画祭、ベルリン国際映画祭)がなぜ立ち上がったかといえば、ハリウッド的なグローバリズムへのカウンターという側面があって、映画は特に、とにかくお金がかかる表現であることも関係してます。長編映画を1本つくれば、数千万円から1億、2億、数億とかかってしまう。制作費を回収するためには相応にヒットさせなくちゃいけないから、市場の原理の影響が強くなります。そうすると、どうしても娯楽性の高い映画は市場で強くて、それはそれで大切なことですが、一方で商業性は低いかもしれないけれど多様性を支える表現みたいな作品はどんどん払拭されていってしまう。そもそも、映画で話されている言語が日本語である、韓国語である、フランス語である、という時点で英語と比べれば少数派、マイノリティなんです。
ー世界共通語は英語ですもんね。
はい。なので、アメリカ映画は言語が英語であるということはそれだけでものすごく強みであって、日本映画はもし国内市場だけではなく海外にも出ていくとするなら、マイノリティとしてどう生き抜いていくかを考えないといけない。映画祭は、市場原理とは別の評価軸でコンペティションをし、賞を与えて、小さいながら市場に売り出していく役割を担っています。それが何十年も経って権威化していく、というのはまた別の問題だと思っています。なので、ノミネートされるということは、まあ、ありがたい話ですね。