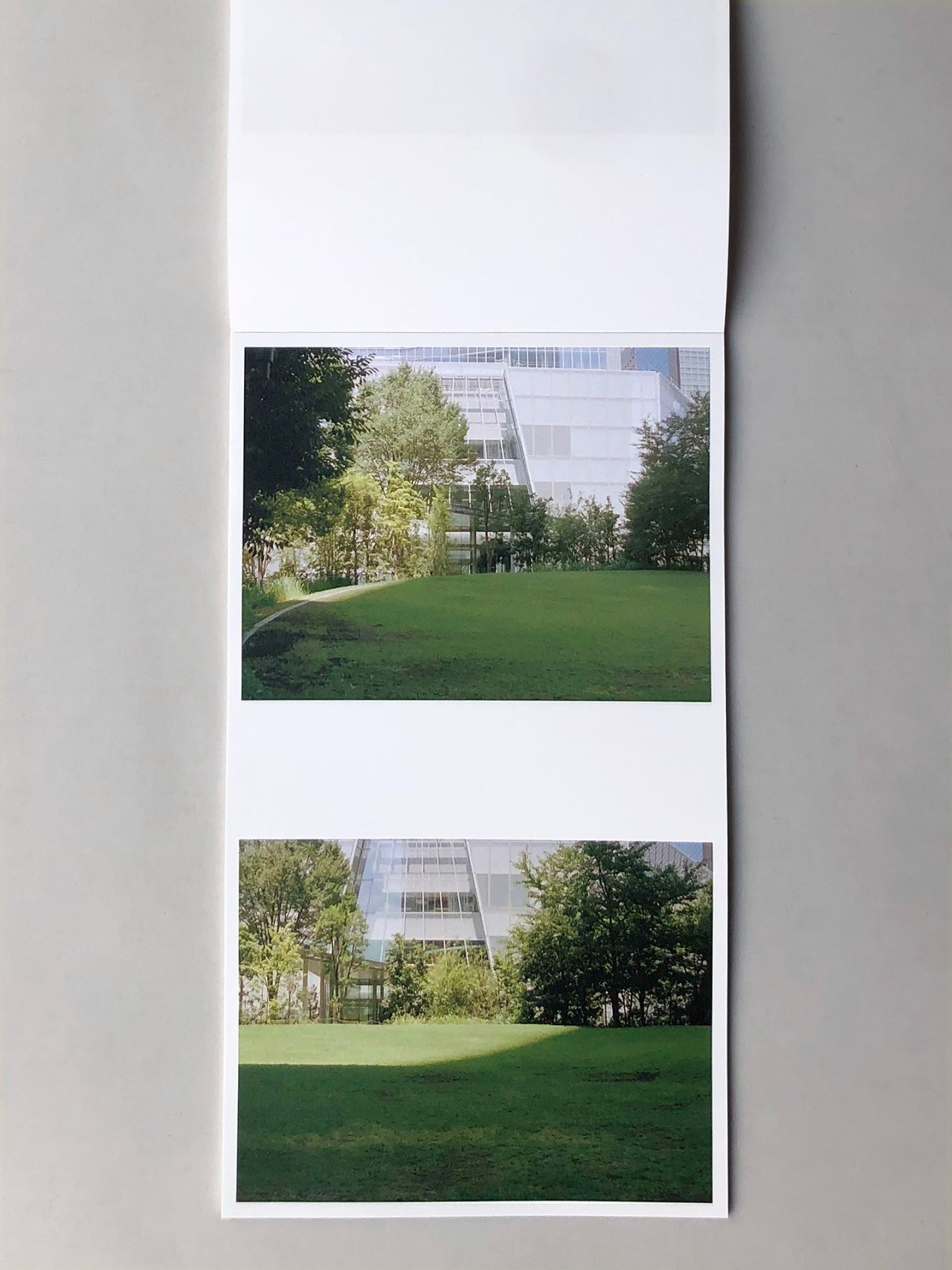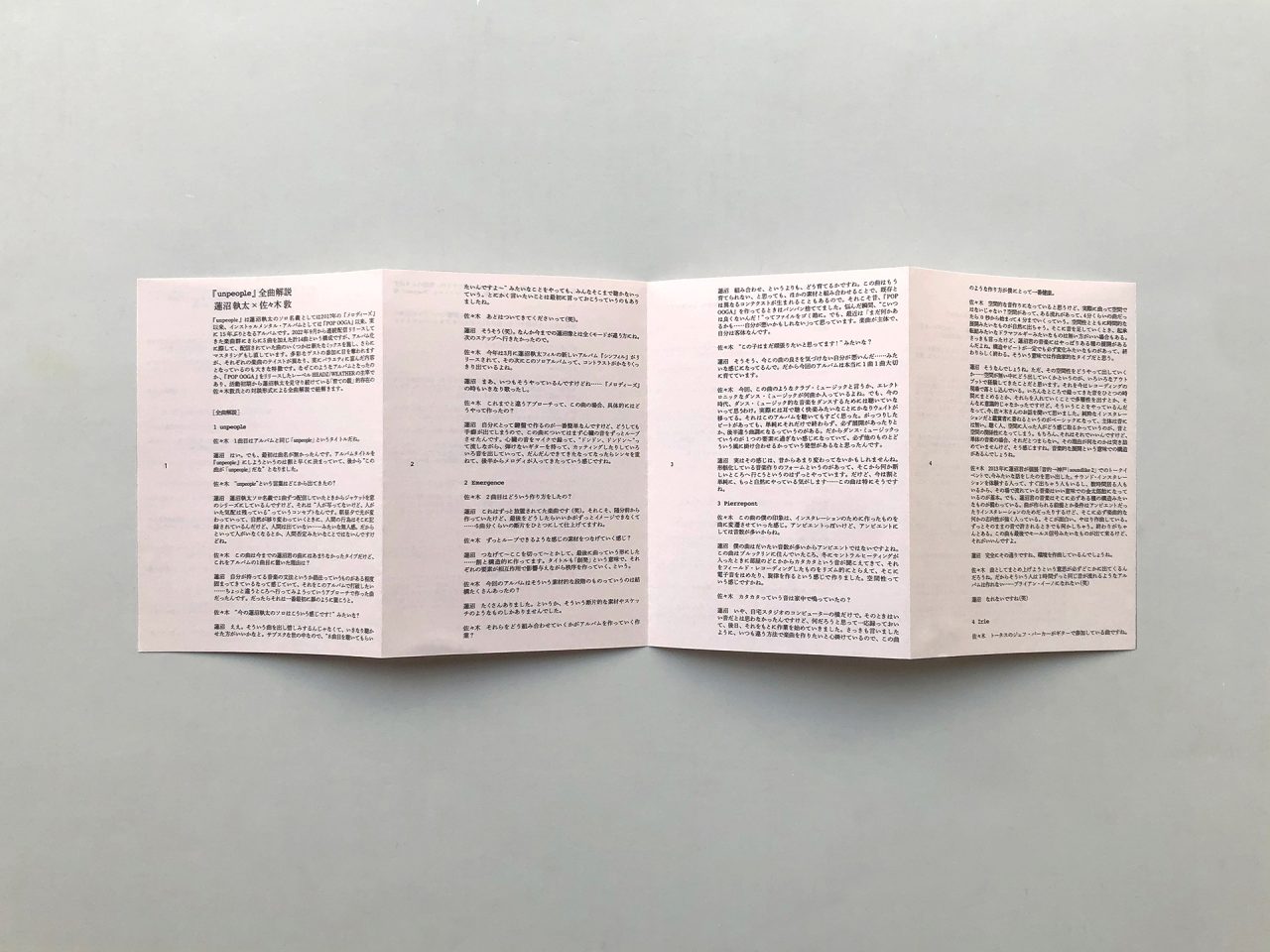「僕の存在すらいらないんじゃないか」音楽家・蓮沼執太の現在の境地
shuta hasunuma
artist photography: riku ikeya
products & venue photography: so hirose
interview & text: chikei hara
10月6日にアルバム「unpeople」を発表した音楽家の蓮沼執太。2022年9月より配信シングルとして発表されてきたソロ・プロジェクトの集大成となるこのアルバムの楽曲には、Jeff Parker (ジェフ・パーカー)、小山田圭吾 (Cornelius)、灰野敬二、KOM_I など、その他大勢のゲスト・コラボレーターやエンジニアが参加している。「純粋に自分のための音楽」として作り上げられた本作には、5年間もの制作期間を要したという。コロナパンデミック前後の時間の流れや、ブルックリンから日本に活動拠点を移した蓮沼の日常の変化も感じ取れる。
人間の不在を想起させるタイトルがつけられたこのソロ・プロジェクトは、グラフィックデザイナー・田中せり、写真家・池谷陸と共に作り上げられ、10月1日まで恵比寿のアートブックショップ POST で同名の展示が開催された。タイポグラフィの主体が存在せず影のみで表された「unpeople」のロゴや、池谷によって写された窓の定点観測、写真に映る場所で蓮沼が記録したフォールドレコーディングの音楽など、どれも客体的な人の存在が浮かび上がる内容だった。
本プロジェクトに込めた想いやコロナ・パンデミック前後の心境の変化、他者という存在への向き合い方について蓮沼にオンラインインタビューで話を聞いた。
「僕の存在すらいらないんじゃないか」音楽家・蓮沼執太の現在の境地
Portraits
─アルバム「unpeople」は2022年の9月からリリースされた楽曲を中心にまとめられていますが、今作でご一緒されているグラフィックデザイナーの田中せりさん、写真家の池谷陸さんとは元々どのような関係でしたか?
僕自身はせりちゃんと陸くんとそれぞれで付き合いがありましたが、お互いは接点がなくて。今回のプロジェクトで二人は友達になった仲です。昨年の4月ごろにこのプロジェクト全体のデザインをせりちゃんにお願いして、アイディアを膨らませる中で、写真でビジュアルを作れたらいいと話していた時に、せりちゃんから陸くんがいいのではと提案してくれました。陸くんには、灰野敬二さんとのコラボレーション「う た」のキービジュアルを撮影してもらうなど、僕のプロフィールのポートレートも撮ってもらっていてお世話になっています。
─それぞれの曲に対して当てられているアートワークにはどのような繋がりがあるのでしょう?
今回のプロジェクトでは配信順の1〜3曲目という様な区切りでアートワークのシリーズをまとめていて三部作になっています。一日の中で同じ窓を異なる時間で写していて、窓の外の風景が変わっていく様子を一つのまとまりとして表しています。一般的に音楽を作る人はおそらく、最初にアルバムという形を見据えて組み上げていくプロセスを取るだろうけど、今回はまとまって曲を出すという感覚はなくて少しずつ積み重ねていく過程があったので、ゴールと呼ばれるイメージがあまりなくなんとなくこの形にした意図もありました。アルバムでの曲の順番もそうで、僕が選んだというより楽曲がそうさせたような気がしています。主体は僕じゃなくて曲にあるというくらいの意識を持っています。
─蓮沼さん自身この数年間、窓辺の風景を見ることが多かったですか?
2019年までニューヨークのブルックリンに住んでいて、現在はコロナ・パンデミックで東京に帰り引っ越した家に住んでいます。いまこうして喋っている目の前に大きな窓があって。コロナ禍は基本的に家にいることを要請されていたのでこの窓の前で過ごしていて、窓越しにずっと外を眺めながら時間の変化を大切にしていました。あと、基本的に僕は昼間を創作の時間にあてているので、夜間は全くやらないということも関係しています。普段ロジカルに考えている分、頭を空っぽにするのが好きなんですよね。
─「unpeople」は直訳すると人間の不在を表すことになりますが、このアルバムには孤独な雰囲気はなくてむしろ希望に近い肯定的な印象を受けました。このタイトルにはどういう意味合いを込められていますか?
people を否定しているので、人間の否定として捉えられがちだけど、実はそうじゃなくて。2018年に蓮沼執太フィルから出したアルバムに「ANTHROPOCENE」というタイトルをつけました。これは今では誰でも知っている Paul Crutzen (パウル・クルッツェン) の提唱した人新世の標語ですが、人間活動が地球に影響を与えすぎているのではないかという考えから、我々もモノとの関係や人間同士の関係を見つめ直すきっかけを投げかけるニュアンスでつけました。そのあと2019〜2022年にかけて、コロナ禍で社会が閉ざされた状況になると同時に、以前よりも資本主義の流れも強烈になり自分たちの生活への刺激が強まってしまいました。戦争が続いているという事実も大きく、自分たちの生活がより厳しくなっていることを感じています。身近な危機が差し迫ったもっと大変な環境もあるので、日本はこれでも幸せだとは思いますが。「unpeople」というタイトルには、日常が待ったなしの状況であることを考え直したい想いを持たせています。具体的な人間否定は一切ないですが、既存に生きている人たちがもう少し意識的に生きないと、我々のような経済圏にいる人たちはグローバルサウス的な立ち位置の人々に影響を及ぼすことは明らかな状況でもありますし。別に全部否定しているわけではなく、肯定したいからこそつけている側面もあって。この5年間の間、少しずつやってきたことを出すという理由もあって、このようなタイトルになりました。
─既に公開されている楽曲の MV では、プログラマー/アーティストの ucnv さんや映像作家の清水花さんが製作された映像が当てられていますが、そこではどのようなイメージを共有されましたか。
ucnv さんは、12年前に「ミュージック・トゥデイ・アサヒ」というイベントでビジュアルパフォーマンスのような VJ をしてもらったり、プライベートでも親交があって割と長くお付き合いさせて頂いていて、v兄さんって呼んでます(笑)。彼はグリッチの専門家で研究もされている方で、近年 sony park mini や TALION GALLERY で発表されていた複数ある事象の関係性をずらしていく作品の傾向を面白く拝見していました。彼には「Emergence」という曲の MV をお願いしていて、創発を意味するタイトルの様に、独立した複数のエレメントを一緒にすることで、違った動きを組織的に展開して運動体を作る内容になっています。楽曲自体も5曲分くらいの素材を繋ぎ合わせていて土台も違ければ素材もシャッフルしながら作っていった曲だったので、その感じもv兄さんの手法と近い雰囲気があるのではないかと思いました。何かと何かが写っていて、単体だと見えてこないけど、二つが並んだ関係性の中で違うコンテキストが作られる可能性を想像して MV 制作をお願いしました。
清水花さんは陸くんが今回のプロジェクトのコンセプトやこの音楽に合うのではないかと紹介してくれました。unpeople なので、基本的に人が写っていない映像をショートフィルムとしてまとめています。花ちゃんがこれまで撮りためていた素材を見ながら、イメージを共有する中で、彼女からの提案で新たに撮影してもらったカットも交ぜながら、断片的な風景を公開していきました。
─コラボレーターの人間性に引っ張られながら、作品を作り上げることを楽しみながら制作されていそうですね。なんというかそれぞれの人の求心力を大事にしているというか。
コラボレーションには何通りかのプロセスがあると思っていて、僕の場合はこれをやってくれと指示するわけではなくて、僕はこういうことを作っていてなんか面白くできますかというスタンスで今回のアルバムではコラボレーションさせてもらっています。音だけではなくビジュアルもそうで、せりちゃんにも曲のデモとイメージを渡して、こうしたら面白くなるんじゃないかというフィードバックをいただきながら製作しました。信頼してリスペクトしている人たちとの共同作業の中で、僕自身が驚きたいというイメージを持っています。人によって、やることによってコラボレーションの形は変わるけど基本的に僕の作ったものを感じてもらって対話する。そういったコミュニケーションが作品を通して生まれること自体が好きです。
─蓮沼執太フィルでの蓮沼さんの立ち位置は何役ですか?
何役なんだろうな(笑)。年齢も楽器もバラバラで幅広いので全然まとまりがなくて、学級委員くらいの感じかもしれないですね。とはいえ僕の名前が入っているし、作曲やアレンジも僕がやっているのでなるべくみんなと同じ立ち位置にいることは常に心がけていています。リーダーというよりは、一番みんなの音を聞いている人かなと。演奏する音もそうですけど、アンサンブルを構築していると、それぞれの人の機嫌がいい時と悪い時に気づきます。みなさんが生きていてもそうだと思うけど、久しぶりに会った人の声に元気がなかったらよく話を聞くようにしています。全然音楽的ではなくて普通の人間関係の延長だとおもう。そこに特別なものはないです。表向きは音楽をやっている集団ですけど、背後にはスタッフやビジュアルを作る人もいるのでなるべく自分のプロジェクトに関わる人にはそうしたいと気にしています。

─特定のペルソナを限定しないことはいまの蓮沼さんの活動の全体像からも見て取れます。それぞれの領域での活動に壁を一つも感じさせない程シームレスである印象があります。
それは形式という話にもつながると思います。もちろん展覧会を作るのと、レコーディング作品をつくる時は体や頭の使い方も異なります。けど別に特定の業界や個人に向けて届けたいわけでもないからこそ、聞く人や見る人というのはいろいろであってほしいと思っています。そこに壁がないと言ってもらえるのは嬉しいですが、クリエイションが絶え間無く続いているということには、そういうシームレスであることへの想いもあります。自分に嘘をつかないクリエイションをしていきたいです。僕の場合はそんなしっかりしていないので、昨日と明日で僕自身が異なりますし、日々生活とともに変わってしまいます。人間はとても自然だし人工物ではないので、絶えず変化していくものだと思います。じゃあ人間を肯定しているじゃんと言われてしまいそうな話ですけど(笑)。
─そうした変化に対する想いは昔から変わらないですか?
ブルックリンにいた頃に、人はもっと自由にいろんなことをやってもいいと感じました。そこで出会った友達を見ていると、バスの運転手や夜は DJ をする人、朝働いて昼からアトリエに行くアーティスト、美術館のインストーラーしながら作家をする人など、働き方や考え方も様々でした。それを多様性と言ってしまうと少し胡散臭いですが、色んな価値観を肯定することができていろんな生き方があっていいんじゃないかと思います。僕自身が音楽のジャンルや形式を使って、その中で自分が音楽で何をやるかを考えるのが好きなので今のような活動になっています。これはなんで音楽をやっているかという話にもなりますが、音楽に関しては聞かれないと音楽にならないと感じています。人に聞いてもらって空間に響くことで初めてつながっていく行為ですし、そう言った意味では聞き手を無視して自分がやりたいことだけをしていけばいいとも思わないです。
─10月1日まで POST で展覧会を開催されていたように、展示や作品という形態でも発表されることが多いですよね。
POST の展覧会では些細なことに焦点を当てて、現在性を出すことにこだわってやりました。写真というメディアはどうしても過去を写すものなので、会場にあった窓に目を向けたり、蛇口から水を垂らし続けたりすることで今というものを見せました。過去に行ったアートプロジェクトでも人を介さないと作品にならないというものも結構あります。2020年にニューヨークのトンプキンス・スクエアで1日限りの展示会「Someone’s public and private / Something’s public and private」を開催しました。自分の体重分の水をワインボトルに詰めて、訪れた人に動かしてもらうインストラクションのプロジェクトで、あれも僕は条件だけを設定して、枠組みのみ作った作品です。人がこないと何も変化しないので作品にもならないですし。音楽も一緒で人に聞かれないとただの音になってしまうので、人が聞いてから音楽化されるのだと思います。そういう時間や空間の中にあって人がいないと成立しないところに自分の作品の一つの特徴がある気がします。
─「unpeople」というタイトルが不在を指すように、以前から蓮沼さんの作品には「不在」がテーマであるように捉えられるシリーズがいくつかあったように思います。例えば、昨年末に恵比寿ザ・ガーデンホールで開催された「消憶|きおく|Vanish, Memoria」や、先ほど話に上がった作品「Someone’s public and private / Something’s public and private」、2014年の個展「無焦点」などがそうです。今日、不在という言葉を使うことにどういう想いや心境の変化があったのでしょうか?
いま仰ってもらって、不在という言葉自体がキーワードなんだなと思いました。今日的な解釈でいうと、存在がなくても残っているものや人が何かを再生することで、ある種立ち上がってくるような感覚を信じています。何かが起こることで浮かび上がってくる要素は必ずあって、そこに実在は必要ないと思っています。例えば、河原温の「Date Painting」ってあるじゃないですか。日付が描かれることで、河原がその時間には存在していたということを認識することができますよね。そこに河原温という実在はないけれど、いたという証明にはなっている。それと同様に音楽があって、亡くなっている人が書いた曲も再生すればその人が立ち上がってくることもあると思っています。芸術というものには、人がいなくなった途端にレコードや作品から人を復活させる、実在にできる力もあります。だけどそれは不在でもあるわけなので、そういうニュアンスの表れを今は感じています。「無焦点」をやっていた頃はもう少し論理的だったかもしれないですが、今は僕の存在すらいらないんじゃないかというレベルまで考えられるようになりました。あんまりこちらが主体にならないというか、自分以外の他者に主体を譲ることは僕がやっていきたいことでもあると思います。
─9月11日に40歳の誕生日を迎えられたとのことですが、この先の展開や抱負をお聞きできたら嬉しいです。
まず40代になった実感もそんなにないです。今回「unpeople」を作るにあたって、少しずつやっていても5年ほどの年月をかけないと出てこないことがまずわかりました。今までも自分をできる限りを信じてきたけど、更にやりたいことに目を向けていけたらと思います。それに人間は生きる時間が有限ですし。他者とやることが嫌だというわけではなく、人のために何かをやることももちろん大切だけど、自分のために行うことにも力を注いでいければと思います。例えば展覧会だとキュレーションがあって、場所があって自分たちの作品がある。ある種の協働関係を作っていく要素もあるしそこでの魅力もあるわけじゃないですか。普段ライブパフォーマンスや蓮沼執太フィル、u-zhaan (ユザーン) などコラボレーターとのプロジェクトもやっていても、それぞれ現場の雰囲気が異なり、そこで違う顔の人やコンテクストと触れる面白さを感じてきました。それはそれで新しい発見もあって楽しんでいる側面もありますが、他者との共同作業を経て、じゃあソロでの展開はどうしようか?とも思うので、これまで通り柔軟にやりながら考えていきたいです。