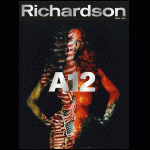金工家・中村友美が生み出す、道具を飛び越え、心地いい空間を完成させるオブジェ
yumi nakamura
photography: chikashi suzuki
interview & text: tomoko ogawa
“鍛金”と呼ばれる技法を用い、金属の一枚の板を、火にかけ、叩き、打ち出しながら、かたちを造り出している金工家・中村友美。新世代コンセプチュアル・アートの旗手として注目されるRyan Gander(ライアン・ガンダー)とのコラボレーションや、 NOIR KEI NINOMIYA 2025年春夏コレクションでは、銅製のヘッドピースを制作したことも記憶に新しい。国内外で個展を開催し、アートと工芸の交差点で表現の可能性を広げる中村。2024年、アトリエを奈良から東京に移したという彼女に、金工家としての歩みと現在地について聞いた。
金工家・中村友美が生み出す、道具を飛び越え、心地いい空間を完成させるオブジェ
Art
—中村さんは元々は武蔵野美術大学でインテリアデザインを学ばれていたということで、金工に出合うのは就職した後だったそうですが、学生の頃から工芸デザインには興味があったんですか?
高校生のときに、美術の教育実習生の先生に美大の存在を教えてもらったのがきっかけで、美術系の予備校に通い、武蔵美に入学しましたが、子どもの頃から空間をつくることは好きでした。自分の部屋の模様替えも好きでやっていましたし、学ぶならインテリアデザインだろうとは思っていて。私が通っていた武蔵美の工芸工業デザイン学科は、工芸とインテリアデザインとプロダクトデザインがひとつになっている学科で、割と珍しい学科だったんです。ただ、在学中は一切金工はやっていなくて、全く興味もありませんでした。当時は、自分はずっとデザインと建築、インテリアの仕事をやっていくんだろうと思っていました。
—それで、企業に就職したんですね。
そうですね。愛知県常滑市にある住宅設備機器の会社に就職し、デザインセンターという未来の商品をつくる部署に配属されて、デザインのプロトタイプなどをつくっていました。でも、商品開発は分業なので、自分が一体何をやってるかがわからなくなってしまい、早々に悩んでいました。そんなときに、名古屋の「gallery feel art zero」(現在の「Gallery Nao Masaki」)で、金工家の展示を見に行く機会があって、そこで衝撃が走ったんです。その方は、徳川家代々の御用鐔師(刀のつば)をつくっていた家系の3代目で、刀が使われなくなった明治以降はお茶道具を家業としてつくられている方なんですね。その傍ら、作家活動もされていて、とても自由な造形でオブジェのような美しい作品を生み出していらっしゃいました。メソポタミア文明などの古い時代ものから影響を受けていらして、1枚の金属の板からどうやってこんなモダンなものがつくれるのだろう?と思いましたし、同時に時代を超えた美しさを感じたんですよね。
—その金工家との出会いをきっかけに、金工の道に進まれたわけですね。
作家というものは、今日考えたものを明日にはものとして形にできるというか、頭と手が直結しているじゃないですか。私は会社勤めで2、3年先の商品開発をしていて。その時間感覚の違いに愕然としました。そして、暮らすことと仕事をすることが1つになっている。つくり手の方と実際出会って、生きることと糧を得ることが暮らしの延長にある生き方に強烈に憧れたんです。金工をやりたいという思いを捨てきれず、3年勤めていた会社を辞めて、無謀にもこの道に飛び込んでしまいました。そこから関東に戻り、武蔵美の同級生に相談して、教えてもらった金工の教室に通い始めました。でも生活していかなくてはならないので、インテリアデザインの事務所で働きながら休みの日に教室に通い鍛金の基礎を学んでいました。そんな中、最初につくったのがやかんです。その金工家のつくるやかんがほしかったのですが、高くて当時は買えなかったので、使いたいやかんを自分でつくろうと思ってつくったものがスタンダードとなって、今もずっとつくり続けています。だから、やかんが全ての始まりなんです。
—そこから奈良で活動をされていたんですか?
2012年に関西に行くことなり、住む場所としては、なんとなく奈良がよさそうだなと思ったんです。ダメだったらインテリアデザインの仕事に戻ろうくらいの気持ちで、生きていけるかわからないけど、とにかくやってみようと一からやり始めて。20代最後の年でもあったので、最後の悪あがきでもあったと思います。でも、わりとすぐに「使いたい」と言ってくださるところが出てきて、案外やっていけるかもしれないと思いました。3年半くらいは、週に3日奈良のギャラリーで展示会の企画スタッフとして働きながら作家活動をしていたのですが、だんだんと制作の時間が取れなくなってしまい、2016年には作家として独立しました。そこから制作時間ができると同時に、仕事も徐々に増えていって、今は作家1本でやっています。最初に「私が金工やりたいんだよね」と言ったときは、デザインをやっている周りの友達はみんなざわついて、きょとんとしていたんですけどね(笑)。何かを始める時って、誰からも期待されるものでもなく、ただ自分だけがそれを信じている、そういうものなんだと思います。
—中村さんの作品はオブジェとしての美しさも際立っていますが、ご自身の作品を工芸、美術のどちらとして捉えているのか、それとも、その二つの境界線は特に意識していないのかを聞きたいです。
元々デザインをやっていたので、どちらかといえば、やかんも湯を沸かすオブジェだと思っています。まさにそういうタイトルで展示会をしたことがあるんですけど。だから、単体というより、やかんというものの連なりや集団体で空間をつくっているという認識ですね。空間、インテリアデザインをやっていた頃は、床、壁、天井や、家具の扉の隙間の高さやピッチを揃えていくような、ミリ単位で全部を設計する事務所だったんですね。そこで学んだのは、そういう細かいディティールの積み重ねがインテリアの空気感をつくるものだということ。心地いい空間というものは、それに気がつかないくらいさり気ないものであって、何がいいのかは一見わからなかったりするんだけれど、実は綿密に設計されているんですよね。それを、やかんの中で実現しようとしているという感覚です。
—中村さんがつくっていきたいものを言葉にするとしたら?
造形としてはものすごくシンプルなんだけど、普遍的なものでありたい、空間に置かれたときに美しいものでありたいと思ってつくっています。建築を見に行くのが好きで、建築家がどういう考えでつくっているのかという視点や思考にインスピレーションをもらうことが多いです。「時代を超えるものってなんだろう?」といつも考えていて。建築って息が長いじゃないですか。100年、200年、さらに長いスパンで残り続けるもの。それを考えると、こういうやかんやうつわも100年、200年後も残っていてほしい。だから、博物館にあるような古いもの、2000年前の器や道具の造形から得ることはすごく大きいですね。
—写真家ホンマタカシさんが撮影した、ちいさなやかんの写真集『Little Kettle』(白船社/2022)はどのような経緯でつくられたのでしょうか?
雑誌『なごみ』でホンマさんが茶室の連載をされているときに、知人のスタイリストがやかんと炉のセットを載せてくれたんです。それを見ていてくれたようでホンマさんが編集部の方に問い合わせしてくれて、嘘だろうと思いましたけど、注文してくださって(笑)。でも、お会いしたことはなくて。その2年後ぐらいに、奈良で工務店を経営されている方が、ホンマさんに仕事の依頼をした際に、奈良の工房にホンマさんを連れて来てくださったんです。それで、やかんでお茶を入れたら、すごく気に入ってくれて、次の日には「何か本を一緒につくりませんか?」と提案してくれました。
—やはり、金工とお茶は密接な関係にあるんですね。
そうですね。道具をつくるにあたって、茶道と中国茶の両方を習っていたのですが、特に茶道は、道具とその配置、順序がものすごくきっちりと決まっており、それは合理性から来ているんですね。実際お稽古を重ねていくとなぜその位置でなくてはいけないのか、その理由がわかるというか。座った状態で全部が手に届くように、無駄なくお茶を点てることができるよう突き詰めて考えられているという点に感銘を受けますし、そういった茶道の所作から空間の設計、季節の室礼まで全てが繋がっています。学生の頃からですが茶室の設計にはものすごく興味があります。一方で、中国茶は道具組みの自由さが楽しいと感じその世界に足を踏み入れました。ただ歴史はものすごく深く、お茶の種類も星の数ほどありそれによって道具も茶器も変わります。そちらにも長い歴史の中で培われた道具の合理性があります。金属はお茶の世界では脇役ではあるのですが、それを踏まえながらもこの現代において金属でできることの可能性を広げていきたいという思いはあります。一杯に懸けるお抹茶の力強さと、何煎も淹れながらその変化を楽しむ中国茶は全く違ってどちらも魅力的で面白いですね。
—金属は使っていくと経年変化していきますが、自分の元から離れた作品たちのその後は気になるものですか?
使い方、環境によって、人それぞれ、全く違う育ち方をするんです。今修理で帰ってきているものが、銅でつくり銀メッキを施した急須なのですが鈍い銀色に育っています。お料理屋さんでお酒を出すときに使われていて、冷蔵庫に入れ冷やした状態で使用しているので汗をかいた水滴が幾つも重なり、美しい表情を生み出していました。火力の強さでも変わりますし、ガスの質が違うと少し青みがかったり、空気中の成分によっては黄色っぽくなったり。それぞれの場所で変化したやかんは、自分ではつくれない何か別の作品に姿を変えています。それがとても面白いと思っていて。経年の美しさや面白みはそのそれぞれに異なる表情にあるなと。ちょうど2年前、京都の「HIN / Arts & Science」で展示をしたときに、新作展示とは別の空間で、知り合いが何年か使っているやかんを集めて展示したんです。それぞれに変化した作品たちが一堂に並んだ姿は壮観でした。お客様からもとても好評をいただきました。10年後くらいにまたぜひやりたいですね。
—丁寧にケアをすればいいというわけでもないんですね。
意外とやかんは毎日ガンガン使うのが一番。使わずに閉まっておくのはもったいない。水を入れっぱなしにして、毎日継ぎ足しながら沸かす、という方が一番綺麗に保てます。あとはよく撫でてやることですね(笑)。つやつやに育ちます。
—日本国外での個展と日本での個展、反応はやはり違いますか?
中国、韓国と台湾は同じアジアだからか、経年したものがみんな好きなんですよね。だから、展覧会に持っていくとみんな育った状態のものがほしいと言うんです。もちろんそれらは売らないんですけど。でも、2019年にカナダのトロントで個展をしたときは、経年に対してどんな反応があるかちょっと不安でした。結果は、アジアと何も変わらず、みなさん経年したものも新しいものも同様に受け入れてくれました。どの国でもお湯は沸かしますし、お湯を沸かす行為自体はとても原始的なものですよね。自分がほしくて始めましたが、意外と世界共通の普遍的な道具かもしれないと今は思っています。
—2024年からアトリエを東京に移されましたが、その理由は?
12年奈良で暮らしましたし、アトリエが手狭でもあったので、そろそろ広いところに場所を変えてもいいかなと思ったんです。もともと関東出身で親や姉も東京にいますし、そろそろ戻ろうかなと。それと、一人でできる作業量の限界も感じていて、お手伝いの人を入れたので、分業にできるところはしていけるように、環境と状況を変えたいなという思いで戻ってきました。
—最後に、今後、挑戦したいことはありますか?
ここ最近は現代美術のギャラリーTARO NASUの所属アーティストのRyan GanderやSimon Fujiwara(サイモン・フジワラ)とコラボレーション作品を作るなどアートとしての機会もいただくようになりました。NOIR KEI NINOMIYA のショーのヘッドピースをつくらせていただいたことも大きな経験でした。工芸だけの領域にとらわれず今までやったことがないことに挑戦してみたいなと思っています。空間をつくるプロジェクトもいつかやってみたいなと今は想像を膨らませています。