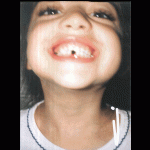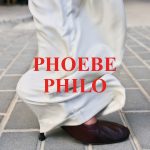Martin Parr(マーティン・パー)が集積する、「Small World」という現実の断片
Photography: Chikashi Suzuki
Martin Parr
photography: chikashi suzuki
Interview & text: tomoko ogawa
独自のユーモアのセンスで切り取られた、人間への深い関心と、そこに垣間見える現代社会への皮肉。英国のフォトジャーナリストのMartin Parr(マーティン・パー)は、40年以上にわたって、世界を旅しながら現実の場所にいる、現実の人々にカメラを向けてきた。彼が一貫して追い続けているテーマのひとつが「マスツーリズム(大衆観光)」である。
1994年、Parrは報道集団マグナム・フォトに所属するが、選考時は投票権を持つメンバーの半数から反対され、物議を醸した。翌年、パリで開催した個展「Small World」では、マグナム・フォトの創設者の一人であるHenri Cartier-Bresson(アンリ・カルティエ=ブレッソン)から、「あなたは私とは全く違う惑星から来た人だ」とジャッジするファックスを受け取ったという。Parrの写真が、それまでの報道写真の枠組みとは一線を画す、異端ともいえる表現だったことを象徴するエピソードだ。2022年には、そのときのファックスと自らの返信を挟んだ写真集『LES ANGLAIS / THE ENGLISH』を、「Reconciliation(和解)」と題した展示とともに発表。かつての批判をもユーモアとまなざしの一部に変える姿勢からも、Parrという写真家の独自性が垣間見える。
現在開催中のKYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭2025では、建築家・安藤忠雄が設計した「TIME’S」を会場に、代表作「Small World」が展示されている。長年にわたり撮影されたシリーズに加え、開催直前に京都で撮り下ろした新作もスライドショー形式で公開されている。2021年に多発性骨髄腫と診断され、治療を続けながらも旅をやめず、今もなお目の前の現実を写真に収め続けるMartin Parr。彼はなぜ、人生や世界を、愛をもって面白がることができるのか――。その答えは、彼の写真の中に息づいている。
Martin Parr(マーティン・パー)が集積する、「Small World」という現実の断片
Photography
—あなたの写真は独自のドライなユーモアと皮肉がありながらも、今回のKYOTOGRAPHIEのテーマ「HUMANITY(人間性)」でもある人間性に対する好意的なまなざしを感じさせます。あなた自身は、フォトジャーナリストにとって必要な資質は何だと考えていますか?
まず人が好きでなければならないと思います。それは重要かなと。人生は面白いし、人も面白い。だから、ユーモアを取り入れるのは良いことですね。私の写真にユーモアがあるものがあるのはそのためです。
—人が好きということは、人と会話をすることもお好きなんですか?
いえ、いつもそうというわけではありません。撮影の種類によりますね。ポートレートを撮るならそうですが、観光地のような場所を撮る場合はそうではないですね。
—なるほど。あなたはドキュメンタリー写真をどのように定義しますか?
世界中の現実の場所にいる、現実の人々の写真だと思います。
—何をもって良いドキュメンタリー写真だと判断されるのでしょう?
写真家と被写体の間のメッセージとつながりが明白であるときです。ただ一枚の写真だけでは判断できません。一連の写真を見る必要がありますね。
—あなたは写真を撮るだけでなく、動画も撮影しますし、展示会を開催したり、あらゆる形態の作品集をつくったり、写真や作品集を収集したりとその活動は多岐にわたります。幅広く活動する理由とは?
私は西洋世界の余暇の過ごし方と、彼らが自由時間に何をしているかに注目していますし、それが主なテーマとなっています。そして、私は様々なことをするのが好きですし、そうするのは良いことだと思っています。外の世界はとてもクレイジーなので、刺激を受けないなんてありえないでしょう?
—とはいえ、かなりの量の写真集を刊行されていますよね。
森山大道や荒木経惟ほどは多くありませんけどね(笑)。一生懸命働いているし、たくさんのプロジェクトがあるので、それらの多くを本にするのは良いことかなと。本になれば、永遠に残りますし。本は捨てられませんから。
—編集して、プロジェクトを完成させる過程がお好きなんですか?
その結果も好きですし、解決することが好きなんだと思います。
—あなたはソーシャルメディアを写真を大衆化するためのツールとして巧みに利用していますが、同時に、スマートフォンがもたらす世界をある種の皮肉を込めて捉えていますね。
そうですね。スマートフォンは過去20年間で社会に最も大きな影響を与えたものだと思います。すべてが変わりましたから。
—インターネットやテクノロジーの進化に対しては、肯定的ということでしょうか?
そうですね。ご存知のように、常に変化していますからね。と同時に、観光地に行っても、もう何も見ることなくスマートフォンで写真を撮るだけの人もいる、と言えるかもしれませんし。
—新しいテクノロジーやスマートフォンとどのように関わっているのでしょうか?
私はスマートフォンを持っていますし、財団にはSNSを担当するメンバーがいて、毎週何を投稿するか話し合っています。毎週、異なるストーリーがあり、私をフォローしてくれる人たちと連絡を取り合うことは重要です。私たちの財団から新しい本が出たときは、SNSで告知し、人々がそれを買ってくれる。
—自己宣伝のために使っていて、例えば、多くの若い世代がしていると言われているような自己表現のためではないと。
どちらかというと、フォロワーとのコミュニケーションのためだと思います。でも、若者たちと少し重なる部分もあると思います。彼らもフォロワーを増やそうとしているわけですからね。
—写真における真実とフィクションの境界線は、見る人次第だとは思いますが、プロパガンダ写真が意図的な嘘だと仮定すると、今日のソーシャルメディアの状況をどう見ていますか?ソーシャルメディア上の画像は嘘だと思いますか?それとも本当だと言えると思いますか?
ソーシャルメディアを利用する人は、より正直な傾向があると思います。もちろん、常にありきたりな表現もありますけどね。だから、何が真実味を帯びているかを見極める必要がある。なぜなら、写真家は自分の作品の中で脆弱性を示すことがあるからです。
—確かに、弱さや痛みのある作品には真実味を感じますね。
明らかに、ソーシャルメディアで自分のしていることについて大げさな主張をする人もいますが、それは人々にとって精神的にあまり良くないものだとは思いますね。
—あなたは写真家として商業的に成功しながらも、非常に主観的で個人的なアプローチを維持していますが、両方のバランスを取る秘訣とは?
私はただ、人々が求めるMartin Parrの写真を撮っているだけです。ご存知のように、ファッションブランドは最近、華やかさよりも本物らしさを求めているんです。私はそれをうまく提供できます。ごく最近、ファッションに関する本『FASHION Faux PARR』を刊行しました。
—あなたは日本を何度も訪れ、日本にまつわる作品集も刊行していますが、最初に来た頃と比べて、どのような変化がありましたか?
先ほどお伝えした通り、スマートフォンの登場がもちろん影響していますが、世界中の他の場所と同様に、私が初めて来た頃とは異なりますよね。今、日本の写真はヨーロッパやアメリカでも知られていますが、当時は本当に見過ごされていましたから。日本に来て、特に『provoke(プロヴォーク)』時代の本をたくさん見つけたことは、非常にエキサイティングで刺激的でした。批評家Gerry Badger(ジェリー・バジャー)と私とが編集した写真集の歴史シリーズ『The Photobook』の第一巻にも収録しています。
—古本を探す方法も違ったのでしょうか?
今は、神保町に行けば、すべての書店がそこに揃っています。以前は、写真家Bruce Gilden(ブルース・ギルデン)の案内のおかげで、東京郊外の店をあちこち回っていました。彼はすでにいくつかのリサーチをしていたので。彼が私に日本の写真集を紹介してくれたんです。
—そうだったんですね。今でも感じる日本の良い面はありますか?
もちろん! 食べ物も好きですし、電車の効率の良さも好きです。イギリスでは時間通りに運行しませんからね。すべてがとても整然としていることが非常に印象的です。
—確かにそうですね。個人的に、イギリスと日本には共通する特徴があるようにも感じますが。
ええ、私たちは古いものと新しいものが混ざり合った島国ですから。
—初期の作品を振り返ったときに新たな発見はありますか?
特にはないのですが、時々、コンタクトプリントを見直して、見落としていた画像を掘り起こすことはあります。私は多発性骨髄腫という種類の癌を患っていて、足が不自由なので、もう長くは写真撮影ができないかもしれない。だから、すべてのコンタクトプリントを見て、アーカイブすることで、旅立ちの準備をすることができるかなと考えています。
—と言いながらも、旅を続け、写真を撮り続けていらっしゃいますよね。
京都に来たい気持ちを抑えきれませんでした。私の観光プロジェクトの新たな写真に加えるのに、これほど素晴らしい選択はありませんから。桜が満開なのもボーナスです(笑)。
—誰もが桜の写真を撮っていますからね。セレブリティを撮るかのように。私も撮りましたし。
もはや日本中が熱狂するお祭りですね。
—あなたの作品を見ていると、アイデアを探求する意欲は年齢とは関係ないのだなと感じます。好奇心を駆り立てるものは何ですか?
なぜかって? ただ自然にあるものなんです。なぜかと言うと、あなたを見ているだけでもすべてが興味深いからです。例えば、日本のインタビューはいつもたくさんの人が同席しますからね。あなた以外、誰が何をしているのか、隣でパソコンを開いている人が何をしているかもわからない。私は、今この部屋にいる人々が何をしているのかを理解しようとしているんです(笑)。
—よく聞かれる質問だと思いますが、若い写真家に向けて、先ほどおっしゃっていた被写体と有意義なつながりを築くためのアドバイスは?
適切な被写体を見つけ、近づき、写真家と被写体の間の関係を築く必要があります。それが実現すれば、そこから発展し、彼ら自身の個性が出てくるでしょう。それは簡単なことではありません。ほとんどの写真家は怠けすぎだと思います。
—なぜ怠慢だと?
写真は非常に早く何かを提供してくれるものなので、今日の午後にも本をつくることができてしまう。もちろん、ひどい出来になるでしょうけどね。つまり、多くの人が良い作品をつくるよりも、有名になることに興味を持ちすぎているとは思いますね。
—それはそうかもしれません。でも、怠けているというより、自信や勇気がないという可能性もあるのではないかなと。
そうですね。でも、彼らはプロジェクトを解決はしていませんよね。ほとんどのプロジェクトは未解決のままです。毎年何百冊もの本が出版されていますが、非常に良い作品はごくわずかです。そうであっても、写真家は取り組み続けなければならない。だから、怠けるべきではないんです。
—放っておかずに解決していくことが、ごくわずかのいい作品づくりにつながっていくと。写真家ではありませんが、肝に銘じておきます。また、あなたがブリストルにマーティン・バー財団を設立し、アーカイブや功績を開放していること自体が、次世代へのサポートになっていますね。
財団では、本を集めたり、雑誌を入手したり、展覧会を開催したりしています。その中に私自身のアーカイブと、他の多くのイギリス人写真家のアーカイブがあります。見過ごされてきた写真を積極的に支援したり、新しい写真を見つけることもあります。
—その理由は、過去に、特に若い頃にそのようなサポートが不足していたと感じていたからですか?
そうですね、当時は本当に支援を受けられませんでした。同じような問題を抱えている友人たちがいただけで。ご存知のように、私が70年代初頭に大学に通っていた頃は、写真という分野はそれほど発展していませんでしたから。
—あなたの個人のオフィシャルサイトも作品のアーカイブが見れるだけでなく、基本的なインタビューの質問と回答までありますし、動画もあって、とてもオープンですよね。
財団のオフィシャルにも、「Sofa Sessions」という名目でソファーでインタビューされたものがいくつかアップされています。目的は、写真家が何を言いたいのかを聞く機会を与えるためです。それほど長くはなく、20分から25分程度のものです。多くの人々には集中力がないことを知っていますから。
—それ以上の分数を聞けるという人もいるとは思いますが(笑)。
そうかもしれません、知的好奇心がある人であればね。
—今回、KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭に参加され、京都で滞在制作されていかがでしたか?
面白かったです。撮影も編集してスライドショーにする過程もすべて楽しかったですね。
—スライド上映の際にかかっている音楽はご自身で選ばれたんですか? ユニークで楽しげな曲調で。
陽気という言葉がしっくりきますよね。KYOTOGRAPHIEの方々がいくつか提案してくれた曲からこれというものを選びました。
—今年の夏にクルーズの撮影に行かれる予定だそうですね。クルーズにはどのようなイメージがありますか?
よくわかりませんが、人々が1日に5回食事をしているとかですかね。年配の人向けのものだと思います。でも、私ももう72歳で年寄りなので、行ってもいいでしょう。
—どんな作品になっていくのでしょう?
過去に『Cruise Memories』というクルーズの作品集をつくったことはあるのですが、クルーズの写真はまだ十分には撮ってきていないので、その空白を埋めることを楽しみにしています。半年後にまた連絡をいただけたら、どうだったかをお伝えできると思いますよ。