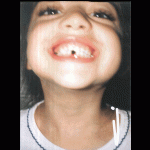写真の“弱さ”と遊ぶ。スティーブン・ギルが映す、世界のかたち
Stephen Gill
photography: naoto kobayashi
interview & text: chikei hara
2003年にロンドン東部のマーケットで手に入れた安価なカメラを使い、その場所に残る痕跡と、まだ存在しない手がかりをとらえた写真集『Hackney Wick』を発表して以来、写真という知覚のメディアを介して、世界の見方そのものを問い続けてきた写真家の Stephen Gill (スティーブン・ギル)。カメラの中に異物を入れたまま撮影する『Talking to Ants』や、現像液にエナジードリンクを混ぜて現代風景を像として浮かび上がらせた『Best Before End』など、その実験的な手法は常に写真表現のあり方を押し広げている。
2014年に拠点をスウェーデンへ移してからは、より遠い場所、より曖昧なイメージの捉え方から、自身の好奇心とコンセプトを形にしてきた。多くの人々から愛される穏やかさと知性を備える一方で、意思決定のプロセスにおける精確さと徹底した制作姿勢で知られる孤高の存在でもあるといえるだろう。現在開催中の「T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO」で展示されている代表作「Hackney Flowers」を前に、写真とともに生きるということについて、対面で話を伺った。
写真の“弱さ”と遊ぶ。スティーブン・ギルが映す、世界のかたち
Photography
ーロンドン東部ハックニーを舞台にした代表作「Hackney Flowers」(2007)は都市の自然を見つめた作品です。今回のT3ではそのシリーズを都市空間に再び置く形になりますが、あらためて都市へと戻すことについてどのように感じていますか?
もともとこのシリーズは一見自然を扱っているようでいて、実際には都市生活の中で見つめた自然が出発点にありました。だから都市で展示するというのは、ある意味でとても自然なアイデアだと思っています。制作から20年が経って、世界も自分も大きく変わりました。振り返ると AI が登場する以前から、すでに写真そのものへの不信感があった気がします。写真を撮ることは今でも好きですが、ストレートで記述的な写真だけに頼ることへの信頼は、2004年の時点で薄れていました。あの頃から、場所や対象を伝えるための別の方法を探し始めていたんだと思います。
ー新しい作品を始めるとき、どのようなものをよりどころにして撮る価値を決めているのでしょうか。
いくつもの要素が絡み合っていますが、まずは自分の手仕事をどれだけ理解しているかに関係しています。たとえばミュージシャンやピアニストが、自分の楽器を完全に理解している状態に近い。その上で、私はある時点から写真の“弱さ”を意識的に使うことを決めたんです。まるで目を閉じても演奏できるような状態に近いと言えばいいでしょうか。以前は撮っているうちに、表現の自由がどこかで制限されているように感じて、まるで透明な壁にぶつかるような感覚がありました。だからこそ、その壁の向こう側へ行く別の方法を探していたのだと思います。
ー制作を始めるときの原動力は、どこから生まれてくるのでしょうか?
私にとって被写体こそがすべてです。むしろ制作の初期段階では、写真そのものが障害になることさえある。だからこそまずは試しながら被写体と協働するという考え方にたどり着きました。自分の考えや意図を一方的に押しつけて作品を窒息させるのではなく、被写体が自ら語り出すのを助けること。その瞬間に立ち会えることが、私にとっての出発点なんです。

ー写真の弱点と遊びたいという思考へと変わり始めた転換点はどこにあったのでしょうか?
2001年、この年のことはよく覚えています。その頃にはすでに20年ほど本格的に撮り続けていて、もう写真の可能性はやり尽くしたと感じていました。写真そのものにも、自分自身にも少し疲れを覚えていたんです。そこで、これが最後の写真集になるかもしれないと思いながら、プラスチックレンズを使って『Hackney Wick』を制作しました。写真の情報を削ぎ落とし、色を抑え、明瞭さを奪うように撮るうちに、不思議と場所の気配や人の感触が、むしろいっそう強く残ったのです。むしろ意志が遮られずに立ち上がることに気づいたんです。写真を単なる記述の道具として使わない——その感覚への気づきが、私にとって大きな転機となりました。それ以降は少しずつ自分を写真の後ろへ退かせ、被写体が一歩前へ出て自然に前景化するような感覚をとらえるようになりました。そうすることでより客観的になれるのではないかと考えるようになったのです。
ーNobody Booksでは書籍という形式で精力的に発表を続けていますが、先ほど話されていた“一歩引く”感覚は書籍制作にも関係していますか?
まさしくそうです。『Buried』(2004-2006)を作っていたころにはすでにその意識があって、場所と私が半々で共同作業をしているように感じていました。その感覚は『Hackney Wick』のあとも続いています。たとえば『Talking to Ants』(2009-2013)では、カメラの中に物を入れて偶然と意図のあいだを探る試みを行いました。まるで目を閉じて自転車をこぐような感覚に近かった。自分の選択に対して少し不確かさを介入させることがむしろ刺激となったんです。
それ以降の作品でも、多くは意図的にコントロールを手放すという姿勢で取り組んでいます。スウェーデンへ移ってから制作した作品は、ほとんど自分の物理的な存在がない状態で撮りました。写真を撮っているのは鳥たち自身で、私はその場を演出する指揮者のような存在なのです。そして『The Pillar』(2015-2019)では写真家としての私の姿は完全に消えています。

現在開催中の「T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO」にて展示されている Stephen Gill の作品「Hackney Flowers」
ースウェーデンに移住されてから約10年ほど経つそうですね。現在の暮らしをどのように受け止めていますか。
おそらく12年くらいになると思います。スウェーデンに移ったのは、少し立ち止まりたいと思ったからなんです。ロンドンにいた頃は、すべてのことが仕事や作品づくりに結びついてしまっていて、視覚的な刺激も多すぎた。常に制作に引き戻されるような感覚があって、次第にそれがストレスになっていました。だからスウェーデンに移ればもう少しゆっくりできると思ったのですが、実際はそんなふうにはならなかった (笑)。結局のところ、問題はロンドンではなく自分自身だったんです。
それでも嬉しいのは、いまは周囲にすぐに反応するのではなく、導かれるように身を任せて風景の声を聴くことを少しずつ学んでいる気がすること。不思議なことに自然というものは、子どものころからずっと私を強く惹きつけてきたと思います。ただ、長く都市で生きてきたからこそ、スウェーデンに着いて「これからは自然を撮るんだ」とは言いたくなかった。むしろ、風景のほうから学びたいと思ったんです。今の生活はとても理にかなっていると感じています。
ー制作のエネルギーやペースという面では、いまどのように感じていますか?
正直に言うと、アイデアはこれまで以上にたくさんあるのに、エネルギーが追いつかなくなってきています。この数年で大きな作品を4つほど作りましたが、どれも発表までにおよそ9か月の制作が必要で、その体力があるかどうか少し自信がなくなってきました。最近になって初めて、自分のペースに追いつけないと感じるようになった。でも3年前に完成させた作品も、撮り始めてから3年かかったので、ものごとがゆっくり進むことは決して悪いことではないと思っています。
幸いなことに、今は誰かに依頼されて作っているわけでも、締め切りを課されているわけでもありません。出版社と契約しているわけでもないので、時間の制約がないんです。私は単純に作ることが大好きなのです。制作のプロセスそのものが、すでに私を十分に満たしてくれる。もちろんいずれは形にしたいという気持ちはありますが、本当に嬉しいのは、まさに作っているその瞬間なんです。
ー現代のような時代において、書籍のような二次元的な形式でのアウトプットを、どのように位置づけていますか?
特に今のようなデジタルの時代では、私たちは常に膨大なものを吸収し続けており、気づけば受け取る側にまわってしまっています。だからこそ、何かを作るという行為が本質的に大事だと感じるんです。それは絵でも、陶芸でも、文章でもいい。手を使って自分のまわりの世界と関わり、考え、反応すること。そうした能動的なあり方こそが大切だと思っています。
ー紙とペンだけでも驚くほど満たされることがあるし、むしろこれほどまでに書くことや描くことが意味を持つ時代は、これまでになかったのではないでしょうか?
今の私は、以前よりも言葉や絵画に強く信頼を置いています。そして、写真よりもむしろ絵画のように、手の痕跡や時間の蓄積を宿す媒体に惹かれています。なぜなら情報を超えた、存在そのものに関わる力を感じるからで、おそらくこの二つは、他のどんな表現よりも長く生き残っていくのではないかと思います。

ーあなたの活動は現代アートに非常に近いものがありますが、それでも自分を写真家として定義し続けていますよね。それでも写真から離れないのはなぜでしょう?
私はやはり自分を写真家だと思っています。おそらくどんな時も写真を実践の中心に置いてきたからでしょう。正直に言えば、長いあいだ写真のポップな文脈や市場価値観から距離を取ろうとしてきたし、関係を断ち切りたいと思ったこともあります。それでも最終的に気づいたのは、自分をいちばん明晰にしてくれる唯一のものが、写真だということでした。だから私は、写真とともに生きるしかないんです。
ー写真で表現できない、あるいは写真では捉えきれない経験というものはあると思いますか?
私にとって、写真には常に2つの支配的な側面があります。ひとつは、あとからイメージとして見る対象であるということ。もう1つはその写真を撮った特定の日の記憶が同時にそこに流れているということです。
たとえば、その日どんな天気だったか、どんな気持ちで歩いていたか、雨に濡れていた、道に迷った……そういう細部です。そうした記憶が、イメージの下層にはいつも流れているんです。でもそこには注意が必要で、どんなに素晴らしい経験であっても、その写真が自動的に良い作品になるわけではないのです。ときには経験の熱が冷めるのを待つことが必要で、そうでないと作品が思い出の中に閉じ込められて死んでしまうことがあるんです。なのでそこでも写真と距離を保つことが大事なんです。
ーギルさんの言葉や作品には経験する時間や言葉にしにくい感覚との対話が常にありますよね。
今の私は結果よりも経験そのものに惹かれています。なぜなら、それがどこか奇妙で説明できない感覚だからです。私には2人の子どもがいるのですが、彼らのことを考えるとき、結果が必ずしも到達点ではないと感じます。むしろ何かを経験すること、記録さえせず、反応さえしないことなど、そうした行為のほうが本当に重要だと思うんです。若い人たちに伝えたいのは、まず体験から始めてほしいということです。今の時代は、ミュージシャンも映像作家も写真家も最終的にはみんなコンピューターの前に戻らざるを得なくて、あらゆる表現がデジタルに還元されてしまう。でも画面やデータよりも前に、世界と直接かかわることを出発点にしてほしいと思います。