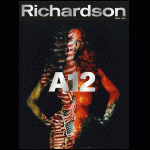大月壮士が打ち出す「黒の無衝撃」は世界を変えうるのか。若きスターデザイナーが見据える理想郷
Soshi otsuki
photography: Riku Ikeya
interview & text: Shunsuke Okabe
世界に誇る日本人のスターデザイナーの誕生だ。その名は、大月壮士。若手デザイナーの登竜門である「LVMHプライズ 2025」においてグランプリ受賞。ZARAとのコラボレーションコレクションの発表。そして現在、フィレンツェで開催されている「ピッティ・イマージネ・ウオモ」のゲストデザイナーとしてショーを開催。しかしながら、大月はこの状況を極めて冷静に受け止めている。まるでこのブレイクスルーが、全て想定の範囲内であったかのように。無限に広がる可能性を前にした、今の心の内を訊く。
大月壮士が打ち出す「黒の無衝撃」は世界を変えうるのか。若きスターデザイナーが見据える理想郷
Fashion Design
— 昨年は「LVMHプライズ」の受賞を筆頭に、ブランドとして飛躍の一年になったかと思います。受賞時の心境はいかがでしたか?
ブランドを立ち上げた直後の2016年にも「LVMH プライズ」にノミネートされたのですが、当時は目の前のことに必死すぎて、あまり記憶にないというのが正直なところです。今回はより自信を持って臨めたので、グランプリの名前が呼ばれたときの感動もひとしおでした。
— 審査の過程では Nicolas Ghesquiere (ニコラ・ジェスキエール) や Stella Mccartney (ステラ・マッカートニー) 、Jonathan Anderson (ジョナサン・アンダーソン) をはじめ、ファッション界のレジェンドたちの講評を経験されました。とくに印象的だったコメントや、手応えを感じた点はありましたか?
プレゼンではブランドとしてのこれまでの歩みや今後のビジョンなどを伝えるのですが、特に手応えを感じたのはブランドの哲学です。
— 具体的にはどういった内容でしょう?
まずブランドのコンセプトとして掲げている、日本人の精神性とテーラードテクニックによって作られるダンディズムの提案というアプローチです。テーラリングというのは基本的にイギリスにルーツがあり、ヨーロッパやアメリカで独自の発展を遂げてきました。そんな中で、日本独自のトラディショナルなテーラリング、いわば着物に代わる“ジャパニーズトラディション”を確立して発展させていきたいということを伝えました。
— “ジャパニーズトラディション”のテーラリングを定義づけるとしたら?
まず一つ具体的にリファレンスとして取り入れたのは、サラリーマンのスーツスタイルです。2025-26年秋冬コレクションでは、バブル時代にあたる1980年代のパワースーツをベースに、リラクシングなムードを取り入れた新しいテーラリングのありかたを追求しました。
— ブランドを立ち上げるまでの経歴について伺ってもいいですか? ファッションに関心をもったのはいつ頃から?
ファッションに興味を持ったのは高校生の頃。それまでは、自分が着るものに特に疑問を持たず、親が買ってきた量販店の服を着ていました。高校に入ってから同級生が少しずつファッションに目覚めて、自分も関心を持つようになりました。高校の担任の先生が日本の伝統芸能が好きで、国語の授業の傍ら、日本の文学や歌舞伎、落語について教えてくれたんです。その影響で、何か表現したり、ものづくりに興味が湧いて。同じ頃 YouTube が出てきて、Hedi Slimane (エディ・スリマン)の時代の DIOR HOMME (ディオール オム)のコレクション映像を見て衝撃を受け、自分もこの道に進みたいと思いました。
— 周囲の反応はいかがでしたか?
漫然と高校を卒業したら大学に進学して就職するのが普通だと思い込んでいたので反対されるかと思ったのですが、意外にも自然に受け入れてくれました。母親が裁縫好きだったり、祖母が洋裁を仕事にしていたり、父方の叔父がモード学院を出てデザイナーをしていたり、今考えればファッションが身近にある環境だったことも大きいですね。
— 両親に勧められ、文化服装学院に入学。在学中にここのがっこうにも通われています。当時はどんな学生でしたか?
最初から海外で成功してやるという意識が強かったので、入学早々にコンペティションなどにも積極的に応募していました。絵が苦手なので全滅でしたが。日本で通用しないなら、留学してやろうと意気込んで資金を貯めるために治験のバイトをしたこともあります。
— 治験の体験談、初めて聞きました。
周りでも結構いましたよ。短時間で稼げるので。勧めるわけではないですが。
— 当時はどんな作風でしたか?
入学時から考えていたのは、テーラリングを武器にしようということ。当時憧れていたのは、Hedi Slimane や Alexander McQueen (アレキサンダー・マックイーン)。王道のテーラリングを修得しながら、モードの世界で新しい表現をしているのがとにかくエキサイティングで。彼らのコレクションを参考にすることもあったのですが、どれだけ技術を磨いても真似事にしかならないことに気づいたんです。自分らしい表現を突き詰めた結果、昔のサラリーマンのスーツの着こなしをモチーフに、新しいスタイルを定義するというアプローチに行き着きました。
— 日本独自の美意識やモチーフは、過去のコレクションでも度々取り入れられてきました。例えば2019年春夏コレクションでは映画『火垂るの墓』を想起させるようなスタイリングやビジュアルの見せ方、2023-24年秋冬コレクションでは喪服をイメージしたような袴や数珠を合わせたり。
日本人であるからには、日本らしさを突き詰めるのが一番強いと思うんですよね。海外の人から見たら、例えば数珠がどういう意味を持つのかは伝わらないかもしれない。でも、コンテクストまで掘り下げずとも、ざっくりとしたイメージで“日本的なもの”をうまく織り交ぜながら、あくまでファッションという共通のコードで繋ぎ合わせられれば良いなと思ってるんです。表層的なジャポニズムにはしたくない、日本人として、日本人らしいクリエイションをしたい、でも日本人じゃなくても伝わるスタイルとして提案したい。そんなことを考えながら日々模索しています。
— メンズファッションの世界において、ルールが確立されたテーラリングと、制約なき自由な表現が求められるモードは二律背反のような関係性にあるように思います。大月さんの中で、テーラリングとモードの関係性はどのようにとらえているのでしょう?
サヴィル・ロウで経験を積んだわけではないので、自分はあくまでモードの文脈に沿っていたいという意識はありますが、個人的にはニアリーイコールの関係だと思っています。例えば Hedi Slimane が提唱したタイトスーツも、Giorgio Armani (ジョルジオ・アルマーニ) が生み出したアンコンストラクテッドジャケットも、当時は明らかに異質な存在でしたが、時代とともに定番として浸透してきた。トラディショナルなものも、スピード感は違えど、時代によってトレンドがあって、そこに影響を与えるのがモードなのかなと。
— 逆に言えば、トラディショナルというルールがあるからこそ、その枠を超えたモードという表現があるとも言えますよね。普段デザインする上で、テーラリングのルールみたいなものは意識されますか?
もちろんトラディショナルを突き詰めると厳格なルールがあるんでしょうけど、あまりそこの境界線は意識していないですね。ルールを破った上で、ありかなしか。それって結局、全部“フェチ”で回収できると思うので。
— 大月さんのフェティシズムは?
なんだろう。具体的なデザインではないんですが、空気感として威厳を排除するようにはしています。スーツって威厳が出るじゃないですか。着ているとちゃんとした人に見える。でもその威厳を取り払いたいという意識は常にあります。
— ノンシャランな感じ?
ノンシャランってどういう意味ですか?
— 無頓着というか、飄々とした感じですね。
そうですね、リラックス感のあるスタイルはいつも意識しています。ルックブックとか見てもらうと分かるんですが、モデルにも猫背でポージングしてほしいんですよ。日本人って猫背が多いので。猫背フェチですね。
— 「LVMHプライズ」グランプリの受賞賞金は40万ユーロ (約7,200万円)。使い道はもう決めていますか?
まずは引越しですね。今は自宅兼アトリエで制作しているので、引っ越してアトリエスペースを構えます。あとは人ですね。パターンや生産管理は外部に委託しているのですが、デザインは一人で全てやっているので、それ以外の業務、例えば外部との連絡や、スケジュール管理や、あとは EC の運用を任せられるような人。『プラダを着た悪魔』のアン・ハサウェイみたいな人いないですかね(笑)。
— パリで活躍する日本人デザイナーで、意識している人はいますか?
世代的に比較的近いということもあり、Auralee (オーラリー) の海外での活躍ぶりには影響を受けています。
— Auralee の評判、すごいですよね。パリの老舗百貨店でも、気鋭のデザイナーをセレクトしたコーナーで唯一日本のブランドとしてフィーチャーされていたのが印象的でした。
しかも、Auralee のサクセスストーリーって、かなり異質だと思うんです。例えば、例えば川久保玲さんや山本耀司さんは、西洋の価値観にはない、全く新しい美の概念を提唱してセンセーションを巻き起こした。sacai (サカイ) の阿部千登勢さんは、ハイブリッドな素材の組みわせを使いながら、リアルクローズとしてのひとつの黄金比を見出した。でも Auralee の岩井良太さんって、そういうブレイクスルーみたいなのがないんですよ。
— Auralee の洋服って、もちろん実際に袖を通したらその素晴らしさが分かるんですが、いかにも海外受けを狙ったようなギミックは一切ないですよね。
一見すると何の変哲もないワードローブ。乱暴な言い方をすれば、オーディナリーなんですよ。それでも自然に海外で評価され、気付けばパリで地位を確立している。これこそ、ファッションの力で影響を与えているということだなと思うんです。川久保さんや耀司さんが黒の衝撃だとしたら、岩井さんはオーディナリーの衝撃だなと。
— オーディナリーの衝撃、言い得て妙ですね (笑) 。SOSHIOTSUKI は、今後どんな“衝撃”を与えたいですか?
ブランドイメージを変えたのは2025年春夏コレクション。
— ブランドとして、今後実現したい夢はありますか?
いつかパリで毎シーズンランウェイショーを開催できるくらいの規模にはしたいなと思っています。
— それ以外は?例えば路面店を構えたり、有名セレブリティに衣装提供したり。
あまり考えてないですね。デザインをしていて一番関心があるのは、自分が作り出したスタイルが、世の中にどう広まって定着していくかということ。ファッションを通じて、人々の考え方に影響を与えたいというのが一番の目標なので。
— SOSHIOTSUKI の洋服を通じて、どんな影響を与えたいですか?
これまで“なし”だとされていたものを、“あり”と思えるようになること。